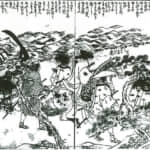兵卒の戦闘意欲を鼓舞した信玄の軍制とは?
武田三代栄衰記⑥
寄親寄子(よりおや よりこ)制を展開し、感状だけでなく褒美も支給

寄親寄子とは
軍役衆を寄子として配備されていた御譜代家老衆は、山県昌景、内藤昌秀、高坂弾正など限られていた。御親類衆や譜代家老衆の中にも地位の差があった。
武田信玄の軍勢は、他の戦国大名と同じく、譜代、本国内国衆、他国衆によって構成された。さらに、村町より諸役免許特権付与を通じて動員された、武田氏の直参(軍役衆、足軽、牢人)がこれに加わった。
譜代は、甲斐の武士たちで、なかでも侍大将は数百人を指揮する軍事指揮官で、山県・原・内藤などの大身の譜代が任命された。譜代は、自身の所領より動員した兵卒と、家来を独自に引率していた(これらは武田氏から「又被官」と呼ばれた)。また譜代の中から、旗本足軽大将に任命される者も多かったという。
国衆は、大小の規模の差はあるが、知行貫高千貫文以上の、城持の大身の武家で、「家中」(家風、洞中とも)の家来や、領内の兵卒を引率した。
信玄は、他国から来た牢人たちの中から、すぐれた人材を雇用し、戦功者は足軽大将に任命して、その他は足軽として、組下に編成した。また村町から動員された軍役衆は、軍勢の中で占める割合が多かったと推定されている。信玄は、彼らを組み合わせて、軍勢の編成が行われた。
まずその核となったのが、武田御一門衆と譜代家老衆である。彼らは寄親(よりおや/一手役、物主)に任命され、国衆と軍役衆(ぐんえきしゅう/寄子・同心衆とも)らを預かった。
さらに、武田御一門衆と譜代家老衆の一部は、先方衆(外様国衆、信濃・西上野・駿河などの占領地の国衆)を相備衆(組衆)として、信玄より預かったとされる。
甲陽軍鑑に記された先方衆らの組織とは
同書によると、武田御一門衆のうち、武田逍遙軒信綱(たけだしょうようけんのぶつな/信玄の弟)と一条信龍(いちじょうのぶたつ/信玄の異母弟)のみが、先方衆を相備にしていたという。
譜代家老衆では、山県昌景(やまがたまさかげ/駿河江尻城代、遠江・三河方面軍、駿河・遠江・三河・信濃の先方衆のうちより11氏)、内藤昌秀(ないとうまさとよ/西上野箕輪城代、関東方面軍、上野の先方衆より7氏)、馬場信春(ばばのぶはる/信濃牧之島城将、飛騨・越中方面軍、飛騨・越中・駿河の先方衆より6氏)、春日虎綱(かすがとらつな/信濃海津城代、信越方面軍、信濃川中島衆17氏)、土屋昌続(つちやまさつぐ/信玄側近、信濃先方衆より7氏)が、先方衆を相備衆として信玄より預かっていたという。先方衆の中の依田(芦田)信守・信蕃父子は、同じ信濃先方衆丸子(丸子城主)と武石氏(武石城主)を預かっていたといい、信玄より信頼されていたようだ。
信濃真田、依田(芦田)氏と西上野小幡氏は所領規模が大きく、軍勢も多く、自分たちだけで一軍を編成できた。
監修・文/平山優
(『歴史人』12月号「武田三代」より)