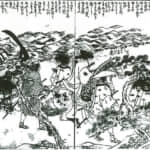信玄が乗り越えた父・信虎の追放と嫡男・義信の死
武田三代栄衰記④
今川氏親との戦の最中に生誕した信玄と信虎の事情

その遺徳を偲んで、県内外の有志から浄財を募って建てられた、甲府駅前にある「武田信玄公之像」。昭和60年11月に現在の場所に移設された。毎年12月には像の大掃除が行われる。
武田信玄が誕生した大永元年11月3日、武田家は滅亡の危機にあった。父・武田信虎(のぶとら)はこの時、駿河今川氏親(うじちか)の大軍の攻撃を受け、甲府郊外にまで攻め込まれていたのだ。
武田家の譜代ですら、信虎の動員に応じぬ有様で、甲府陥落と武田家滅亡は目睫(もくしょう)の間に迫っていた。信虎は、残余の軍勢を率いて、甲府郊外飯田河原に布陣し、臨月の大井夫人を要害城に待避させ、決戦に臨んだ。
その前月である10月16日、飯田河原(いいだがわら)合戦で信虎は奇跡的勝利をおさめた。その直後に誕生したのが信玄である。信虎は戦勝後の嫡男誕生を喜び、勝千代と命名したといい、意気揚がる武田軍により、まもなく今川軍を壊滅させた。平穏が戻ると、勝千代は生母大井夫人に抱かれて躑躅ケ崎(つつじがさき)館に入った。武田家中の人々は、勝千代を「御曹司(おんぞうし)様」と呼び、敬っている。
人口に膾炙(かいしゃ)した、信虎と信玄父子が不仲であったという確かな証拠はない。すべては『甲陽軍鑑(こうようぐんかん)』が出典である。
確実な史料を追っていくと、信虎は信玄に「太郎」の仮名を与え、元服時には室町幕府将軍足利義晴(よしはる)に要請して、偏諱(へんき)を拝領することに成功。彼を「晴信(はるのぶ)」と名乗らせ、信虎の官途「左京亮(さきょうのすけ)」をも継承させている。そればかりか、冷泉為和(れいぜいためかず)らを迎え、武田家を代表して歌会を主宰させているほどである。間違いなく、信玄は父信虎の後継者として処遇されていた。
ではなぜ、信玄は父を追放したのか。それは、永年の戦乱で荒廃した甲斐の状況と、連年のように押し寄せる飢饉、災害、疫病、物価暴騰が背景にあった。
とりわけ、信虎が周囲の諸大名と対立していたが故に、路地封鎖(経済封鎖)を受けることがしばしばで、これが物価暴騰と飢饉に拍車をかけていた。甲斐の人々は、これを信虎の不徳(悪逆非道)の結果をみなし、怨嗟(えんさ)を募らせていた。信玄は、内乱再発の危機を回避すべく、父追放に動いたのである。
今川方の第2次川中島合戦調停案に信玄と義信の対立
父信虎追放と並んで、信玄が冷酷な人物と指弾される原因となったのは嫡男義信の死である。『甲陽軍鑑』によると信玄は義信を可愛がり、自身の後継者として大切にしていたといい、義信元服時の信玄の振る舞いは息子を思う父親の心情にあふれ家臣らが感涙に咽(むせ)ぶほどであったという。
ところが、弘治元年の第2次川中島合戦において、信玄と義信の対立が表面化する。俗に200日対陣と呼ばれる長期戦で、武田と長尾両軍は疲弊していた。そこへ、今川義元が和睦の仲介を働きかけた。だが、義元が提示した調停案に、信玄は不満であったらしく、交渉は難航した。
すると、今川方の調停に難色を示す父信玄を、義信が激しく非難したらしい。閉口した信玄は、彼が一族とみられる人物に出した密書で「義信は今川家のために父子の関係を忘れ困惑している」「こちらでは、(景虎との)和睦交渉を一時中断している有様だ」と嘆くほどであった。
当時、今川氏は、斎藤道三・織田信長の攻勢を受け、守勢に立たされていた。そこで義元は、第2次川中島合戦を収め、信玄とともに敵方に当たろうと考えていたらしい。一悶着あったものの、義元の仲介で、第2次川中島合戦は終了した。この時から、義信が同盟国今川氏に心を寄せる人物であったことが確認できる(義信正室は義元息女嶺松院/れいしょういん)。
永禄8年4月、東美濃で武田と織田の衝突が発生した。信長は急ぎ、軍勢を退かせ、信玄に接近し、関係改善に動いた。そして永禄8年9月9日、信長は、織田忠寛(ただひろ/津田一安)を使者として信玄のもとに派遣し、信長養女苗木氏(遠山直廉女、龍勝院殿)を、信玄の息子諏方勝頼のもとに娶(めあ)わせることを条件に、同盟締結を申し入れた。信玄はこれを了承し、11月、勝頼と龍勝院の婚儀が実施されることとなった(甲尾同盟の成立)。
嫡男武田義信事件と心優しき父親としての信玄
義信はこれに反発し、重臣飯富虎昌(おぶとらまさ)らとともに信玄暗殺の謀議を計画した。義信派の決起は、10月初旬であった。だがこの密謀は発覚し、義信派は捕縛され、失敗に終わった。信玄は、10月15日、飯富虎昌らを処刑しその他の義信派の家臣を国外に追放した。義信は、織田との同盟は、今川氏との同盟破綻に繋がることを憂慮し、三国同盟維持と反織田の路線を堅持しようとしたのだろう。
この時はまだ信玄は、義信を廃嫡にしようとは考えていなかったようだが、義信が翻意しなかったらしく、父子の関係は拗(こじ)れ、臨済宗の高僧らが仲を取り持とうとしたがうまくいかなかった。やがて義信、廃嫡され甲府東光寺に幽閉されたと伝えられる。そして永禄10年10月19日、義信は死去した(享年30)。信玄は、自らの後継者を失うことになった。
弘治2年、信玄の次男龍宝が天然痘に罹患し、生命は取り留めたものの、失明してしまった。信玄はこれを悲しみ、瑜伽寺(ゆがじ/笛吹市八代町)の薬師如来に願文を捧げた。この薬師如来は眼病に霊験あらたかといわれていた。信玄は、もし両眼が平癒すれば寺領を寄進します、もし片眼が治れば仏門に入れます。しかし治らぬとあれば、我が右眼を龍宝に与えて欲しいと願文に記している。
信玄は、北条氏政に嫁いだ息女黄梅院が懐妊したとの知らせを受け、安産と母子ともに健やかなることを祈念した願文を、冨士御室浅間神社に捧げている。それも、一度だけではない。現存する願文だけでも、弘治3年、永禄9年の二度に及ぶ。
前者は嫡男を無事に出産したがその後早世している。後者は息女を産んだようで後に千葉邦胤(くにたね)に嫁いだ。永禄8年には松姫の病気平癒を祈願した願文を北口本宮冨士浅間神社に納めている。家族を大切に思う心情を示す史料が残っている武将も珍しい。
監修・文/平山優
(『歴史人』12月号「武田三代」より)