江戸時代に由来する銀座・京橋・築地の地名
今月の歴史人 Part1
地名には歴史と由来がある。現在、当たり前のようにある有名な地名はどのような経緯で、どのように名付けられたのか? ここでは全国的にも著名である東京の地名に迫る。約1400万人が暮らす東京。その巨大都市の各所に付けられた地名の大半が江戸時代に名付けられている。知らずに呼んでいた地名にも、深い歴史があったのだ。今回は銀座・京橋・築地の地名の由来を解説する。
日本一知名度が高い商業地・市場の地名の由来

銀座の由来は銀貨の鋳造所銀貨を鋳造する銀座役所の発祥は慶長17年(1612)。場所は現在の中央区京橋2丁目、ティファニー銀座本店の場所にあった。その後、寛政12年(1800)に蛎殻町に移転し、上絵図はその当時の銀座の場所を指している。(国立国会図書館蔵)

銀貨の製作を描いた『銀座巻物』貨幣を鋳造する場面。幕府は全国に流通する銀の品位を統一して、商取引の円滑化を図る目的で銀座を創設した。銀貨を管理・監督する役人・大黒常是は代々世襲制だった。(『銀座巻物』/国立国会図書館蔵)
日本橋・銀座・築地エリアは武士が住んだ「山の手」に対して、「下町」と呼ばれた地域である。江戸城に住む将軍、将軍を守る幕臣、参勤交代制に基づき江戸で隔年に生活した諸大名の生活を支える町人が主に集住した。現在の行政単位でいうと中央区となる。江戸湾にも面した地域であり、埋め立てにより造成された土地で占められている。
銀座は明治に入ってから行政上の町名にもなった地名である。江戸時代は新両替町という町名だったが、幕府が銀貨を鋳造する銀座を置いたことで、銀座と俗称された。明治2年(1869)に東京府により銀座1~4丁目と改称され、銀座の町名が正式に誕生する。

京橋京橋は昭和34年(1959)に川が埋め立てられると取り壊され、姿を消したが、江戸時代は日本橋を出発して東海道を行くと。最初に渡る橋だった。(国立国会図書館蔵)
京橋の地名の由来は、かつて銀座と京橋を分けていた川に架かる橋とされる。日本橋から東海道で京都に向かう場合、最初に渡る橋であったことから京橋と名付けられたが、架橋されたのは日本橋と同時期とされる。京橋が架橋されたことで川も京橋川と名づけられたが、戦後の復興で埋め立てられてしまい、名前の由来となった京橋も取り壊された。
魚市場のイメージが今も強い築地が生まれたのは明暦3年(1657)の明暦の大火後のことだ。大火のため江戸の町の過半は灰燼に帰したが、焼け残った瓦礫や残土を処理して復興に着手するため、翌4年より、当時は江戸湾に面した木挽町(こびきちょう)の地先が埋め立てられる。沼や海を埋め立てて築いた土地は築地と称されたが、そのまま地名となった事例である。
現在の日本橋本町にあたる鉄炮町の歴史は江戸開府以前にさかのぼる。天正18年(1590)に家康が関東の太守として江戸城に入った際、御用鉄砲鍛治頭を務める胝宗八郎(あかがりそうはちろう)に土地を与え、配下の鉄砲師とともに住まわせたことで、鉄炮町と名付けられた。名づけ親は家康という。

八丁堀奉行所の与力・同心が屋敷を持った町として知られるが、本来は水路沿いに約8丁(約872〜880m)にわたって築いた堀を指す。水路に架かった3つの橋を「三ツ橋」と呼ぶ。(国立国会図書館蔵)
江戸町奉行所の与力・同心の異名でもあった八丁堀の地名は、江戸初期の寛永年間に幕府が掘削した運河の堀の長さが八町だったことに由来する。この地域は慶長年間に埋め立てにより造成されたが、八丁堀が生まれたことでその名が地名となる。

佃島隅田川河口の埋め立てが進められた現在は地続きだが、かつての佃島はその名の通り「島」だった。摂津国西成郡佃村の漁夫30余人がこの島に移住し、郷里の地名を反映させて佃島となった。(国立国会図書館蔵)
佃島は寛永年間に摂津国西成郡佃村の漁民を江戸に呼び寄せことがはじまりである。隅田川河口の干潟を埋め立てて人工の小島とし、佃村の漁民に与えたことで佃島と名づけられた。佃村の漁民たちは隅田川で獲れた白魚を将軍に上納することが幕府から義務付けられたが、白魚漁は江戸の春を告げる風物詩として親しまれた。現在では埋め立てにより佃島は陸続きの土地となり、島ではなくなっている。
監修・文/安藤優一郎

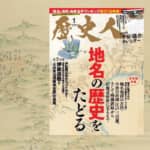



A-10569-1195_E0119071-150x150.jpg)
