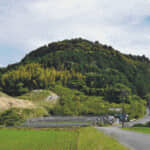武田家臣団の日常生活と衣食
「歴史人」こぼれ話・第6回
武田家臣団の組織と平時の生活
甲府駅前_銅像-300x199.jpg)
甲府駅前にある武田信玄銅像
戦国武将は大名を頂点に、その一族・譜代(ふだい)家臣・国衆などのピラミット型の家臣団で構成されており、家臣は大名から知行地(ちぎょうち)を与えられ奉公(軍役ほか)する主従関係のあるものに限定され、それらの配下の兵士として徴用されていた農民兵は別個に考える必要がある。
家臣についても戦時での大将格(寄親)と部隊長格(寄子)の二重構造になっており、平時でも行政組織上の役職や自家の経営規模の上で大きな差異があったほか、戦時での役割にも大きな違いがあった。
武田氏の家臣団の構成については、信玄晩年期の成立とされる「武田法性院信玄公御代惣人数之事」(『甲陽軍鑑』巻八、「惣人数」と略称)によれば、親類衆18名、譜代家老衆17名、他国衆107名、譜代国衆33名、近習衆102名、その他、信玄子弟付ら24名、一騎合衆(甲斐・信濃・駿河・三河・上野)約40名をあげている。総勢340人の名が書き上げられており、この数値は少ないように思われるが、実態に近いものと判断される。戦時にはこれらの配下の従者・農民兵や、帰属した他国衆らが加わって軍団を編成して対処していた。
武田氏の場合、平時には当主信玄を支える親族と家老衆らが家臣団の最上層部を構成し、さらに譜代国衆で実務を担当する奉行などの重役層と、その配下で実務を分担した諸役人や近習衆などがあり、その総勢は天正10年(1582)3月の武田家滅亡後に徳川家康へ忠誠を誓って提出した起請文(きしょうもん・「天正壬午甲信諸士起請文」)では、ほぼ同じ様な家臣団区分で482人を書き上げている。
先述の「惣人数」と比べて多くなっている点は、例えば大将格である跡部昌忠(あとべまさただ)ほかの重臣衆中として23名の同心衆を書き上げていることによる。
家老ほかの重臣層は所領での館のほかに、城下でも武田館の周辺に屋敷地を与えられ家族とともに常駐していた。日常的に政務に参画するとともに、武道の鍛錬や戦術の諮問にあずかっていた。諸役人や近習衆らも城下に屋敷地を与えられ、各分野での役務を分担していた。
彼等は地方での所有地は少なく、屋敷周りの菜園などを耕作して生活していた。戦時では家子(いえのこ)・郎党(ろうとう)をはじめ同心衆や農民兵を軍団として組織し、戦場に赴いた。武将の子弟は幼少期に寺に通い、手習いや「往来物」の音読や書写によって文字を収得してはいたが、重要文書などは大名右筆(ゆうひつ)に代筆させていた。
信玄-300x221.jpg)
学者久閑(くが)の処に行き、話を筆記する学習熱心な信玄『絵入幼年歴史』/国立国会図書館蔵
中国や日本の古典学習に熱心だった信玄の生活とは
信玄は神仏の信仰に関しては、宗派に偏せず各宗に保護と統制の両面の政策で対処しているが、とりわけ禅宗妙心寺僧(関山派)との交流が顕著であった。諸寺社に対する自筆の祈願文も多く残っており、その多くは戦勝祈願であった。晩年には比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)より僧正位を授与されている(曼殊院文書)。
自らは不動明王(ふどうみょうおう)と毘沙門天(びしゃもんてん)を信仰し、恵林寺(えりんじ・甲州市塩山)に現存する不動明王像は、信玄が在世中に京都の仏師康清(こうせい)に対面して掘らせたものといい、さらに館内に毘沙門堂を設けて日参しており、家法として先祖新羅三郎義光(しんらさぶろうよしみつ)からの伝来である御旗(日の丸)と楯無し鎧(小桜韋鎧兜大袖付、菅田天神社所蔵)を重用していた。とりわけ子女の肉親への情愛は深く、次男竜芳(りゅうほう)の眼病治癒の願文(「歴代古案」)や、長女黄梅院(おうばいいん)の安産祈願の願文が残されている(御室浅間神社文書)。
日常生活での衣食に関しては具体的な史料を残していないが、三菜一汁の簡素なものであったとされている。住居は政庁を兼ねた武田館(躑躅ケ崎館・つづじがさきやかた)のみで、土塁と堀のみの防禦(ぼうぎょ)施設であり、非常時での詰城として館北方2キロの要害山上に積翠寺(せきすいじ)城を構築していた。重臣らも知行地内に城館を構えており、戦時には占領地の城代や城番をも兼務することが多かった。
嗣子(しし)の勝頼(かつより)は、天正9年(1581)になって、織田信長の攻勢に対処するため、新たに七里ケ岩台地上(韮崎市)に本格的な山城として新府城を築いて政庁を甲府から移転させたが、移転直後に織田方に攻められ、自ら城に火をかけて逃亡している。
須玉のろしの里ふれあい公園-225x300.jpg)
甲斐源氏(武田氏)発祥の地とされる若神子(わかみこ)城址に作られた「須玉のろしの里ふれあい公園」(北杜市)