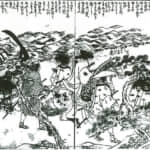22歳の新当主・信玄が発揮した領国拡大の手腕
武田三代栄衰記⑦
諏訪郡を電撃的に併合し、佐久郡を平定した底力

諏訪大社の上社本宮。諏訪上社を総括する神官だった諏訪氏は、宗教的権威を利用し、諏訪地方を版図とする戦国大名へと成長。頼満時代に最盛期を迎えるが孫の頼重時代に信玄に併合される。勝頼の母(諏訪御料人)の実家でもある。
信玄は家督相続後の、天文11年(1542)6月、諏訪郡への侵攻を開始し、上原城主諏訪を滅ぼした。
信玄は、上原城代に重臣板垣信方を配置し国外に領国を広げた。上伊那郡高遠城主高遠頼継(たかとおよりつぐ)、福与(箕輪)城主藤沢頼親(よりちか)らが武田と戦端を開いたが、天文14年までには平定した。
信玄は天文12年から佐久郡への進出を図り、岩村田大井貞隆(さだたか)を降伏させ、望月城主望月昌頼を小諸に追放した。その後、天文15年に、内山城の大井貞清(さだきよ/大井貞隆の子)を降伏させ、同16年には、志賀城主笠原(依田)清繁を攻略したばかりか、後詰めに来た関東管領上杉軍をも撃破した。佐久郡では小諸(こもろ)城主大井氏とその周辺の国衆が、上杉氏の支援を得て頑強に抵抗を続けたが、もはや武田優位の情勢は変わらなかった。
信玄は天文17年2月、埴科(はにしな)郡葛尾(かつらお)城主村上義清と上田原で戦い、初めての敗戦を喫した。佐久や諏訪で反武田の叛乱が起こるが、信玄は7月の塩尻峠合戦で、信濃守護小笠原長時(ながとき)を撃破し、諏訪、佐久を再平定した。
天文19年、信玄は小笠原長時を攻めてこれを筑摩郡から追放すると、余勢を駆って、村上方を攻略すべく、小県(ちいさがた)郡戸石(といし)城を攻めた。しかし、信玄は2度目の敗戦を喫してしまう。
小笠原長時追放に始まる村上義清らとの連戦
敗戦したが大規模な叛乱(はんらん)は起こらず、信玄は天文21年には安曇郡を平定した。天文22年、村上義清の支援を受けなおも抵抗を続ける筑摩郡の旧小笠原方を討ち、義清を攻略すべく信玄は深志(松本)から、北国脇往還(善光寺道)を進んだ。途中、抵抗する刈谷原城などを次々に降伏させた。武田軍の勢いに押され、旧小笠原方の国衆は信玄の軍門に降った。
武田方は、村上方の国衆に調略を仕掛けており、武田軍の圧倒的な勢いの前に彼らは義清を見限り次々に武田方へ帰属した。このため、義清は本拠地葛尾城を包囲される形勢となった。そのため義清は、天文22年4月、葛尾城を捨てて越後に逃亡した。
信玄は、天文23年、木曾郡福島城主木曾義康・義昌父子を降し、さらに下伊那に出兵した。信玄のもとには、伊那郡松尾城(飯田市)主であった小笠原信貴(のぶたか)が亡命していたといわれる。信貴は、鈴岡城主小笠原信定(信濃守護小笠原長時の弟)と吉岡城主(下條村)下条時氏(しもじょうときうじ)らにより追放されていた。信玄は松尾小笠原氏の本領回復の支援を名目に下伊那に出兵し、小笠原信定を追放、下条氏を降伏させ、なおも抵抗を続けた神之峯城主知久(ちく)頼元を、10月には降伏させ、下伊那を完全に平定した。
監修・文/平山優
(『歴史人』12月号「武田三代」より)