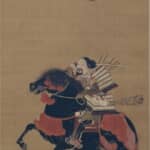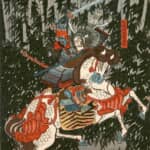独裁者のイメージとは裏腹に、まさに“忖度の人”だった「平清盛」若い頃は母性的な気遣いと優しさに満ちあふれた好青年
忖度と空気で読む日本史
『平家物語』で「悪人」のレッテルを貼られた平清盛。今も独裁者のイメージが付きまとう剛腕政治家であるが、権力を握る前の清盛は、度量が大きく、八方美人ともいえるほど忖度できる人だった。なぜ清盛は変わってしまったのだろうか。
■教訓書に記された“優しい清盛”
多くの人が思い描く平清盛の人物像といえば、ざっと次のようなものだろう。
武士として初めて太政大臣となり武家政権を樹立した人物。
人工島を築いて港を整備し日宋貿易を推進した革新的な政治家。
後白河法皇を幽閉して朝廷の実権を握った独裁者。
おおむね正しいが、もっとも浸透しているイメージは最後の「独裁者」ではないだろうか。確かに、晩年の清盛は平家の権力を盤石にするために手段を選ばなかった観がある。
治承3年のクーデターで後白河法皇を幽閉した後、外孫の安徳天皇を即位させ、退位した高倉上皇の最初の御幸を平家の氏神である厳島神社にしたことは、比叡山をはじめ多くの寺社の反発を招いた。
その後の福原遷都についても、人々の不満を知りながら、心を奮い立たせて内裏の造営に邁進し、高倉上皇が帰京を望んでいることを告げられても「それは結構。だが、この老法師はお供するつもりはない」とはねつけた。
高倉上皇が体調を崩し、清盛は三男の宗盛と口論する事態となり、ようやく還都に同意したが、帰京後は以仁王の乱に加担した興福寺・園城寺を焼き討ちし、貴族の邸宅を没収して軍事拠点にするなどやりたい放題。そして反乱勢力の掃討を進める中、熱病により64歳の生涯を閉じるのである。
こうした晩年の頑なさや強引さは、清盛を「大悪人」呼ばわりした『平家物語』のイメージと合致する。まさに老害という感じである。
ただし、若い頃の清盛はこうではなかった。八方美人と言ってよほど周りに気遣いができる、まさに“忖度の人”だったのである。
鎌倉時代中期の教訓書『十訓抄』に次のような話がある。
――気遣いということに関しては、福原大相国禅門は立派な人であった。ある人が間の悪い苦々しいことをしても、冗談でやったことだと思うようにして、にこやかに笑ってやり、とんでもなくひどいことをしても、役立たずと声を荒げることもない。冬の寒い時には、身辺に仕える幼い従者を、自分の衣の裾の方に寝かせてやり、早朝、彼らが寝坊していたら、そっと床から抜け出して、存分に寝かせてやった。最下層の召使いであっても、その人の縁者の前では一人前の人として扱ったので、その者は大変面目に感じ、心から喜んだという。このような情けのある人だったから、あらゆる人が彼を慕ったのである――
母性的と言ってよいほどの、気遣いと優しさではないか。
■頼れる嫡男の死が清盛を変えた?
この逸話を裏づけるように、壮年期の清盛は度量の大きさと処世術で、人々から厚い信頼を寄せられた。
出世の足がかりとなった平治の乱で、清盛は藤原信頼と源義朝に捕らわれた二条天皇を内裏から救出して六波羅に迎える。公卿・殿上人が続々と六波羅に駆けつける中、関白・藤原基実と父の忠通が入ってくると、よそよそしい空気が流れた。基実は今や朝敵となった信頼の妹婿だったのだ。
そこで、ある公卿が「いかがしますか」と聞いたところ、清盛は「摂関家のことは相談には及びません。おいでがなければお呼びするところですが、ご自分からいらしたのは殊勝なことでございます」といって人々を感心させた。若い基実も、この言葉を聞いてさぞ安堵したことだろう。
平治の乱後、後白河上皇と二条天皇が父子で政治の実権を争うようになると、清盛は二条天皇の御所に宿直所を作って、家中の者を昼夜、護衛にあたらせる一方、蓮華王院(三十三間堂)を造営して上皇に寄進している。
この当時の清盛の様子を、慈円は『愚管抄』で「ヨクヨクツツシミテ、イミジクハカライテ、アナタコナタ(彼方此方)シケル」(よく慎重に考えて巧みにふるまい、双方にお仕えしていた)と記している。
そんな清盛が、なぜ「大悪人」と言われるほどに変わってしまったのだろうか。つまらない結論だが、やはり権力を持ち過ぎたことと、年を取って短気になったというのが原因なのだろう。
加えて晩年、頼みとしていた嫡男・重盛に先立たれたことも大きかったのではないだろうか。治承3年のクーデターも、重盛の死の直後、法皇が管弦の遊びにひたり、あまつさえ重盛の知行国を没収したことが原因の一つであった。「イミジク心ウルハシク」と評された息子の死が精神的な打撃となり、行動に歯止めがきかなくなった可能性もある。豊臣秀吉が弟・秀長の死後、精神的に不安定になってしまったように。
清盛の死後、平家の行く末は三男の宗盛に託された。だが、「父は遺恨があればすぐに報復した。自分はことを荒立てないために知らぬふりをしてしまう」という宗盛に、斜陽の平家のかじ取りができるわけもなく、清盛の死から2年半ののち、西海へと没落していくのである。

平清盛 皇居三の丸尚蔵館/ColBase