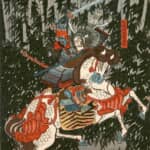嫌われていることを「自覚」していた毛利元就、反毛利の“空気”を敏感に感じて「毛利両川体制」が生まれた
忖度と空気で読む日本史
わずか一代で、国人領主から中国地方一帯を治める戦国大名にのし上がった毛利元就。破格の出世の背景には、元就の卓越した武略・知略に加え、世間の“空気”を敏感に察知し対処する処世術があった。陰謀、怨恨、嫉妬が渦巻く戦国の地域社会において、元就はどのように立ち回り、息子たちに何を残したのだろうか。
■“毛利は嫌われ者である”という自覚
一代で大内氏に従属する国人領主から、東は出雲、西は長門まで支配する大大名にのし上がった毛利元就。その破格の栄達は、豊臣秀吉ら天下人を除けば戦国随一といってよい。元就の死後も勢いは衰えず、孫の輝元の時代には10数か国を支配下におき、四国・九州まで版図を広げた。
躍進の原動力となったのが、元就の次男・吉川元春と三男・小早川隆景が毛利宗家を支える「毛利両川体制」である。
その形が定まるのは、元就が安芸国内で勢力拡大を進めていた天文19年(1550)のこと。元春を大朝荘(広島県北広島町)の吉川氏の養子として送り込み、すでに竹原小早川家を継いでいた隆景に、本家の沼田小早川家(同三原市)も継がせて統合した。
このようにサラっと書くと、「さすが元就、養子政策によって鮮やかに他家を乗っ取ったのだな」と錯覚してしまうが、実際は縁組に反対する家臣をことごとく誅殺、あるいは所領を没収している。戦国の世は甘くない。
ちなみに同じ年、元就は譜代の重臣だった井上元兼とその一族も粛清している。元就の当主擁立にも協力した元兼は、その功に驕り、出仕はしない、段銭は納めない、普請にも応じないとやりたい放題。怒り心頭に発した元就によって、鉄槌が下されたのだ。
このように、元就は時に強引な手を使って国人領主を統制していった。当然、恨みを抱く者も現れる。元就自身、それは自覚しており、隆元に「当家を良かれと思う者は、他国はもちろん、当国にも一人もいないだろう」「家中にも快く思っていない者がいるはずだ」などと述べている。
ひどく悲観的だが、賢明な元就は国内に蔓延する反毛利の“空気”を敏感に感じ取っていたのだろう。この状況に対処するためには、一族が結束してあたるしかないと考えるのは当然の成り行きだった。
■「三矢の訓」の元ネタになった「三子教訓状」
毛利の行く末を案じた元就は、臨終の間際、長男・隆元、次男・元春、三男・隆景を呼び、3本の矢を与えて「矢は1本ずつなら簡単に折れるが、3本束ねればなかなか折れない」と述べて結束を促した、と伝えられている。
有名な「三矢の訓(みつやのおしえ)」であるが、周知のとおり、これはフィクションである。そもそも隆元は元就より先に亡くなるのだから、こういう状況が生まれるはずはないのだ。
ただし元ネタはある。弘治3年(1557)11月、3兄弟宛てに書かれた「三子教訓状」がそれだ。
発端は同年4月、大内氏を滅ぼした元就が、にわかに引退を表明したことにある。これに慌てたのは、形式的ながら、すでに家督を相続していた隆元だった。毛利が衰えることを恐れた隆元は、「自分は才覚がない」といって思いとどまるよう懇願し、自分も引退して5歳の幸鶴丸(輝元)に家督を譲る、自分が死ねば元就も引退できなくなるだろうなどといってダダをこねた。
その後、隆元は元就の再三の説得を受け、当主として責任を全うする覚悟を固める。そして、その条件として、弟の元春・隆景が毛利氏の運営に参画することを要求した。
当時、隆元は弟たちに不信感を抱いていたらしい。隆元いわく、元春・隆景は養家の繁栄を優先し、吉田郡山城に来ても長居せず、自分をないがしろにして2人だけで「ちこちこ」と話し合い、こちらから「なつなつ」と話しかけることもできない。自分を見限っているように見えて腹立たしいと、元就に訴えている。
いささか被害妄想気味な気もするが、元就も「他家をまとめても毛利が無力になったら意味がない」といって同調し、2人に毛利一門としての自覚を持たせることを約束した。
こうしたドタバタを経て、同年11月25日、元就から3兄弟に出されたのが14か条からなる「三子教訓状」であった。その中に「3人の仲に少しでも亀裂が生じれば、3人とも滅亡すると心得よ」という一条がある。まさに「三矢の訓」の言わんとすることと同じであり、創作とはいえ、この逸話が真実の一端を伝えていることは間違いない。
翌日、3兄弟は連署して父の意向に従う請文を提出し、毛利独自の「両川体制」が本格的に始動する。元春・隆景は元就の言いつけをよく守り、宗家の運営に参画。隆元も弟たちに、毛利家臣に直接命令できる権限を与えて、彼らの誠意に応えた。
永禄6年(1563)の隆元の死後も、両川は幼少の輝元を支え、毛利氏の発展に尽くすのである。

毛利元就/国立国会図書館蔵