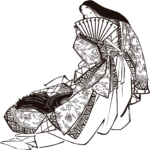安徳天皇を抱いて入水した「二位の尼」の死の情景 「三種の神器」のゆくえは?
日本史あやしい話
壇ノ浦の戦いに敗れた平家一門。名だたる武将たちが次々と入水したことは、よく知られるところである。その最後の場面というべきが、清盛の継室・時子(二位の尼)に抱かれた安徳天皇が、涙ながらに入水してしまったことである。そこでどんな儚くも哀しい出来事が繰り広げられていたのか、あらためて振り返ってみることにしたい。
■安徳天皇を抱いて海の底へ
「尼ぜ、われをばいづちへ具してゆかむとするぞ」
まだ8歳にも満たない幼帝が、祖母を見上げてこう言ったという。幼帝とは、高倉天皇の第一皇子・安徳天皇で、祖母とは、平清盛の継室・時子のことである。壇ノ浦の戦いに敗れた平家一門、その滅亡の時に繰り広げられた悲運の一コマであった。
時は、1185年4月25日のこと。源氏方を率いるのは源頼朝の弟・義経で、平家方を率いるのは清盛の息子・宗盛と知盛である。摂津の渡辺水軍、伊予の河野水軍、紀伊の熊野水軍をも味方に引き入れた源氏方の船数は830艘。これに対して平家側は500艘。船の数だけ見れば源氏側が有利なように見えたが、開戦当初は平家側の方に分があったようである。戦い半ば、不利を悟った義経が、起死回生の策に出た。掟破りともいうべき非戦闘員である船の漕ぎ手めがけて、次々と矢を放ったのだ。その是非はともあれ、戦況が一転。潮の流れが反転したことも、源氏側に勝機が傾いた一因というべきだろうか。
ともあれ、結局は、平家側が敗退。敗北を悟った名だたる武将たちが次々と入水していった。幼帝を乗せた御船においても、儚くも物悲しい出来事が繰り広げられることになる。まず、最高指揮官の一人であったはずの知盛が御船に乗り移り、いきなり掃除をし始めたから、誰もが驚いたに違いない。「見苦しからん物共、みな海へいれさせ給へ」と、船の中を走り回って掃いたり拭いたりしたというのだ。
この様子を目の当たりにした二位殿(二位の尼)こと時子も、これで覚悟が決まった。神璽を脇に抱え、宝剣を腰に差した上で、天皇を抱いて海に身を踊らせようとしたことが『平家物語』に記されている。その時、声を発したのが安徳天皇で、冒頭に記した、儚くも悲痛な叫びであった。
これに答えるかのように、祖母である二位の尼が、「極楽浄土とてめでたき処へ具し参らせさぶらうぞ」と泣きながら答えたという。さらに、「浪の下にも都のさぶらうぞ」と慰めながら、そのまま「千尋の底へぞ入り給ふ」というから、何とも哀れであった。このあたりが『平家物語』最大の見せ場で、祖母が孫を道連れに死出の旅に出ようという場面ゆえに、涙する者も多かったことだろう。
祖母の言いつけに従って手を合わせ、涙ながら念仏を唱える幼帝。祖母はと見れば、すでに腰に三種の神器の一つである宝剣を刺し、神璽(八尺瓊勾玉)も小脇に抱えて待ち構えている。その上で、幼帝を抱きかかえて船から飛び降りたとか。幼帝はもとより、祖母・時子もそのまま海底に沈んだと話を続けるのである。
ただし、この時の情景は、書によって多少異なる。鎌倉幕府の事績を記した歴史書『吾妻鏡』では、先帝を抱き上げたのは時子ではなく、時子に仕えていた按察の局(按察使局伊勢、権大納言・藤原公通の娘)だったとか。安徳天皇も時子もそのまま海底に沈んでしまったが、この女性は助け出されて、筑後川のほとり・鷺野ヶ原に移り住んだとも言い伝えられている。村人たちから慕われ、尼御前とも呼ばれたとも。そこで安徳天皇と平家一門の霊を祀る社を建てて祈祷。それが後に尼御前神社と呼ばれた水天宮(久留米市)の前身だというのも興味深いお話である。
■幼帝の母・建礼門院の心の内
時子と幼帝が海の藻屑と消え去った、その直後の情景にも目を向けておこう。幼帝が祖母・時子に抱きかかえられながら海中へと沈んでいった様子を、すぐ近くから、気が狂わんばかりの思いで見つめていた女性がいた。いうまでもなく、その実母・平徳子(建礼門院)であった。幼帝といえども、平家の血が流れている以上、生き残るすべがなかったのかもしれないが、何と言っても、我が腹を痛めた子である。悲痛な叫び声をあげたことも想像に難くない。『平家物語』の「大原御幸」の章には、海に飛び込む前の時子が、娘・徳子に対して「一門の菩提を弔うために生き延びよ」と命じたことが記されているが、徳子には到底そんな心持ちになれなかったのだろう。その地獄絵を目の当たりにしながら、我ももはやこれまでと前後不覚となって、急ぎ「御焼石・御硯を左右の御懐に入れて」身を投げてしまったのだ。
しかし、自ら死を望んだその願いも虚しく、渡辺党の源五右馬允昵なる武人が、熊手を彼女の御髪にひっかけて引き上げてしまった。こうして、意に反して生きながらえることになってしまったのである。その後、京へ送還されて出家。大原寂光院で、安徳天皇と平家一門の菩提を弔って暮らしたとのお話は、多くの方の知るところだろう。
後に、後白河法皇がお忍びで大原を訪れたことがあったが、その際、落魄した我が身を恥じらいながら、飢えと渇きに苦しみ(餓鬼道)、我が子が海に沈むのを目の当たりにせざるを得なかった苦しみ(地獄道)をも味わうなど、六道をめぐるような人生であったことを述懐している。そんな場面に心打たれ、思わず涙した方も少なくなかったに違いない。
その後白河法皇も、徳子とは、その父・清盛によって幽閉されたこともあったという悪縁の仲。徳子自身も、後白河法皇の後宮に入る可能性があったなど、何かと因縁めいた間柄であった。それらをふまえれば、この法皇の訪問にも、何やら別の意図がありそうに勘ぐってしまうのは、筆者だけではあるまい。
最後に、安徳天皇のことにも目を向けておこう。史実としては、海の藻屑と消えたはずであったが、前述したように、日本各地に生き延びたとの伝承が数多く伝えられている。その死があまりにも儚いがゆえに、何とか生き返らせたいとの人々の願いによるものと考えられそうだが、果たして?
その幼帝に関して、実に興味深い記述があるので紹介しておきたい。それが、作家・宮尾登美子氏が著した『宮本本 平家物語』における設定である。実は、壇ノ浦に沈んだのは安徳天皇ではなく、その異母弟・守貞親王だったというから目を丸くしてしまうのだ。平家にとって安徳天皇は、平清盛の娘・平徳子が生んだ子。何としても、後世に平家の血筋を残したいという時子の願いによって、守貞親王が替え玉として御船に乗り込ませたというのだ。守貞親王は同じ高倉天皇の息子とはいえ、母は藤原殖子(坊門殖子、七条院)で平家一門ではなかったからである。もちろん小説ゆえに、真実かどうか定かではないが、全くあり得ない話ではないだろう。
また、気になる三種の神器にも一言触れておきたい。時子が脇に抱えていた神璽(八尺瓊勾玉)は海上に浮かんで回収されたようであるが、腰に差していたはずの宝剣(天叢雲剣)は、とうとう見つからぬままであった。ただし、この時失ったのは宮中の儀式で用いられた形代で、本物は熱田神宮に保管されていたとみなされることもあるようだ。
また、もう一つの神鏡である内侍所(八咫鏡)は、無事回収されている。これを所持していたのは平重衡の妻で、安徳天皇の乳母でもあった藤原輔子(大納言佐殿)であった。神鏡が納められていた御唐櫃を持って海に入ろうとしたものの、袴の裾を船ばたに射つけられ、足にまとわりついて倒れたところをとり押さえられている。いずれにしても、三種の神器に関しては、何かと明確にはし難いお話も多いが、むしろそれはそれ、謎は謎として、そのまま解明せぬ方が良いと思うのだが、いかがだろうか?

『源平壇浦大合戦之図 』/東京都立中央図書館蔵