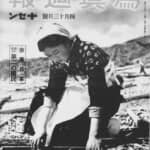欧州で始まった世界大戦は遠く離れた日本の雑誌報道にも影響し、国に大きな影を落とした
国民に大きな影響力を発揮した雑誌『写真週報』から読み解く戦時下【第4回】
ドイツとポーランドの間で勃発した戦争は、フランスとイギリスの参戦を誘い、全欧州を巻き込む戦争の様相を呈してきたが、最初の半年は、奇妙な静けさに包まれていた。だが1940年の5月、遂に西部戦線へ戦火が拡大する。その時、日本ではどんな報道がなされていたのか。激動の1940年を見ていきたい。
1939年9月1日、ドイツ軍がポーランドへ侵攻を開始。それを受けフランスとイギリスは3日、ドイツに宣戦布告した。こうして第2次世界大戦が勃発したのだが、ドイツ軍はフランス領内に攻め込むことはせず、国境地帯のアルザス=ロレーヌでは戦闘らしい戦闘は起こっていない。
このような「奇妙な戦争」と呼ばれる状態が、翌年の5月まで続いた。だが1940年5月10日、ドイツ軍がオランダ、ベルギー、ルクセンブルクに侵攻を開始。フランス軍とイギリス軍もこれに対応すべく、軍の主力をベルギー方面に進撃させた。欧州の西部戦線で本格的な戦闘が始まったことは、『写真週報』の昭和15年5月22日号で扱われている。
.jpg)
【西部戦線(5月22日号)】西部戦線で本格的な戦闘が始まったことを告げる5月22日号の記事。ドイツ軍の空挺部隊の写真が3点のほかは、ベルギーとオランダの迎撃体制を紹介したものであった。
記事の冒頭は「風前の灯火と看なされつつ、その中立に汲々としてゐたオランダとベルギーも遂に戦火の巷となった」と記され、ドイツ空挺部隊のほか、戦闘準備に追われるオランダ、ベルギーの様子が紹介されている。
その後、ドイツ軍は瞬く間にベネルクス三国を蹂躙し、フランス軍の防御が手薄なアルデンヌの森へ装甲部隊を投入。5月15日にドイツ装甲部隊はミューズ川を渡り、20日には早くも英仏海峡に達している。15日にオランダ、28日にはベルギーが降伏し、5月末には英仏軍の多くがイギリス本土に撤退した。そして6月10日に、それまで日和見を決めこんでいたイタリアが英仏に宣戦し、フランス領内に攻め込んだ。
パリは無防備都市宣言をしていたので、ドイツ軍は6月14日に無血入城を果たす。そして22日、コンピエーニュの森でドイツとフランスの間に休戦条約が結ばれた。フランス降伏のニュースは、早くも写真週報昭和15年7月3日号で伝えられている。だが写真の点数は少なく、地図図版メインで紹介。フランスとの戦いを撮影した写真は、次の7月10日号に掲載されている。
.jpg)
【フランス降伏(7月10日号)】フランス敗戦については7月3日号で伝えられているが、西部戦線からの戦闘写真が掲載されたのは7月10日号であった。マジノ要塞への苛烈な攻撃が伝わってくる。
7月10日号の巻頭記事は、満州国皇帝陛下である愛新覚羅溥儀(あいしんかくらふぎ)の来訪を伝えるものであった。溥儀は1934年に満州国皇帝に即位し、その翌年には初の外国公式訪問として日本を訪れている。そしてこの時が2度目の日本公式訪問で、1940年6月に東京で行われた「皇紀二千六百年記念式典」に参列。溥儀にとっては、これが最後の公式外遊となった。中国との戦争が長引いていたこの時の日本にとって、溥儀の存在は欠かせないものであったことが、記事の配置から伺える。
.jpg)
【溥儀来訪(7月10日号)】満州国皇帝溥儀の日本公式訪問を伝える記事。この見開き前には扉写真として、東京駅まで出迎えに赴いた昭和天皇が、笑顔で溥儀と握手を交わす光景が掲載されている。
そして10月9日号が巻頭で扱っているのが、去る9月27日にベルリンのヒトラー総統官邸で調印された、日独伊軍事同盟成立を伝えるものであり、9ページにわたりドイツとイタリアの特集が組まれている。両国の軍事力を分析して世界地図を塗り分け、欺瞞に満ちた世界秩序が罷り通っていることを批判する記事などを組んでいる。
.jpg)
【三国同盟(10月9日号)】10月9日号の巻頭は、三国同盟成立を祝うため外務大臣官舎に集った高官たちの写真が飾った。右からオット独大使、インデリ伊大使、松岡洋右外相、星野直樹企画院総裁、東条英機陸相。ただ右の広告は、平和そのものだ。
その秩序とは、おもに英米仏が中心となって築いた植民地主義で「日独伊三国は弾かれ持たざる国」ということを主張。前大戦で敗れ、どん底まで落とされたドイツの復活を、称賛して止まない論調となっている。同じく、前の戦争では戦勝国側でありながら、国が疲弊してしまったイタリアを復活させた、ムッソリーニの政策を讃えている。
フランスが敗れたことは、アジアの地にも大きな影響を及ぼした。蒋介石(しょうかいせき)への支援物資運搬ルートのうち、フランス領印度支那(現ベトナム)を通るものが最大規模であった。
.jpg)
【仏印進駐(10月23日号)】北部仏印へは平和進駐が画策されていたが、富永恭次少将の独断が影響し、武力進駐が行われてしまう。日本は国際的な信頼を失ったが、記事からは長閑な雰囲気しか伝わらない。
そこでフランスがドイツに屈服したこともあり、日本は昭和15年(1940)9月23日未明、北部仏印に武力進駐を開始する。だが10月23日号に掲載された仏印の光景は、長閑なものであった。この仏印への進駐は、日本が大戦へ足を踏み入れることを決定づけてしまう、まさに後戻りができない作戦となったのだ。
.jpg)
【紀元2600年奉祝楽曲(12月18日号)】12月18日号には、紀元2600年を祝うために各国から寄せられた奉祝楽曲の演奏が行われたという、平和な記事もあった。下の写真はリヒャルト・シュトラウス作曲「紀元二千六百年に寄せる」の演奏風景。