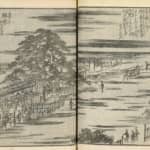太平洋戦争の緒戦において日本軍はなぜビルマを攻略したのか?
最悪の陸戦・インパールの戦い 第1回
後世まで最悪の作戦、地獄の戦場と語り継がれるインパール作戦は、多くの日本軍将兵が無駄死にしたことで知られている。ここでは、作戦に参加したひとりの兵士が残した記録を手がかりに、もう一度、戦いの全貌を振り返ってみたい。

ビルマ中部のエナンジョンで、油田を占拠中の第33師団の兵士。日本が戦争に踏み切った最大の理由は、石油輸入相手のアメリカが、日本向けの石油輸出をストップしたから。そのため油田確保は、至上命令だった。
「牟田口廉也(むたぐちれんや)だけは許せない!」
普段はとても温厚な祖父だったが、話がビルマ(現ミャンマー)戦線やインパール作戦のことに及ぶと、驚くほど語気を強め、こう語ったことを思い出す。
こんな話を聞かせてくれたのは、仕事でつき合いのある山本陽一(仮名)さん。すでに故人となってしまったが、陽一さんの祖父・正一郎(仮名)さんは、戦時中にビルマ方面に出征していたのだという。
正一郎さんは昭和14年(1939)12月1日、補充兵役として編入されるも一旦は除隊。しかし昭和16年(1941)12月3日、近衛輜重兵(しちょうへい)連隊補充隊に再び応召された。同日付で独立自動車第101大隊第3中隊に編入される。
間もなく日本はアメリカ、イギリスと戦闘状態に入った(オランダに対する宣戦布告は少し後であった)。正一郎さんは12月23日、広島の宇品港を出港。同日、部隊は第15軍隷下(れいか)となった。そして昭和17年(1942)1月13日にバンコクの港に入港する。
正一郎さんが乗った船がバンコクに到着する前、飯田祥二郎(いいだしょうじろう)中将に率いられた第15軍主力(基幹は第33師団と第55師団)は、開戦後すぐにタイ王国に平和進駐していた。
この地域での日本軍は、まさに破竹の勢いだった。山下奉文(やましたともゆき)中将が率いる第25軍(基幹は近衛・第5・第18師団)が、アジアにおけるイギリスの牙城であるシンガポールを目指し、マレー半島を南下。各地で戦闘を重ねつつ1000kmの道のりを踏破し、昭和17年1月31日にはマレー半島最南端のジョホール水道に到達する。そして2月15日には、シンガポールも攻略し、マレー半島を支配下に置いた。
一方、当初の大本営の作戦構想では、ビルマへの侵攻は大きなウエイトを占めていなかった。ビルマ作戦は第15軍が担当することになっていたので、昭和16年12月14日に隷下の第55師団がビルマ最南端のヴィクトリアポイント(現コートーン)を攻略。そして1月20日になると、第15軍主力がタイ・ビルマの国共を越える。1月末には第三の都市モールメン(現モーラミャイン)を占領。2月初旬には第33師団がパアーンを陥落した。
こうして1月上旬に策定した計画通り、第15軍は順調に南部ビルマへ進撃。その先、首都ラングーンへ進むには、兵力や補給の問題があるので、さすがに時間がかかると思われた。ところがマレー方面の戦況が順調に推移したため、戦力に余裕が生まれた。それにより、上部組織である南方軍の姿勢が積極的なものに変化したのである。
タイとビルマの国境付近には、標高2000m級の山脈が約100kmにわたり行く手を遮っている。まともな道もない山岳地帯を、日本の設営隊は自動車が通れる道を建設しながら、約1カ月かけて進んだ。正一郎さんはトラックの運転と整備が主な任務であったので、細心の注意を払いつつ、出来たばかりの道にトラックを走らせて北上したと思われる。
日本軍を迎え撃つビルマのイギリス軍は約3万。そこへ新たに第17師団を編成し、シッタン川の防衛に当たらせていた。加えて約10万の中国軍が援軍として布陣。日本軍は最初に第17師団と遭遇するが、英軍は橋を破壊して後退してしまう。川を渡ると英戦車部隊との交戦に突入。日本軍の戦車や山砲は英軍戦車には歯が立たないため、夜襲と肉弾戦法でこれを退けてしまう。
そして3月8日にはラングーン市を陥落させてしまい、飯田司令官が入城する。英国のビルマ総督レジナルド・ドーマン=スミスが、すぐに中部の避暑地であるメイミョー(現ピンウールイン)に逃れてしまったのも、ラングーンが簡単に陥落した要因となった。
一方、日本軍側はマレー作戦が早々に終了したため、シンガポールから第18師団と第56師団が第15軍の戦闘序列に加わった。第18師団は、もともとは中国戦線に派遣されていた精鋭だが、昭和16年11月に第25軍に編入され、マレー作戦に従事していたのである。この師団の師団長は、後にインパール作戦を強行する牟田口廉也中将であった。
こうして勢力を増した日本軍は、4月17日に中部油田地帯のエナンジョンを占領。5月1日にはマンダレーも陥落させる。そして中国国境に近いミートキーナ(現ミッチーナ)やバーモといった辺境の拠点も抑えたため、ビルマにあった中国の蒋介石に対する補給路「援蒋ルート」の遮断に成功。日本軍は当初の予定を遥かに上回る、華々しい戦果を挙げたのであった。

1940年代のビルマ、ラングーン市街地のメインストリート。当初、日本の大本営は補給の制約から、ラングーン攻略には時間がかかると踏んでいた。日本版電撃戦を展開したマレー作戦の成功により、陥落が早まった。