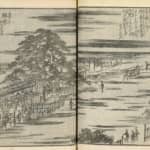伊勢長島の一向一揆撃退に艦砲射撃を導入。 志摩一国を領し、海賊大名と称された九鬼嘉隆
海賊衆を水軍組織に昇華させた男 海の戦国大名「九鬼嘉隆」第4回
軍船を浮いた砦に転用するという、誰も思いつかない戦術で伊勢長島の一向一揆勢を駆逐した九鬼嘉隆。名実ともに織田家随一の水軍の将となったが、その前に強敵・村上海賊衆が立ちはだかる。

鳥羽市歴史文化ガイドセンター内にある資料館に展示されている、九鬼嘉隆の鉄甲船の模型。奈良興福寺の多聞院英俊が書き残した資料を元に再現。鉄を貼った船体が黒く見えたことから、黒船とも呼ばれた。
志摩一国の平定に成功した九鬼嘉隆は、織田信長から旧領を安堵されたうえ、正式に織田家の侍大将に列せられた。その翌年の永禄13年(1570)は、4月23日に改元され元亀元年となった。これは改元に反対であった信長が、越前の朝倉義景討伐に出陣している隙に、将軍・足利義昭が勝手に行ったのである。
この元亀というのは、信長にとって最悪の時期であった。諸国で信長と敵対する勢力が跋扈(ばっこ)し、文字通り休む間もなく各地を転戦している。この頃、信長の運も尽きたのではないか、という噂が味方の陣中にも広がっていった。九鬼の家中も例外ではなく、「織田家に将来はないのでは?」という声も挙がっていた。だが嘉隆は「自分が運命を供にするのは信長しかいない」と定めていた。
元亀元年9月になると、とうとう石山本願寺も信長に敵対。同年6月に姉川で信長と徳川家康の連合軍に破れた浅井長政・朝倉義景の軍が、本願寺軍と示し合わせて籠もっていた比叡山から出撃。近江の織田領に侵入して、比叡山麓の坂本城を攻め落とし、弟の織田信治と森可成(もりよしなり)を討死せしめている。
そして11月になると、信長の許にさらに悪い知らせが届けられた。伊勢長島の一向(いっこう)宗徒が、石山本願寺に誘われ兵を挙げたのだ。木曽川、揖斐(いび)川、長良川の河口に飛び石のように点在する中洲に砦を設けた門徒衆に対し、織田軍は効果的な攻撃を繰り出せず、2度の総攻撃にも失敗する。
そして長島攻略の決め手がないまま天正2年(1574)を迎えた。この年の正月、嘉隆は信長が再度長島を総攻撃することを聞きつけた。川では軍船は役立たないと判断され、過去の戦いに九鬼の水軍衆は投入されていない。だが今度の戦いには、全船団を引き連れて参戦することを滝川一益(かずます)に直訴した。
そして織田軍の総攻撃が開始されると、嘉隆率いる水軍は、小早船はもちろんのこと安宅船、関船といった大型船まで川筋を漕ぎ上った。しかも浅瀬で座礁すると、船を浮き城代わりにして、砦内に鉄砲や弓矢を浴びせかけたのである。これを見た織田軍の陸兵たちも戦意が上がり、それぞれ川船に分乗して砦に攻め寄せた結果、長島城は陥落する。降伏を申し出た門徒衆を信長は許さず、男女の別なく2万人余が、ことごとく処刑された。
嘉隆が行った座礁した船を砦とした苦肉の策と、それを逆手にした“艦砲射撃”を信長は大いに評価。戦後、嘉隆は信長から志摩一国を与えられた。これにより嘉隆は、小さいながらも国持ち大名となる。同時に織田水軍の総大将となり、海賊大名と呼ばれた。

嘉隆が完成した6艘の鉄甲船を集結させた鳥羽の港。当時の海岸線はもっと陸地側に入り込んでいたようだ。さらに沖合には多くの島が浮かんでいるため、波や海流の影響を受けにくい天然の良港だということがわかる。
信長は翌天正3年(1575)10月、越前の一向一揆も平定した。残るは総本山の石山本願寺だけとなり、信長の勢いに圧倒された本願寺は、織田方へ和睦を申し入れた。おかげで天正4年(1676)の正月は、織田家中にとって久しぶりの安息の時となった。
だがこの年の2月、前将軍の足利義昭が安芸の大大名・毛利輝元(てるもと)の許を訪ねて、室町将軍家の再興を依頼。毛利家はこの願いを受け入れ、信長と断交する。さらに義昭は上杉謙信と石山本願寺を提携させたうえ、武田勝頼も説得し謙信と和解させた。こうして新たな信長包囲網が形成されたのである。そして4月には、再び本願寺が信長に牙をむく。
対して信長は、本願寺の周囲に砦を築き、陸路からの兵糧弾薬の搬入を完全に遮断。そのため本願寺に兵糧弾薬を運び入れるには、木津川河口を船で遡上するしかなくなった。
この頃、嘉隆が領する志摩の隣国、伊勢では旧領主の北畠具教(きたばたけとものり)とその一族が、信長に反旗を翻す。そのため、九鬼水軍は石山本願寺攻めに参加できずにいた。その間の天正4年7月、本願寺の要請を受けた毛利輝元は、村上海賊衆を中心とした800艘を超える大船団に出撃を命じた。船団の内訳は兵船が300艘、武器や兵糧を積んだ荷船が500艘である。
途中の和泉国貝塚で紀州の鉄砲集団・雑賀衆と合流し、木津川沖へと漕ぎ進んだ。織田軍は間鍋七五三(しめの)兵衛、沼野伝内(でんない)、宮崎鎌大夫(かまたいふ)といった和泉や河内の海賊衆が、5艘の大型安宅船を中心に約300艘の小型船がそれを取り囲む陣形で、木津川河口を封鎖していた。
だが村上海賊衆は火薬がぎっしり詰められた火矢や、素焼きの容器に火薬を詰め火縄に点火して敵船に投げ入れる焙烙(ほうらく)という独自の武器を駆使し、織田方の船の大半を焼き沈めてしまう。結果は織田方の惨敗で、本願寺には毛利からの物資が悠々と運び入れられた。
この敗戦を受け、信長は嘉隆に必ず勝てる作戦を求めた。そこで嘉隆が考案したのが、薄く伸ばした鉄板を船体に貼り付け、敵の火攻めを防ぐ甲鉄船の投入であった。この提案に、新しいものに目がない信長はすぐに飛びついた。そして費用を惜しまず建造を命じる。
翌天正5年(1577)、嘉隆は雑賀攻めに参加したほか、多くの時間を鉄船造りの監督に当てた。幸いこの間は、羽柴秀吉の軍が中国攻めを開始したこともあり、海上での大きな戦闘は起こっていない。そして天正6年(1578)6月、艤装(ぎそう)を終えた6艘の鉄船が、志摩の鳥羽港に回航されたのであった。

鳥羽市内に建つ常安寺は九鬼家の菩提寺となっていた。本堂裏には九鬼家歴代の墓碑が並ぶ廟所がある。綾部城主となっていた九鬼隆季が、延宝年間(1673〜80)に現在の形に整備。中央の五輪塔が嘉隆のもの。