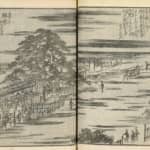英傑 “織田信長” に臣従後、伊勢攻略で海賊衆を率い大活躍!
海賊衆を水軍組織に昇華させた男 海の戦国大名「九鬼嘉隆」第2回
伊勢志摩地方の一国衆でしかなかった九鬼氏だが、やがて時代の寵児であった織田信長に服属することが決まる。そのことによって、戦国武将として徐々に頭角をあらわしていく。

九鬼氏発祥の地と言われる九鬼湾。入江が深く入り込んでいるため、嵐に見舞われても船が沈む心配が少ない。そのうえ外海からは入江の奥を見ることができないので、格好の船隠しとなってくれる。
志摩の十二国衆に攻められ、九鬼嘉隆(くきよしたか)が名切の領地を後にして朝熊山の金剛證寺に登ったのは、永禄8年(1565)のことだ。この年、嘉隆は数えで24歳。今川義元を破り一躍時の人となっていた織田信長は嘉隆よりも8歳年長であり、隣国美濃の攻略に力を注いでいた。
京都では将軍足利義輝が、松永久秀と三好三人衆に襲撃され二条御所で命を落としている。戦国最強と評されていた甲斐の武田信玄は、越後の上杉謙信と長年にわたり抗争を続け、いまだに決着をつけられずにいた。永禄8年というのは、そんな年であった。
まさしく裸一貫となった嘉隆が幸運だったのは、九鬼家の家臣の中に織田家の重臣となっていた、滝川一益(かずます)の縁者がいたことだ。一益は甲賀の出身と言われているが、祖先については不明な点が多い。そのような人物を重用するあたり、家臣の出自にこだわらない信長らしさの表れといえよう。九鬼家も出自ははっきりしていない。信長が家柄などにこだわる人物であったなら、嘉隆が仕えることなど到底かなわなかったと考えられる。
さらに嘉隆が一益の元を訪れたのが、最良の時期だったという点も大きい。嘉隆が一益の元へ向かおうと朝熊山を下ったのは、永禄9年(1866)3月のことであった。この頃、長年に渡った美濃攻めが大詰めを迎え、信長の目はすでに伊勢や近江へ向いていた。海に面した伊勢を攻めるには、船いくさに長けた海賊衆の力が不可欠だ。しかし当時の織田家には、まともな海賊衆は随身していなかった。
さらに南伊勢を治めていた公家大名の北畠(きたばたけ)氏は、志摩の国衆を扇動し九鬼を追い出した張本人である。いわば嘉隆にとっては、不倶戴天(ふぐたいてん)の仇なのである。海賊の出であり、しかも伊勢や志摩の現状を熟知する嘉隆は、たとえ現状は裸一貫でも信長にとって十分利用価値のある男であったのだ。そのような事情もあり、嘉隆はすぐさま信長に臣従することが決まり、滝川一益の与騎となった。

JR紀勢本線の九鬼駅。入江の一番奥に位置しているので、北東側にある古くからの集落からは離れている。海で暮らす者と陸で暮らす者の感覚の違いが感じられる。
永禄10年(1567)に美濃攻略を成した信長は、休む間もなく北伊勢攻略を一益に命じている。伊勢南部五郡は国司北畠氏の支配下にあったが、北八郡は小豪族が割拠し、日々争いが絶えなかった。その中で神戸、長野両家の力が抜きん出てはいたが、大名として君臨するほどではなかった。そこで一益は両家に調略の手を伸ばしたのである。最終的に神戸家には信長の三男・三七丸(後の織田信孝)、長野家には舎弟の織田三十郎信包(のぶかね)を養子とし、北伊勢を手中に収めた。
さらに永禄12年(1569)になると、南伊勢の北畠氏攻略の軍を発した。この家は南北朝以来の名家であり、新興勢力である織田家の誘いなど歯牙にもかけなかった。しかも1万を越える兵は強く、それを率いる北畠具教(とものり)自身、剣豪の塚原卜伝(ぼくでん)から一ノ太刀の奥義を授けられた剛の者であった。さすがの織田軍も、長期戦を覚悟しなければならない。
そこで伊勢の軍略を任されていた滝川一益は、具教の実弟である木造具政(こづくりともまさ)を調略し、味方に引き入れた。そのうえで信長が自ら4万の大軍を率い、具教の籠る大河内城を包囲。
この戦いにおいて嘉隆は、北畠氏の支城であり伊勢湾からの補給の要となっていた大淀城を攻略。この時、嘉隆は四散していた九鬼海賊衆を結集し、沖に新たに編成した軍船を並べて海上封鎖を行った。そして大鉄砲を駆使して落城させたのである。さらに北畠氏の残党ともいえる三鬼城や長島城攻めにおいては、海上から十艘の軍船で攻め、これらの城を陥落させている。この戦果は、信長に船いくさの重要性を強く認識させた。
こうして大河内城は完全に孤立。それでもなかなか落ちないことに業を煮やした信長は、一益の策に従い次男の茶筅丸(ちゃせんまる/後の織田信雄)を養子に入れ、南伊勢を平定した。
この戦いで嘉隆は、信長から一番の働きと認められたうえに、志摩国の平定を命ぜられている。ほんの数年前、他の国衆たちに攻められ後にした故国を、自らの手で平らげるのである。その命を受けた嘉隆は、感極まり、全身に震えを覚えたに違いなかった。

九鬼嘉隆が生まれ育った大王崎。ここにあった名切城を根城としていた。目の前に広がる海は、熊野灘と遠州灘の分海点。沖は黒潮が流れ、陸地近くには暗礁が多い難所である。