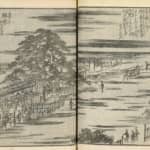水軍の重要性を見抜いた織田信長に志摩平定を命じられた“ 九鬼嘉隆 ”
海賊衆を水軍組織に昇華させた男 海の戦国大名「九鬼嘉隆」第3回
裸一貫という境遇でありながら、昇り竜のような織田信長に臣従した九鬼嘉隆。水軍を扱うその手腕は、早くも信賞必罰を旨とする信長に認められ、志摩一国の平定を命ぜられる。

伊勢湾から大王崎にかけての沿岸部は、波が穏やかな日ならばシーカヤックによる快適な海上散歩が楽しめる。だが大王崎の沖合には黒潮が流れ、熊野灘と遠州灘の分海点となっている。流される心配がある海域なのだ。撮影/野田伊豆守
滝川一益(たきがわかずます)の寄騎となった九鬼嘉隆は、織田信長による永禄12年(1569)の伊勢攻略において、海上からの城攻めを成功させるという大きな軍功を挙げた。これにより嘉隆は、信長から志摩一国の平定を命ぜられたのである。
そこで嘉隆は、志摩の地頭連合の盟主的存在であった鳥羽監物・鳥羽主水父子を切り崩す策に出た。まず使者を送り自らに従うように申し出る。当然、鳥羽父子はこれを拒絶。これを受け、嘉隆は全船団を率いて鳥羽家の本拠である泊浦(鳥羽)の砦に向かった。
この時の九鬼(織田)水軍(信長は海賊という名称を嫌ったと言われている)の兵力は安宅船(あたけぶね)1艘、関船2艘、それに小早(こばや)船14艘の計17艘で、将兵は二百余人であった。鳥羽方の兵数は70名にも満たなかったので、これだけで十分だ。加えて大淀城攻めの際に威力を発揮した、大鉄砲を30挺ほど携えている。
これで海上から砦を囲み、一斉に鉄砲を撃ち込んだ。その凄まじい威力に、すっかり戦意を挫かれた鳥羽方は嘉隆が示した和議に応じて城を明け渡した。さらに監物の末娘を嘉隆の正室として差し出している。こうして志摩国で最も影響力を持つ鳥羽家と血縁関係を結ぶことに成功した嘉隆は、残りの地頭たちには速やかに鳥羽砦に伺候し、恭順の意を示すことを促す書状を送りつけている。
だが、期限までに鳥羽砦にやって来た地頭は2人だけで、浦砦の和田大学助などは九鬼の使者の首を刎ね、公然と反旗を翻した。嘉隆はすぐさま出陣し、たちまち和田大学助とその一族郎等を全滅させてしまった。
この苛烈な処遇に、残りの地頭たちはかえって臣従するのを躊躇ってしまう。そこで嘉隆は自分と鳥羽の娘の婚儀に、地頭だけでなく地侍まで招待し、去就をはっきりさせようと試みた。それでも顔を出さない地頭は、明らかな敵として掃討しようと考えたのだ。
この時に嘉隆の頭にあったのは、国司の北畠家の海賊大将を務め、自分を志摩から追い出した張本人の小浜民部景隆を、次の標的とすることだった。小浜民部を討てば、他の地頭は必ず降ってくる。そう判断したのである。
だが小浜民部は九鬼に従うのを潔しとせず、一族郎等すべてが船に乗り込み、志摩国からの脱出を試みた。この時、志摩の海賊衆では小浜家に次いで大きな勢力を誇っていた向井正重も、小浜民部と行動を共にしている。
小浜・向井の連合船団が伊勢湾を抜け、南へと向かう際、九鬼側の船団もこれを追撃したため、志摩の海賊衆同士の海戦が勃発。この時、志摩の他の地頭たちは進んで九鬼方に味方し、脱出を試みる小浜・向井の船団に攻撃を仕掛けている。結局、小浜景隆も向井正重も討ち取ることはできなかったが、嘉隆はこれで志摩一国の平定に成功したのである。
この時の嘉隆は知る由もなかったが、小浜景隆と向井正重は志摩を後にすると、南から東へと進路を変えている。同じ頃、今川領を攻め取り悲願であった海への進出を果たした甲斐の武田信玄が、大急ぎで水軍の編成に着手していた。多くは旧今川海賊衆をそのまま組み入れたのだが、それだけでは足りず北条方の海賊衆にも誘いの手を伸ばしている。

答志島から一望した鳥羽湾。入江に加え答志島、菅島、坂手島をはじめとする大小の島々に守られているため、海面はとても穏やか。鳥羽は船を隠しておくこともできる、海賊衆にとって条件の揃った場所であった。撮影/野田伊豆守
そんな時、九鬼嘉隆によって伊勢・志摩を追われた小浜景隆、向井正重は、信玄にとってどうしても欲しい戦力だった。西上を念頭に置き始めていたこの頃の信玄にとって、海上警固と兵糧の輸送のため、自前の海賊衆は欠かすことのできないものであった。しかも彼らは、西への海路を熟知している。
このふたりは、武田家が滅びた後には徳川家の海賊衆となっている。そして後年、再び嘉隆と対決することになるのだが、それはまた後の話としよう。
現代人、それも船とは無縁の人にとって海の地理感はピンとこないであろう。小浜・向井両氏が志摩を後にして東へ向かったのは、そこは古来より海の道となっていたからだ。
伊豆の下田を朝山まけば
晩にゃ志州の鳥羽の浦
伊豆の下田には、このような里謡が残されている。風をうまく捉えれば、伊豆から志摩は1日の距離ということだ。逆に志摩から伊豆に向かう際は、黒瀬川と呼ばれる沖合を流れる黒潮に乗れば造作もない。
かつてこの鳥羽の港から南下し、大王崎方面を目指してシーカヤックを漕ぎ進めた経験があるが、実際に海に出てみるとそれが実感できる。波が穏やかな日でも、油断していると思いもよらない流れにつかまり、知らぬ間に沖へ流されてしまうのだ。
だがそれを知っていた伊勢・志摩の海賊衆にとって遠江や駿河、そして伊豆といった国は、文字通り指呼の間なの
である。まさに海はひとつにつながっている。ここはそれを思い知らされる海域なのである。

正面に見える島は神島。その左手の奥にあるのは三河の渥美半島・伊良湖岬だ。これだけ近くに見えるので、鳥羽と伊良湖の間は陸路よりも海路のほうが遥かに早い。現在でもフェリーが運航しているのがその証し。撮影/野田伊豆守