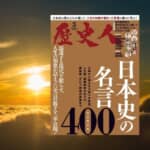強く美しく生きた北条政子・篤姫・清少納言の言葉
今月の歴史人 Part4
激動の時代を強く美しく生きた女性たちの言葉は、現代をしなやかに生きる指針ともなる。現代に名を残す女性の偉人たちの、名言に迫る。
今もなお生き続ける先駆的な女性たちの言葉
北条政子
「源氏三代の恩は 山岳よりも高く 大海よりも深い」

北条政子 国立国会図書館蔵
鎌倉幕府初代将軍・源頼朝の正室。伊豆の地へ流されていた頼朝と地元の武家の娘の政子は恋に落ち、その縁で北条氏は頼朝の味方になった。頼朝の死後にはふたりの子の源頼家・源実朝が将軍になったが、暗殺されてしまう。のちに4代目将軍として藤原頼経が迎えられると政子はその後見人となった。
しかし時の後鳥羽上皇と幕府の関係が悪化した承久3年(1221)の承久の乱勃発寸前に、御家人たちに宣言したのがこの言葉。政子は上皇側につきたければそれでもいいとした上で、代々の将軍たちからの恩を忘れるなと釘を刺したのだ。この演説がきっかけになって御家人たちは結束、上皇方の軍勢を蹴散らした。
清少納言
「ありがたきもの。舅に褒められる婿。また、姑に思はるる嫁の君」

清少納言 東京国立博物館蔵/ 出典:Colbase
「清少納言」は女房としての通称で、本名は不明。
優れた歌人の家系に生まれ、本人も芸術・文学の才を豊かに育てた。橘則光と結婚した後に離別、正暦4年(993)に一条天皇の中宮(皇后)・定子(藤原道隆の娘) の女房となる。長保2年(1000)に定子が亡くなった後、清少納言がどうなったかはさまざまな伝説がありよくわからない。
しかし、彼女が 残した随筆『枕草子』はありし日の定子の輝き、清少納言の才智を今に残している。紹介したのは枕草子の「ありがたきもの(滅多にないもの)」 の一節。現代語訳としては、「姑に褒められる婿も、姑に好まれる嫁も、滅多にいない」の意。今も昔も変わらない話なのだなと思わされるとともに、清少納言の鋭い視点とシニカルな価値観を感じさせてくれる。
天璋院(篤姫)
「我れ入輿の折りは、この城にて死ぬまでの生涯を送る覚悟なり」
天璋院(篤姫)は時の薩摩藩主で従兄にあたる島津斉彬の養女になった後、 近衛家の養女として江戸幕府13代将軍・徳川家定の3人目の正室になった。 しかし結婚後2年に満たずして家定が亡くなり、落飾した彼女は大奥に残った。やがて14代将軍・徳川家茂の正室として和宮が江戸城へ入ってくると、しきたりの違いもあって対立しつつ、やがて和解して徳川家のために協力す るようになったとされる。
この言葉は慶応4年(1868)に官軍への江戸城明け渡しが決まった際、それを拒否してのもの。あくまで政略結婚であり、 夫は既にないが、それでも嫁いで来て徳川の人間になったからにはその一員としての誇りと結びつきを忘れない、という強い意志が感じられる。
監修・文/榎本秋