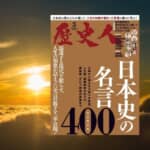人生訓、組織経営のあり方を語った徳川家康、毛利元就らの言葉─歴史家・小和田哲男氏が愛した名言─
今月の歴史人 Part1
長年にわたって歴史の研究を続ける歴史家は、偉人のどのような言葉に影響を受けてきたのだろうか? 歴史家として、戦国時代研究の第一人者として知られる小和田哲男氏に好きな「英傑たちの言葉」を選んでもらった。
歴史の魅力をわかりやすく伝える戦国時代研究の第一人者
【小和田哲男氏が選ぶ英傑たちの言葉】
徳川家康
「人には其長所のあれば、 己が心を捨て、 たゞ人の長所をとれ」
『徳川実紀』「東照宮御実紀」附録十八
[現代語訳]人にはそれぞれ長所がある。個人的な見方を捨てて、ただその人の長所を見極めることが重要だ。

徳川家康75歳でこの世を去るまでの間に、家康は数々の名言を残している。『徳川実紀』以外には『名将言行録』や大道寺友山による『落穂集』などにその言葉が残されている。

徳川家康の言葉が記された『徳川実紀』上の一文(傍線部)の前には「ややもすれば己が好みにひかれ、 わがよしと思ふ方をよしと見るものなり」とある。家康はあくまでも個人の主観を排することの大切さを説いた。(国立国会図書館蔵)
徳川幕府の公式記録『徳川実紀』(正式には『御実紀』)に残された徳川家康の言葉を、第1に挙げたい。『御実紀』には創業者・家康の人材観を示す言葉がいくつも記されているが、これもそのひとつである。この一節から、自分の好みで家臣を採用するのではなく、その者の得意分野は何かを見極めることが必要と家康が説いたことがわかる。
家康の人材観の一例としては、こんな逸話も『御実紀』に見える。家臣の小幡昌忠(おばたまさただ)が謀反人を処罰する際、 抵抗されて左手首を失った。「この腕では働けない」と辞去を願う昌忠に対し、家康は「左手はなくとも右手で太刀を持てば戦えよう」といい、 留まらせたという。その後も昌忠は懸命に槍働きを続けた。
『御実紀』は幕府の儒家・林述斎(はやしじゅっさい)の建議で編纂が開始され、成島司直(なるしまもとなお)らが実務にあたった。それから実に35年後の天保14年(1843)に完成。初代の家康から10代・家治(いえはる)までの歴代将軍の治績が記されている。全516冊のうち家康の治績は「東照宮御実紀」10巻と附録(逸話集)が25巻。「附録」は2代・徳川秀忠以下の将軍が多くは2〜3巻でまとめられているのに対し、家康は飛び抜けて多い。当然ながら、家康が神格化された影響もあるが、創業者の「君主論」は、それだけ重んじられるべきものと考えられたのだろう。
鍋島直茂
「人は下程骨折候事、能く知るべし」
『直茂様御教訓ケ条覚書』
[現代語訳]立場が下の者ほど、骨の折れる仕事が多いということは(上に立つ者であれば) 常に頭に置いておかなくてはならない。
第2の言葉として「直茂様御教訓ケ条覚書(なおしげさまごきょうくんかじょうおぼえがき)」の一条を挙げたい。肥前の戦国大名・龍造寺隆信(りゅうぞうじたかのぶ)に仕えた鍋島直茂は、のちに龍造寺家の実権を握り、江戸時代には鍋島家による佐賀藩の祖となった。豪族から大名にまで出世した直茂は、下の者にどういう思いで接していくべきかを説いた家訓を残した。立場が下の者の苦労を、自分の子孫が忘れることのないようにと残したのであろう。藩祖・直茂の名を冠した「家訓」にある一 条は、すべての組織が手本とすべき言葉であると思える。
毛利元就
三人の半ば、少しにても、懸子へだても候はゞ、 ただただ三人御滅亡と おぼしめさるべく候々
『毛利元就自筆書状』(『毛利家文書』)
[現代語訳]三人の間に、少しでも壁や隔たりが あったならば、三人とも滅亡するも のと思いなさい。

毛利元就 宿敵・尼子氏との死闘を制す ることにより、安芸の小豪族から中国の覇者へ昇りつめた。 「謀多きは勝ち、少なきは負ける」という言葉も残しており、 夜襲や伏兵戦術など知略を駆使した作戦を用いた。(国立国会図書館蔵)
最後は毛利元就の遺訓として名高い、いわゆる「三矢の訓」のもとに なった言葉である。これは元就が長男・毛利隆元(たかもと)、次男・吉川元春(きっかわもとはる)、三男・小早川隆景(こばやかわたかかげ)に宛てた弘治3年(1557)11月25日付の自筆書状に記したもの。 戦乱の世には親子や兄弟の争いが絶えなかったため、元就は毛利家がそうならないようにと心配して、次世代に向けての教訓となる言葉をこのように残したのであろう。兄弟3人の結束を説いたこの言葉は、中国地方を制した名君らしい、味わい深い言葉である。
監修/小和田哲男、文/上永哲矢