描かれた豊臣大坂城と、復興された大阪城天守閣
天守閣学芸員が語る 知られざる大阪城の歴史 第2回
追求される豊臣大坂城の姿
豊臣秀吉が築いた大坂城天守の姿は、現在にいたるまで人々の関心の的になり、資料を踏まえたさまざまな復元案が提示されてきた。昭和6年(1931)に復興された大阪城天守閣の外観や構造についてインターネット上でいろいろと指摘されるのも、在りし日の大坂城に対する関心の高さゆえだろう。
近年よく耳にするのは、「豊臣系」城郭では黒色、「徳川系」城郭では白色の外観が採用されるとの説に基づき、四層目まで白壁の大阪城天守閣は考証ミスではないかという意見だ。最上層のみ黒塗りであることから、「豊臣・徳川の折衷デザイン」と解釈されることもある。
それでは、歴史資料は大坂城の姿をどのように伝えているだろうか。
それぞれに異なる屏風での描かれ方
現在、豊臣時代の大坂城を描いたとされる屏風は5点存在する。最も古くから知られてきた「重要文化財 大坂夏の陣図屏風」(大阪城天守閣蔵)に見える天守は、外壁に黒い腰板をつけ、屋根瓦は青みを帯び、金の装飾と引き立て合って暗色の印象を強く与える。

「重要文化財 大坂夏の陣図屏風」 (大阪城天守閣蔵)の大坂城天守部分
いっぽう、成立が最も古いとされる「大坂城図屏風」(大阪城天守閣蔵)では、やはり各層の外壁に黒い腰板をつけるが、その表面に金色の菊文や桐文、巴文(ともえもん)、唐草文様など大ぶりの装飾を施す点がずいぶん異なっている。
「大坂冬の陣図屏風」(東京国立博物館蔵)は、外壁の柱を見せてその間を薄黒く塗り、「京・大坂図屏風」(大阪歴史博物館蔵)は柱や長押をあざやかな赤色に塗る。そして2000年代になって大きな注目を集めた「豊臣期大坂図屏風」(オーストリア、グラーツ市のエッゲンベルグ城博物館蔵)では、最上層の外壁のみ黒塗り、その他の層は白壁という、奇しくも現在の大阪城天守閣を彷彿させる姿で描かれている。
いずれも最上層に廻縁(まわりえん)をめぐらす五層天守だが、色調はそれぞれに特徴があり、破風(はふ)の位置や形状も異なる。「夏の陣図屏風」が長きにわたり「黒い豊臣大坂城」のイメージ定着に影響を与えてきたが、ほかの屏風も含めて見ると、天守の描かれ方は実に多様だ。
なお、文禄5年(=慶長元年、1596)の大地震によって、天守の外観が変わった可能性も指摘されている。一口に豊臣大坂城といっても、時期によって異なる姿であったかもしれず、それも踏まえた議論が求められるだろう。
そして、現天守閣は?
昭和の天守閣復興時の設計主任であった古川重春氏の著書『錦城復興記』などによれば、この時は明確に「太閤秀吉の城を復興する」という意識のもとに進められているので、現天守閣が「豊臣・徳川の折衷デザイン」によってつくられたとはいえない。
上記にあげた屏風のなかで、復興時に最重要資料として参考とされたのは、当時黒田家(旧福岡藩主)所蔵の「夏の陣図屏風」だ。それならばどうして現在のような外観になったのかと言われそうだが、『錦城復興記』からは、この屏風だけでなく大坂城にかかわる文献資料、日本各地の現存城郭(戦災焼失前の名古屋城や和歌山城、広島城も含む)の意匠や構造を広く研究したうえで、外観を決定していることが読み取れる。

「古写真 大阪城天守閣施行記念写真」 (大阪城天守閣蔵)
徳川時代の大坂城が描きこまれた「大坂市街図屏風」(個人蔵、大阪城天守閣寄託)や「大坂市街・淀川堤図屏風」(大阪城天守閣蔵)などで、実際にはなかったはずの廻縁が天守最上層にあったり、外壁の柱が強調されたり、デフォルメされているのは興味深い。作者自身の天守に対するイメージや、豊臣大坂城の残像を投影しているとの指摘もある。絵画資料が必ずしも写実的に描かないものだと思えば、復興にあたり「夏の陣図屏風」を絶対視しないという態度は、むしろ評価されるべきではないか。

「大坂市街・淀川堤図屏風」 (大阪城天守閣蔵)の大坂城部分
今年、復興90周年を迎える現在の天守閣は、大阪市が日本一の人口を誇った「大大阪時代(大正末期~昭和初期)」の繁栄の気運を受けてつくられ、当時最先端の技術と熱心な研究の成果が注ぎこまれたものだ。これ自体が近代建築として、豊臣とも徳川とも異なる独自の価値を持っている。都市のシンボル復興に湧いた時代に思いを馳せ、あたたかく見守っていただきたい。
※上記に紹介した絵画資料のうち、「重要文化財 大坂夏の陣図屏風」「大坂城図屏風」「大坂市街図屏風」「大坂市街・淀川堤図屏風」など大阪城天守閣の収蔵品は、図録『描かれた大坂城・写された大阪城』に掲載されています。徳川時代も含め、大坂城がいかに多様に描かれてきたかがうかがえますので、ぜひご覧ください。
執筆:大阪城天守閣 学芸員 岡嶋大峰
大阪城天守閣
https://www.osakacastle.net/

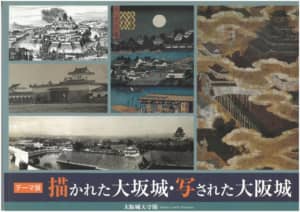
-150x150.jpg)




