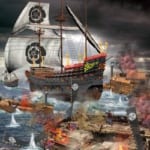Ifの信長史 第9回~東北・郡山で伊達政宗と大野戦~
織田軍が苦戦を強いられた積年の仇がこの地にも
織田軍が苦戦を強いられた積年の仇がこの地にも

CG製作/中村宣夫
足利義昭が将軍職を辞し、ようやく信長の完全なる政権が成立したものの、まだひとつ、懸念されるものがあった。
東北地方の動向で、やはり、天正16年(1588)6月、それは現実となった。後に郡山合戦と呼ばれるようになる伊達政宗の大叛乱である。
政宗は、それまで敵対していた最上義光や佐竹義宣と盟を結び、佐竹家に庇護されていた上杉景勝とも契り、奥羽聯合ともいうべきものを創り上げ、信長に敵対することを宣言したのである。
信長は数年前に臣従してきた真田昌幸を先鋒に、神戸信孝、柴田勝家、前田利家、徳川家康などを遣わしたが、翌7月、ここに予想外の敵が現れた。出羽国に一向一揆が勃発したのである。これらの背後にはむろん石山本願寺があった。
信長はこの本願寺の顕如には幾度となく煮え湯を飲まされてきたが、大坂の地を退去してからはそれほど厄介な存在ではなくなっていた。ところが、ここにきてにわかに勢力を盛り返し、出羽国を臍とした奥州の西沿岸部に理想郷を築き上げようと、旗を挙げたものらしい。さらに面倒なことには、紀州から駆逐した雑賀衆や焼き討ちした伊賀者まで流入していた。このおもわぬ敵の出現により、信長は東北方面の軍勢をふたつに分けざるを得なくなってしまったのだ。
一向一揆に対しては柴田勝家と前田利家、奥州聯合に対しては神戸信孝、真田昌幸、徳川家康。それが仙台における大敗北に繋がった。一揆はどれだけ攻め続けても効果がなく、勝家らは気力が萎えた。一方では、奥州聯合を攻めなければならない神戸が頭を抱える事態となっていた。昌幸と家康が仲違いし、まるで連繋が取れぬようになり、そこを政宗らに衝かれ、一敗地に塗れたのだ。天正17年(1573)2月、奥州方面軍は陸奥国安積郡郡山城に逼塞し、数か月が経った。
(次回に続く)