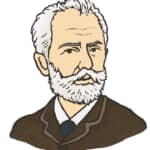石田三成は空気を「読まなかった」のか「読めなかった」のか? “天下分け目の戦い”の勝敗は「忖度」と「空気」が決めた!?
忖度と空気で読む日本史
他人の気持ちや意思をくみとり配慮する「忖度」。ムラ社会に生きる日本人にとって大切な処世術である一方、過剰な忖度が弊害を生み出すこともある。そんな「忖度」「空気」によって引き起こされた歴史的事件や出来事を紹介する本コラム。今回は、空気が読めずに天下分け目の戦いを引き起こしてしまった悲運の武将・石田三成をとりあげる。
■秀吉には忖度するが、同僚に厳しい三成
周知のとおり、関ヶ原の戦いは徳川家康が上杉景勝討伐のため会津に出陣したすきをついて、石田三成が上方で挙兵したことに始まる。
一般に、家康による会津征討は、三成の挙兵を予期しての軍事行動だったといわれることが多い。しかし、会津征討に際し、家康は白河や米沢など5方面から侵攻する計画を立て、従軍諸将や東国諸大名に対し、各方面の先鋒や守備、案内役などこと細かに指示している。その綿密な計画には、本気で上杉氏を倒そうとする家康の気迫が感じられ、とても三成の挙兵を誘うパフォーマンスとは思えない。
一方、三成は家康の東下が、挙兵のチャンスであると早くから考えていたようだ。家康が会津に向かうと、大谷吉継を近江・佐和山城に呼び寄せ、「家康の行状は太閤の遺言に背くばかりか、秀頼公を侮辱するものだ」と述べ、力を合わせて家康を討つべきことを説いた。それに対し、吉継は「愚かなこと。家康の実力・声望は大きく、兵を挙げれば天下が混乱するだけだ」と何度も諫めたという。
吉継としては“人望のないお前が挙兵しても誰もついてこない、空気を読め!”という気持ちだったのだろう。だが、三成は頑として応じなかったため、吉継は敗北を予期しながら協力することを誓うのである。
秀吉にぬるい茶と熱い茶を順番にふるまったという「三献茶」の逸話からもわかるとおり、三成は目端の利く男である。だが、そうした忖度は秀吉に向けられるだけで、他者の気持ちには無頓着なところがあった。
江戸時代に成立した『翁草(おきなぐさ)』という随筆に、次のような逸話がある。ある年の10月、毛利輝元から秀吉に大きな桃が贈られてきた。“珍しい品なので、秀吉様にさしあげたい”という気持ちだったのだろう。ところが、これを受け取った三成は「初冬にこのような大きな桃がとれるとは珍しい。しかし、季節外れの果物を食べて上様がお腹を壊されては一大事だ」といって、使者に桃を突き返したという。
朝鮮出兵で深刻化した加藤清正ら武断派との対立も、秀吉への忖度が過ぎた結果といえる。壮絶な戦いを強いられた蔚山(ウルサン)籠城戦ののち、武将たちから戦線縮小や撤退を主張する意見があがったが、三成ら奉行衆は「それは太閤の命に背くものである」と糾弾した。
前線の武将たちの気持ちを汲もうともせず、杓子定規に秀吉の意向を押し付けたことが、武断派と文治派の対立を深め、関ヶ原の戦いの伏線になったことはよく知られている。
■大義名分をかかげる三成と人心の掌握を重視した家康
このように、三成は秀吉に対し盲目的ともいえる崇敬の念を抱いていた。今回の挙兵も、太閤死後の家康の傍若無人ぶりを許すことはできないという忠義の心に突き動かされてのものだったのは間違いない。
それが分かるからこそ、吉継も三成の要請を受けたのだろう。だが、冷静な吉継は、次のような条件をつけることも忘れなかった。
「家康殿は家柄も良く実力もあるのに、軽輩・小者にも慇懃(いんぎん)で世間の評判が良い。一方、貴殿は態度が横柄で、諸大名から下々の者にまで悪口を言われている。公儀の威光によってうわべは尊敬しているように見えても、本心ではない。その点をわきまえて、毛利輝元と宇喜多秀家を上に立て、出しゃばらぬことが大切だ」と説いた。散々な言われようだが、三成の立ち位置を見極めた的確なアドバイスといえよう。
ここからの三成の動きは早かった。秀頼のいる大坂城に輝元を迎え、増田長盛ら奉行衆との連名で家康の非を糾弾した「内府ちかひの条々」を作成し、諸大名にばらまいて世論の形成に努めた。一連の工作により、三成は自身の私怨による挙兵を、豊臣政権による公戦という形にすることに成功し、挙兵の大義名分を得たのである。
一方、やり玉に挙げられた家康は、黒田長政ら与党の武将を介して西軍諸将に内通を呼びかけたうえ、1か月も江戸にとどまり、全国の諸大名に協力を求める書状を送りつけた。
大義名分をよりどころとした三成と、人々の心をつかむことに注力した家康。この違いが、関ヶ原の最終決戦に表れたといえるだろう。三成や宇喜多秀家らが奮闘する中、西軍の吉川広家や毛利秀元、島津義弘など多く武将が戦闘を傍観した。最後は小早川秀秋の裏切りにより盟友・大谷吉継は自害、三成は刑場の露と消えるのである。

『太平記英勇伝』「岸田光成」 東京都立博物館蔵