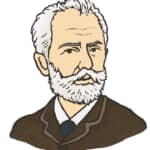攘夷運動は「日本を守る戦い」か「排外主義」か? 古代・中世とはケタ違いの摩擦を生んだ、近世初頭と幕末の“外国人問題”
昨今話題の“外国人問題”。その背景にはグローバル化があるが、歴史的に見ても、外国人との軋轢は、世界的なヒト・モノの移動によりもたらされてきた。豊臣政権の禁教令はヨーロッパの大航海時代に端を発し、幕末の攘夷運動は西欧列強の植民地獲得競争が契機となった。古代・中世とはケタ違いの摩擦を生んだ、近世初頭と幕末の“外国人問題”を見てみたい。
■キリスト教から日本人と領土を守ろうとした豊臣秀吉
日本人に西欧の脅威を感じさせた最初の出来事がキリスト教の到来であった。
天文18年(1549)、フランシスコ・ザビエルが鹿児島で布教を開始して以後、イエズス会の宣教師が次々と来日。南蛮貿易の利を求めるキリシタン大名の庇護を受けて、急速に信者を増やしていった。
外国人が増えれば、当然日本人との軋轢も生じる。ザビエルは最初の布教地である薩摩で、さっそく仏教勢力の妨害を受けており、永禄4年(1561)には平戸で、貿易をめぐるトラブルによるポルトガル人の殺傷事件も起きた。
やがて、キリシタン大名の中から、領民を強制的に信者にして神社仏閣を破壊させる者、自身の領地をイエズス会に寄進する者まで現れる。南蛮貿易を通じて日本人を奴隷として売買することも行われた。信仰の問題にとどまらず、日本人の身体や領土まで危機にさらされることとなったのである。
これを問題視したのが天下人・豊臣秀吉であった。九州平定後の天正15年(1587)6月、キリシタン禁令を発令。キリシタン大名や宣教師による一連の行為を禁じ、騒動の大本である宣教師の国外退去を命じた(伴天連追放令)。大村純忠がイエズス会に寄進した長崎・茂木は没収され、各地で教会が破却された。
しかし、秀吉が南蛮貿易を認めたこともあって禁教令は徹底されず、その後もキリシタンの数は増え続け、“外国人政策”は江戸幕府の課題として持ち越された。
■尊王攘夷は「日本人を守る」戦いだった?
近代以前の日本において、外国人への拒否感が最高潮に高まったのは幕末である。ペリーが黒船で来航し、幕府に開国を迫って以後、「野蛮な夷狄(いてき)を打ち払え」「幕府の祖法である鎖国を守れ」といった強硬な攘夷論が声高に唱えられた。
特に日米修好通商条約が調印され、横浜・箱館などが次々と開港されると、各地で攘夷論者による外国人襲撃が多発する。安政6年(1859)、ロシアの士官と水兵が横浜で惨殺、同7年にも横浜でオランダ船長と商人が殺害された。以後、アメリカ領事館通訳のヒュースケン襲撃事件、高輪・東禅寺のイギリス公使館襲撃事件など、各国公使を狙ったテロに発展していく。
日本人が外国人に反感を抱いたのには理由がある。日米通商修好条約は日本側に裁判権や関税自主権のない不平等条約であった。市場では、外国人商人による威圧的な取引が行われ、日本人を利用して密かに国内の商取引に参入する者もいた。
開国は国民生活にも大きな影響を与えた。対外貿易が大幅な輸出超過となったことで物価が急上昇。金貨の大量流出がこれに拍車をかけ、下級武士や庶民の生活を圧迫した。
こうした事実を見る限り、(テロは論外として)攘夷の思想それ自体は、国民の利益を守る健全なナショナリズムの発露であり、「日本人の生活を守る」戦いだったといえるかもしれない。
その一方、攘夷論者の中に、単に外国を夷狄として見下す狂信的な排外主義がはびこっていたのも確かだ。例えば、坂下門外の変に参加した水戸浪士は「このままでは日本人が外夷と同様に禽獣の群れになってしまう」という危機感を吐露している。こうした思い込み、決めつけレベルの観念的な差別意識によって、彼らの凶刃は操られていたのである。
■『ペリー提督日本遠征記』が描く日本人と米兵の交流
最後に殺伐とした攘夷運動と一線を画す、日本人とアメリカ人のささやかな交流の場面を紹介したい。『ペリー提督日本遠征記』に残された記録である。
ペリーの1回目の来航時のこと。ペリー艦隊が江戸湾で測量を行っていると、外国人を見たいという住民が集まって来た。住民のある者は、測量船に向かってあらゆる身振り手振りを使って歓迎の気持ちを表し、きれいな水や特産の梨を米兵に提供した。
そうこうするうちに、互いに友情が湧いてきて、タバコを交換して吸ったり、アメリカ士官が短銃を撃って住民たちを喜ばせる光景も見られた。帰艦した水兵たちは、日本人の親切な気質と景色の美しさに有頂天になっていたという。
ここに記された日本の住民には、外国人に対する恐れも警戒心もみられない。異なる国の人間同士であっても、先入観を排し、予断を持たずに接すれば、言葉や人種の壁を越えて心を通わせることができるのかもしれない。

「横浜休日亜墨利加人遊行」国立国会図書館蔵