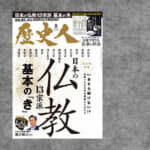『西遊記』三蔵法師のモデル・玄奘を始祖とする日本の仏教宗派【法相宗】とは─仏教13宗派の歴史─
日本の仏教13宗派 基本の『き』#03
■玄奘三蔵から伝えられた「唯識説(ゆいしきせつ)」を重視

法相曼荼羅図
中央に宝冠を被った弥勒菩薩が描かれている。唯識思想は、兜率天で弥勒菩薩からインドの無著、世親へと伝えられたとされる。(東京国立博物館蔵/ColBase)
法相宗(ほっそうしゅう)は、、唐時代の中国で7世紀半ばに成立した。『西遊記』に登場する三蔵法師のモデルとなった玄奘(602~664)がインドから唯ゆ い識し きの経典を伝えたことに始まる。その弟子の基(窺基、慈恩大師)が「唯識経典」の教えを整理・体系化して教義を確立した。ここから玄奘を始祖、基を宗祖と呼ぶこともある。
唯識とは、われわれが現実と思っているものは心が生み出したものにすぎず、確かに存在しているのは識(心)だけとする教え。教えが難解であるため一般には信仰が広まらず、中国仏教の主流となることはなかったが、華厳宗や天台宗など他の宗派にも影響を与えた。
日本へは白雉4年(653)に唐に渡った道昭(629~700)によって伝えられた。道昭は玄奘より直接教えを受けたと伝えられている。
道昭は帰国後、飛鳥寺で教えを広めたが、平城遷都後は元興寺に移った。
その後、智通・智達・智鳳・智雄・玄昉などが唐に留学して法相宗の教えを学んだ。中でも玄昉(?~746)が朝廷に重用され政治にも参与することになったことから、法相宗の地位も向上した。また、帰国後の玄昉が興福寺を拠点としたことから、興福寺は法相宗の中心的寺院となった。
道昭の弟子の行基、智鳳の弟子の義淵も朝廷が尊崇する名僧となったことから、法相宗は南都六宗の中でもっとも有力な宗派となった。
平安時代以降は興福寺が藤原氏の氏寺として勢力を強めたこともあって、大きな政治力をもつようになった。その一方で法相宗の教義は仏教の基礎として広く学ばれた。
興福寺のほか、奈良の薬師寺と法隆寺が大本山として信仰を集めていたが、戦後、法隆寺は聖徳宗を立宗して離脱した。興福寺の末寺だった京都の清水寺も北法相宗本山として独立した。
監修・文/渋谷申博