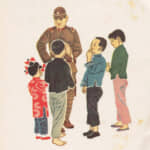朝ドラ『あんぱん』復員船に乗るまでは何をしていた? 史実ではたらふく食べ、絵を描き、芝居をつくる日々
朝ドラ『あんぱん』外伝no.46
NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』は、第13週「サラバ 涙」が放送中。嵩(演:北村匠海)はやっとの思いで御免与町に帰還する。駅には夫を亡くして憔悴しきったのぶ(演:今田美桜)がいたが、互いに気づかなかった。嵩の帰りを、伯母の千代子(演:戸田菜穂)は心から喜ぶ。史実でも、やなせたかし氏は約8ヶ月にわたって、中国で復員輸送船の順番が回ってくるまで待機していた。しかし、その生活は我々の想像に反して自由かつ文化的なものだったのだ。
■衣食住に困らず、現地住民との関係も良く、趣味に没頭する日々
昭和20年(1945)8月15日、正午の玉音放送で、ポツダム宣言の受諾と日本の降伏が国民に公表された。やなせたかし氏(本名:柳瀬 嵩)はそれを、上海の朱渓鎮(現在の朱家角鎮付近)で迎えている。
終戦を迎えた後は、日本人捕虜として収容されることもなく、広い建物を利用した居住地が与えられて復員船の順番を待つことになったという。驚くべきは、現地の人々と非常に友好な関係を築いていたということだ。著書『ぼくは戦争は大きらい: やなせたかしの平和への思い』(小学館クリエイティブ)によると、日本軍の存在が付近の盗賊の襲来を牽制することに繋がっていたらしく、現地住民からもそのことで「ずっといてほしい」と言われるほどだったとか。
福州からの移動においては深刻な食糧不足に見舞われたが、朱渓鎮には“上海での決戦”を想定してかなりの量の食糧が備蓄されていた。そして終戦を迎えると「どうせ連合国軍に没収されるなら、自分たちで食べてしまおう」と、連日大量の食材が消費され、豪華な料理が並んだという。お腹を空かせるためにみんなで外を走る習慣もあったほどで、食にはまったく困らなかった。
衣食住が満たされていると、次は娯楽が求められるようになるのは世の常だ。やなせ氏がいた部隊でも、やがて部隊のなかに賭場ができたりした。また、将校や下士官のなかにはやなせ氏に「絵を教えてくれないか」と頼みにくる人がいたらしい。そのうち、あちこちで絵を描いたり、俳句を詠んだりする会ができるようになり、戦時中にできなかった文化的な趣味を楽しむ時間がもてるようになった。言ってしまえば、軍の中に趣味のサークルができたような感じだ。
中隊ごとに“演劇部”のような会もあり、やがて聯隊規模で演劇コンクールをしようということになった。やなせ氏は大隊本部の下士官で構成される芝居の上演を提案し、脚本・演出を担当。音楽に秀で、ハーモニカを得意とする曹長が作曲した音楽に、歌詞をつけたりもしたらしい。戦争が終わって、帰国こそできずともやなせ氏のマルチな才能は既に発揮されていた。
広い食糧倉庫で稽古が始まり、衣装は生地などを調達して手作りした。当然女性はいないので、女性の役もそのグループ内の下士官が担当した。なんと上官にコンクールの審査を依頼したらしいのだが、どのグループの演劇も大好評。最終的に上官も「甲乙つけがたい」としたらしい。こうしたエピソードからも、終戦を迎えて復員船を待つ間、やなせ氏がいた部隊では階級を問わず比較的余裕のある生活を送っていたことが窺える。
やなせ氏は著書において、自身が漫画家として漫画を描くだけでなく、歌詞を書いたり、詩を書いたりと幅広い文化活動をしていることに触れ、「今思えば、軍にいたころから同じようなことをしていた」というように振り返っている。後年、その豊かな才能を作品づくりに注いで夢と希望を届けることになるやなせ氏の原点は、戦争体験のなかにもあったのである。
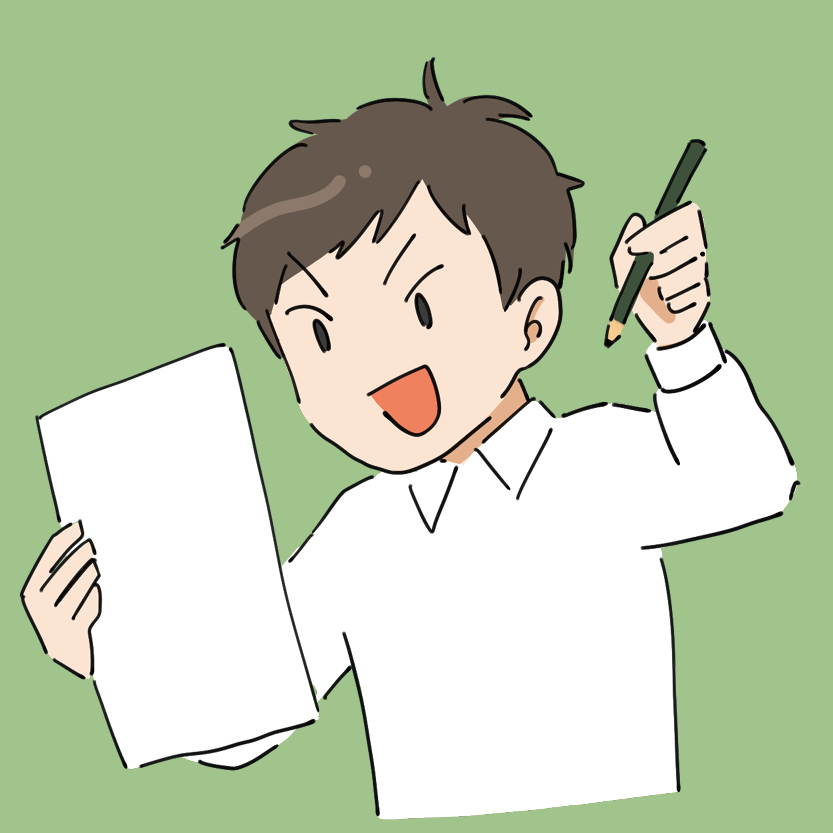
イメージ/イラストAC
<参考>
■やなせたかし『アンパンマンの遺書』(岩波現代文庫)
■やなせたかし『ぼくは戦争は大きらい: やなせたかしの平和への思い』(小学館クリエイティブ)