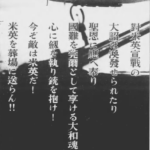「ニセ日本人人骨事件」を乗り越えて…予算がつかず、遅々として進まなかった戦没者遺骨収集事業
パラオ戦没者遺骨収集のいま
■古き日本の面影が残るパラオ

ペリリュー島の西太平洋戦没者慰霊碑
パラオ諸島は1919年から約四半世紀日本統治下にあったため、多くの日本文化、習慣、風習が現在でも多く残っている。例えば、日常生活用具では「タライ」「エモンカケ」「ノコギリ」「ホウチョウ」「タンス」「オケ」「カイダン」など。日常会話でも「キリツ」「マエナラエ」「キュウケイ」「オハヨウ」「アリガトウ」「スマン」など。おもしろいことに、「全島民運動会」もアンガウル島では毎年秋におこなわれている。種目には「玉入れ」「リレー」「綱引き」などが赤白2色に分かれて実施されている。
このため、戦後80年たった現在でも多くの国民が「親日的」「好日的」で、第2公用語が「日本語」に指定されている。世界3大ダイビングスポットという側面もあり、日本からの観光客訪問客には親切友好的に接する人々が多い。しかし、コロナ期間中はやはり外国からの来訪者を強く制限したため、コロナ後でも日本からの直行便が無くなったこともあって、まだ日本からの来訪者数は復活していない。この直行便が無いために、どうしてもグアム、台湾、フイリピン経由となっており、グアム便にいたっては空港でのトランジットが数時間待機という現状である。しかも、その便数はどの経由も極端に減少している。やっと、2025年秋に成田—コロール直行便が週2で復活するとの情報が入ってきている。

ペリリュー島米軍上陸地点のホワイトビーチ
日本では戦後早くの時期から、太平洋戦争で亡くなった戦没者の遺骨収集事業が厚生労働省を主管に始められてきた。戦後、保守政権が長く政権を担ってきたにもかかわらず、実はこの事業には多くの予算がつけられてこなかった。このため、推定350万人といわれる「在外戦没者」の遺骨はシベリアの凍土、満州の荒野、ニューギニアの密林、ミャンマーの山峡、南太平洋の孤島などに放置されたままできた。
1990年代に入り、やっと各地での収集事業が始動し、シベリア、ミャンマー、フイリピン、マリアナ、ニューギニア、ガダルカナル、チューク(トラック諸島)などで定期的な活動が本格化した。しかし、そこに降ってわいた事件が「ニセ日本人人骨事件」であった。
外地での戦没者遺骨収集事業の究極的な目的は、収集した「ご遺骨」の人物特定をして、その方のご遺族、近親者に返還することである。このために、最新の「DNA鑑定」などの手法がとられるのだが、精密な「DNA鑑定」が日本国内でしか出来ないのが現状である。
そこで、各地で収集された人骨を日本に持ち帰る作業が頻繁に実施されるようになったが、なんとシベリア・フイリピン・ミャンマーなどで収集遺骨の中に「現地人」「人骨以外」「獣骨」が混入、混在していることが発覚したのである。
パラオでは1952年最初の遺骨収集団が派遣され、これまでペリリュー島だけでも7800柱が収集されてきた。
その後2015年4月8〜9日、当時の天皇・皇后両陛下がペリリュー島を訪問し、西太平洋戦没者慰霊碑で日本から持参した白菊を献花したことが契機に、2016年臨時立法で厚生労働省直の事業が「日本戦没者遺骨収集推進協会」(JARRWC)が設立され、同協会下で各地の事業が計画実行されてきた。対象地域は、シベリア、旧満州、ミャンマー、インド、フィリピン、マリアナ、ソロモン、パラオ等である。
ペリリュー島では、先述したように1950年代から民間の「遺族会」「戦友会」等が独自に「慰霊団」「遺骨収集団」を派遣して、島内各所で散発的な「戦没者遺骨収集」を実施、焼骨後に日本へ持ち帰っている。
その一方、「戦跡」等に興味をもつ篤志家らの精力的な活動で島内に残る「日本兵墓地」(富山地区など)や「戦車埋没地」情報が確認され、協会側も米国国立公文書館でパラオ関係米軍資料の探索から「アンガウル島サイパン地区集団墓地」「ペリリュー島日本兵集団墓地・埋葬者数1086人」などの存在が推定されていた。

ジャングル内に放置されている95式戦車
2016年度からの調査では、米軍上陸地「ホワイトビーチ」近辺のジャングル内に戦後米軍によって埋蔵された「旧日本軍95式軽戦車」が何台か露見され、さらに金属探知機などであと複数カ所「戦車に埋蔵地候補」が発見された。
95式軽戦車は97式中戦車と並んで、太平洋戦争で一番多く使用されたもので、ほとんどの戦車連隊に配属され、最終的に2374台生産された。だが備砲は37ミリ、装甲は12ミリしか無かった。このため、米軍の主力戦車M4シャーマンなどの75ミリ砲には全く歯がたたなかった。
ペリリュー島でも1944年9月15日上陸した米軍に対して、天野大尉率いる戦車中隊17両(1両は故障で参加せず)が翌日滑走路を巡る攻防で出撃、内2両が米軍の猛攻撃をぬけ、海岸部の米軍陣地まで突入した。
そもそも戦後の「戦没者遺骨収集事業」は遅々としてなかなか実施されて来なかった。米軍は原則として、戦死者の遺骨は必ず故郷に返還することとしている。このため、どのような戦場にも「遺体収納袋」を用意していた。一方、日本軍では日清・日露戦争時には戦死した友軍の遺体を戦闘後収容して、荼毘にふした後、遺骨箱に収納する余裕もあった。しかし、太平洋戦争島礁部の玉砕・全滅戦では、そのような余裕もなく、多くの戦死者が現地に放置されたままになっていった。今次大戦での内外戦死者総数は約310万人、この内外地でのそれは約240万人と推定されている。国の計画的な「戦没者遺骨収集事業」は1952年やっと開始され、1975年度まで23万柱強が収容されたが、これは全体のわずか9.6%に過ぎない。現在では、中部太平洋(パラオなど)17万3千柱、フイリピン36万9千柱、中国(旧満州など)23万3千柱、東部ニューギニア(ソロモン諸島など)13万4千柱が未収集のご遺骨数と推定されている。

ペリリュー島天皇陛下行在所