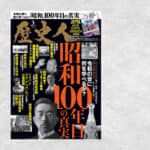「日本を守るとは、天皇を中心とする歴史と文化の伝統を守ること」 三島由紀夫は何を目指したのか?【昭和100年目の真実】
昭和100年目の真実 #04

東京・市ヶ谷にある防衛省
■自衛隊駐屯地に立て籠もり決起を呼びかける
昭和45年(1970)11月25日、作家の三島由紀夫は自ら設立した民兵組織「楯の会」会員の20代の若者4人とともに、東京・市ヶ谷にある陸上自衛隊市ケ谷駐屯地の東部方面総監部を訪れた。現在は防衛省がある。
約束していた益田兼利総監との面会の場で、三島は日本刀などを武器に総監を人質にし、隊員に向かって演説させるよう要求した。三島は総監室前のバルコニーに出て、部隊内の放送を聞いて集まった自衛隊員ら約1000人に対し、憲法改正と隊員の決起を訴えた。
「日本を守るとは何だ。天皇を中心とする歴史と文化の伝統を守ることである」「男一匹が命を賭けて諸君に訴えているんだぞ。いま日本人がだ、自衛隊が立ち上がらなきゃ、憲法改正ってものはないんだよ。諸君は武士だろう。武士ならばだ、自分を否定する憲法をどうして守るんだ」「諸君の中に一人でも俺と一緒に立つやつはいないのか。…一人もいないんだな。それでも武士か。憲法改正のために立ち上がらないと見きわめがついた。これで、俺の自衛隊に対する夢はなくなったんだ」
上空を報道のヘリコプターが飛び、隊員から「引っ込め」「ばかやろう」などとヤジも飛び騒然となった。演説を10分ほどで切り上げた三島は「天皇陛下万歳」を叫んだ後、総監室に戻って日本刀で切腹自殺した。享年45歳。25歳の楯の会会員、森田必勝も切腹した。残った会員3人は昭和47年4月、監禁致傷や嘱託殺人などの罪で懲役4年の実刑判決を受けた。
■世界的な作家は何を目指していたのか
三島の本名は平岡公威。東大法学部を卒業後、大蔵省に勤めたが9カ月で退職。昭和24年に長編『仮面の告白』で作家としての地位を確立した。昭和29年の『潮騒』で新潮社文学賞、昭和31年の『金閣寺』で読売文学賞、昭和40年の戯曲『サド侯爵夫人』で芸術祭賞。諸外国語に翻訳されて各国でも読まれ、ノーベル文学賞候補にも挙げられた。自決事件は、『豊饒の海』第4巻「天人五衰」の最終回原稿を書き上げた後のことだった。世界的作家が起こした事件は社会に大きな衝撃を与えた。佐藤栄作首相は「気が狂ったとしか考へられぬ」と日記に書き、中曽根康弘防衛庁長官は「迷惑千万。常軌を逸した行動」と会見で批判した。一方で右翼は「義挙」と評価した。
三島は1960年代後半ごろから、政治色の強い文学作品や評論を発表していた。ボディビルで体を鍛え、自衛隊への体験入隊を繰り返した。
昭和41年に発表した短編小説『英霊の聲』では、二・二六事件で決起した青年将校や神風特攻隊の兵士らの霊が、戦後の昭和天皇による人間宣言を呪う話を書いた。昭和43年10月には民族派学生を集めて「楯の会」を結成した。
昭和44年5月13日には東京大学駒場キャンパスの大教室で、東大全共闘との討論会を行った。同年1月に全共闘が機動隊と攻防戦を展開した安田講堂事件について、「天皇という言葉を一言彼らが言えば、私は喜んで一緒に閉じこもっただろう」と語り、「諸君の熱情は信じます」と共感を示した。
監修・文/北野隆一