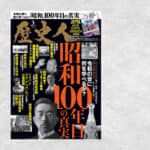高度経済成長がもたらした「影」とは⁉ ─日本発展の裏でなにがあった?─【昭和100年目の真実】
昭和100年目の真実 #02
■所得倍増を実現し世界第2位の経済大国へ

イメージ
高度経済成長とは、経済規模が高い伸び率で拡大し続けることをいう。日本の場合は昭和30年(1955)ごろから昭和48年ごろまで、実質経済成長率が年10%前後で続いた時期を「高度経済成長期」と呼ぶ。
日米安保条約の改定をめぐって反対運動が盛り上がった「六〇年安保」の後、首相が岸き し信の ぶ介す けから池田勇は や人と に交代した。池田は「寛容と忍耐」を基本姿勢に掲げ、「国民所得倍増計画」をつくり、国民の関心を「政治」から「経済」に転換させた。
10年間で実質国民総生産(GNP)を2倍に引き上げると設定し、石油・鉄鋼など重化学工業への転換などを掲げた。石炭から石油へのエネルギー政策の転換により炭鉱産業が斜陽化。合理化のための大量解雇に労組が反対し、昭和35年には戦後最大の労働争議といわれる三井三池争議が起きた。
1人あたりの実質国民所得は昭和43年には昭和35年の2倍を超え、昭和45年には2・5倍に。昭和43年にはGNPが米国に次ぐ第2位となり、その後、国内総生産(GDP)が平成22年(2010)に中国に抜かれるまで約40年間、世界第2位の「経済大国」であり続けた。
生活水準が上昇し、「三種の神器」と呼ばれた電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビが普及。その後、「三C」と呼ばれた自動車(カー)、クーラー、カラーテレビが家庭に導入された。昭和42年に日本の人口が1億人を突破し、生活の豊かさが感じられるようになると、国民の大多数が自分たちを中流階級と意識する「一億総中流」の概念が広まった。昭和45年ごろには、江戸時代中期の5代将軍・徳川綱吉(とくがわつなよし)の治世に経済や文化が熟した時期の元号になぞらえた「昭和元げ禄」とも呼ばれた。
■高度成長がもたらした「影」の部分とは
一方で、経済成長に伴う「影」の部分も顕在化した。農村部の中卒の若者が「金の卵」と呼ばれて都市部の工場などに大量採用される「集団就職」が行われ、農村部は労働力が流出する「過疎」、都市部は人口が集中する「過密」の状態となった。工業開発による環境汚染や公害問題が深刻化した。
国際的にはニクソン米大統領が金ドル交換停止などの経済政策を打ち出した「ニクソン・ショック(ドル・ショック)」で円が切り上げられた。昭和48 年には国際通貨不安により固定相場制が崩壊し、世界が変動相場制に移行。同年10月には第4次中東戦争をきっかけに、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)による石油戦略が発動され、原油価格が上昇する「オイルショック」が起き、高度成長期は終わりを告げた。
21世紀に入ると、高度成長期は昭和の古きよき時代を懐かしむレトロブームのシンボル的な時代となった。1950~60年代の人々や風俗を描いた西岸良平の漫画「三丁目の夕日」は平成17年、「ALWAYS 三丁目の夕日」として映画化された。東京タワーの建設が進む昭和33年の東京下町を舞台に、人々の心温まる物語がヒットし、3作がつくられた。安倍晋三が首相になる前に出版した『美しい国へ』で絶賛したことも話題となった。
監修・文/北野隆一