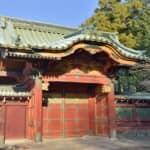紫式部と藤原道長は遠い親戚だった? 平安女流作家たちの意外な関係とは
「歴史人」こぼれ話・第44回
いよいよ2024年大河ドラマ『光る君へ』が放送開始となる。主人公の紫式部を取り巻く人々が織りなす複雑な人間模様と、平安宮中の華やかな日常が描かれる予定だが、やはり注目すべきは強くしなやかに生きた女性たちだろう。今回は現代の我々もよく知る女流歌人たちの出自と関係性について紹介する。
■どこを辿っても藤原! 紫式部の出自と道長との意外な繋がり
平安時代の著名な日記文学・随筆文学として、紫式部の『紫式部日記』、清少納言の『枕草子』、和泉式部の『和泉式部日記』、藤原道綱母の『蜻蛉日記』、そして菅原孝標女の『更級日記』が挙げられる。いずれも学校の授業で一度は耳にしたことがある作品だが、その作者である女性たちの間には意外な繋がりがあることをご存知だろうか。
まずは大河ドラマ『光る君へ』で注目の紫式部。彼女の父親は藤原為時(ふじわらのためとき)という人物で、藤原北家・良門(よしかど)流の生まれだった。今回カギを握る「藤原北家」とは、中臣鎌足(なかとみのかまたり/後に藤原に改姓)の孫であり、藤原不比等(ふひと)の次男・藤原房前(ふささき)を祖とする一族のことをいう。他に南家、式家、京家があるが、後に最も繁栄したのが北家だった。
紫式部から6代遡ると藤原冬嗣(ふゆつぐ)という人物にあたるが、その6男である藤原良門(よしかど)を祖とするのが良門流だ。つまり紫式部は藤原北家の傍流の家に生まれたということになる。後に時代の寵児となって摂関政治を確立させた藤原道長は、この北家の嫡流に生まれた。そして道長から6代遡れば、これまた冬嗣に行き当たる。2人は遠い縁戚関係にあったのだ。
加えて、紫式部の夫となった藤原宣孝(のぶたか)もまた、藤原北家の人間だ。こちらは高藤(たかふじ)流という一族で、良門の次男・藤原高藤を祖とする。

紫式部は『源氏物語』で何度も曾祖父・兼輔が娘の桑子を想って歌ったとされる歌を引用している。紫式部にとって、それだけ大きな存在だったのだろう。
さて、次は冬嗣の長男である長良(ながら)を祖とする藤原北家・長良流へと目を移そう。この長良の曾孫にあたるのが藤原倫寧(ともやす)という人物だ。彼の娘の1人が『蜻蛉日記』を書いた藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)で、藤原兼家の妻だった。その兼家の正室・時姫が産んだのが道長で、ここでも遠回りながら繋がってくる。
さらに、藤原道綱母の姉妹の1人が嫁いだ相手が菅原孝標(すがわらのたかすえ)で、2人の間に誕生したのが『更級日記』の著者である菅原孝標女だ。『蜻蛉日記』と『更級日記』の著者2人はおばと姪の関係にあった。
では、清少納言はどのような生まれだったのだろうか。彼女の父は百人一首にも名を残す高名な歌人・清原元輔だった。元輔には清少納言の他にも子がいたのだが、そのうちの1人が嫁いだ相手が藤原理能(まさとう)という男だった。この理能の妹が、先ほど登場した道綱母なのである。従って、清少納言と道綱母は「きょうだい同士が結婚した」という関係になる。
さて、やや強引なところもあるが、これで4人の才女が繋がった。藤原北家の栄華は言うに及ばず、藤原四家とそれを取り巻く人々も平安の歴史を語る上では欠かせない人物が多い。
冒頭に挙げた5人のうち、唯一系図上近しくないのが和泉式部だ。彼女の父は大江雅致(まさむね)、母は平保衡(たいらのやすひら)の娘と言われる女性である。和泉式部は最初和泉守橘道貞と結婚したが、後に破綻。その後、かの有名な為尊親王、敦道親王兄弟との恋愛などを経て、道長の家司(けいし)を務め武芸に秀でた藤原保昌という人物と再婚した。和泉式部は紫式部の同僚であり、道長の娘・彰子に仕えていた縁からと思われる。保昌は推定で20歳ほど年長で、この結婚時、和泉式部も35歳くらいだったといわれる。恋多き女性の最後の夫が年上の武闘派だったのは面白い。ちなみに、保昌は所謂「藤原四家」の生まれではあったが、北家ではなく南家出身だった。
参考文献:福家俊幸著『紫式部 女房たちの宮廷生活』(平凡社新書)