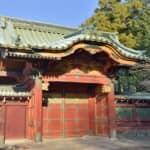山城を拠点とする城主・家臣団の暮らしとは? 全国の山城に遺された往時の痕跡
「歴史人」こぼれ話・第42回
麓から遠く離れた山中・山頂に造られた山城。自然の地形を活かした鉄壁の防御というメリットがある一方で、城主や家臣たちの暮らしとなると不便に思える。実際のところ、山城を拠点とした武士たちはどのようにしてこの城を活用していたのだろうか。そのヒントは、城跡や「城」の歴史に隠されている。
■一見不便そうに見える山城の居住性
山城は、麓からの高さがおよそ100mを越える城のことを指している。現代でいえば、30階以上のタワーマンションに相当する。眺望がよいのは、今も昔も変わらない。ただし、現代と大きく異なるのは、エレベーターのような文明の利器が使えないということである。
もちろん、城主なら、それほどの心配をする必要はない。ある程度のところまでは馬で登ることもできるし、城内に構えられた御殿に常住することも可能である。毎日、登ったり下りたりする必要はない。炊事などをどうしていたのかは不明であるが、おそらく御殿の近くに炊事小屋などを設け、女中も住まわせていたのだろう。必要な物資も、やはり小者などの配下に麓から運ばせていたにちがいない。
このように、山城であっても居住するには問題なかった。実際、河内・三好氏の飯盛城、近江・浅井氏の小谷城、越後・長尾氏の春日山城(かすがやまじょう)、安芸・毛利氏の吉田郡山城(よしだこおりやまじょう)、出雲・尼子氏の月山富田城(がっさんとだじょう)などでは、城内に居館が設けられていたとみられる。これらの城には千畳敷(せんじょうじき)あるいは大広間とよばれるような広い空間があり、そうした曲輪(くるわ)があればこそ、居館をおくことができたのだった。
ただし、すべての武士が山上に暮らしていたとは限らない。むしろ、平時は平地の居館に暮らしていた場合のほうが多かったと考えられる。もちろん、居館は平城であるから、防御の点からすれば、まったく堅固とはいえない。だから、平時には平城の居館に生活し、戦時には山城に籠ったのである。このように、戦時に籠もるために用意された山城を、特に詰の城という。
詰の城には、駿河・今川氏の賤機山城(しずはたやまじょう)、甲斐・武田氏の要害山城、若狭・武田氏の後瀬山城(のちせやまじょう)、周防・大内氏の高嶺城、豊後・大友氏の高崎山城、越前・朝倉氏の一乗谷城(いちじょうだにじょう)などがある。いずれも、居館の近くに築かれた山城だった。こうした詰の城には、普請のあとがあまりみられないことがある。そのため、実際に詰の城であるのか否か、疑問が呈されることも少なくない。しかし、あくまでも有事に必要な城であることを考えれば、さしたる普請が行われないこともあったのだろう。

小谷城で最大の曲輪「大広間」は「千畳敷」ともよばれる居館があったとみられる。
撮影:小和田泰経
■居館と詰の城の二元構造論争の行方は?
従来、戦国時代の武士は平時の居館と戦時の詰の城をセットにしていたと考えられてきた。このような考えに対しては、最近、山上に生活の拠点をおいていた城もあることから、居館と詰の城という二元構造について、否定的な見解もある。たしかに、飯盛城、小谷城、春日山城、吉田郡山城、月山富田城のように、生活するための居館があったとみられる山城が存在するのも事実である。当然のことながら、このような山城に平地の居館は必要ない。ただし、そのような山城は、むしろ一般的ではなかったのではないだろうか。
というのも、古代に朝廷が築いた山城は別として、武士の城は、居館から始まっているとみられるからである。すでに武士の城については、鎌倉時代から文献に記録が残されている。しかし、文献に残されている城というのが、山城であったとは限らない。
そもそも、鎌倉時代や室町時代に、将軍が城に居住することはなかった。鎌倉幕府がおかれた鎌倉や室町幕府がおかれた京都は、文献に「鎌倉城」や「平安城」などとみえるが、これは都市を意味しており、城ではない。鎌倉時代や室町時代の将軍が住んでいたのは平地の居館であり、御所とよばれている。居館に生活していたのは、政治的な目的のためである。ちなみに、室町幕府の将軍も京都の洛中に花の御所とよばれる居館をもっていたが、別途、周囲の山に勝軍山城などを詰の城としていた。
だから、幕府の命で各国におかれた守護は、当初は平地に守護所を設けたものと考えられる。当然、この守護所は、山城ではない。もし、守護が堅固な山城に居住すれば、すぐさま謀反を疑われたことだろう。
鎌倉時代や室町時代には、守護所がそれぞれの国の中心となった。だから、戦国時代になると、守護所としていた居館とは別に、詰の城を設けたのである。今川氏、武田氏、大内氏、大友氏はいずれも守護であり、朝倉氏は幕府から守護相当の地位を認められた守護代の出身だった。つまり、もともと政治的な意味を持つ居館を本拠としていたため、別途、軍事的な意味を持つ詰の城を構えたことになる。
これに対し、山上に居住していたとみられる三好氏、浅井氏、長尾氏、毛利氏などは、いずれも守護代や国人の出身であった。当然、もともとの居館は、政治の中心に築かれてはいない。だから、早い段階から山城に拠点を移すことができたといえないだろうか。
もともと武士は平地の居館に居住しており、戦国時代になって、山城に居城をそっくり移す場合と、居館とは別に詰の城を構える場合の二つがあったというのが実際のところであったと思われる。

月山富田城では、山の中腹に位置する「山中御殿」に城主の居館が設けられていたとみられる。
撮影:小和田泰経