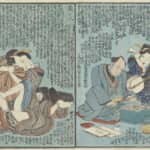「白い目で見る」のルーツ!結婚を拒むため60日間酔っ払い続けた三国志の人物とは?
故事成語で巡る中国史の名場面
日常で何気なく使われる、「白い目で見る」という言葉。実は中国の三国時代末に本当に“白目”を剥いていた人物がルーツとなっていた。当時の権力者に実力を認められながらも、酒を愛し俗世を嫌って生きたその人物とは、一体何者なのか…?
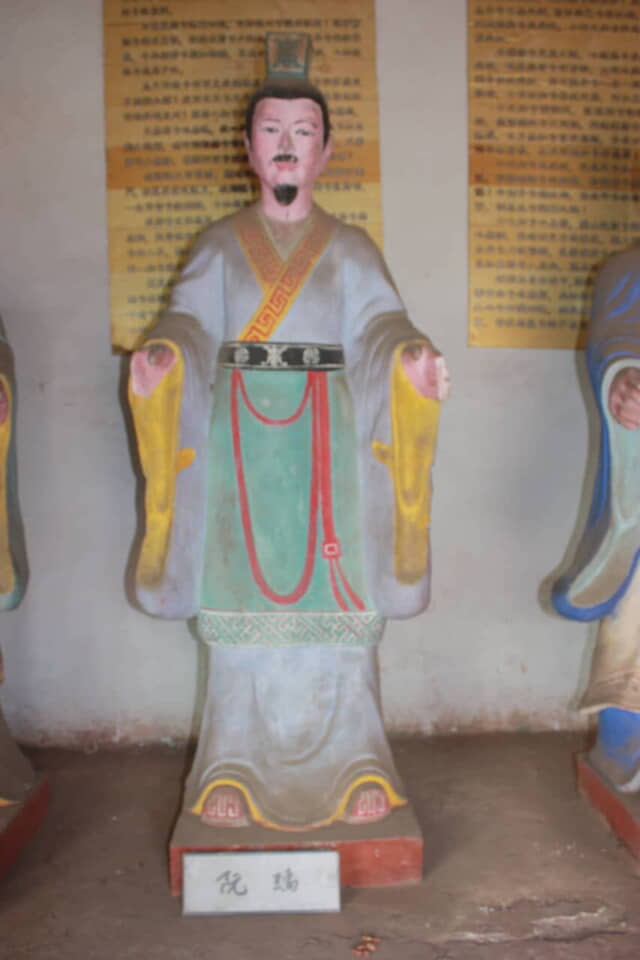
曹操が本拠地とした河北省臨漳県鄴城三台遺址に立つ阮籍の像
■「白い目で見る」の由来は本当に“白目”だった!?
誰しも白い目で見られるのは居心地が悪い。理不尽な同調圧力に抗うというなら気力も湧いてくるが、非が自分にあると明白な場合は、そそくさと退散するくらしか、選択肢が思いつかない。自分が「見る」側ならともかく、「見られる」側にはなりたくない。「白い目で見られる」とはそれくらい恐ろしいことだ。
「白い目で見る」とは、「冷たい目つきで見ること」「冷たく扱うこと」といった意味で使用される故事成語で、「白眼視(はくがんし)」という場合もある。なぜ「冷たい目つき」のことを「白い目」と表現するのか。そのルーツは、本当に「白目」を剥いて相手を冷たく扱った、古代中国のある人物に求められる。
今からさかのぼること約1800年前、日本人にも人気の「三国志」の時代、「竹林の七賢(ちくりんのしちけん)」と総称される7人の知識人がいた。そのなかの1人、阮籍(げんせき)は礼儀作法や上下関係で社会と個人をとことん縛ろうとする儒家(じゅか)を毛嫌いするあまり、寝ているとき以外は酒と奇行と清談(高尚な談話)に明け暮れた。
特定の個人を批評することは極力避けながら、そこは奇行の常習者らしく、気に入った相手には普通に対応し、気に入らない相手に対しては“白目”で対応したと伝えられる。言葉で示すより強烈なインパクトを与えていたわけで、この故事から、「冷たい目つきで見ること」「冷たく扱うこと」を、「白い目で見る」「白眼視」という言葉で表現するようになった。
■“白目”だけじゃない阮籍の奇行
阮籍が生きたのは、「三国志」のなかでも、曹操(そうそう)に始まる魏(ぎ)の国で司馬一族の権勢が強まり、群臣の誰もが帝室の曹一族に忠節を貫くか、司馬一族に加担するか、去就を明らかにする覚悟を迫られつつあった時期だ。阮籍は奇行の持ち主だったが、当代一流の賢者には違いないので、司馬一族当主の司馬昭(しばしょう)は自己の陣営に引き入れるため、阮籍に縁談を持ちかけようとした。
政界での生き残りを優先させるなら素直に受け入れるしかないところ、司馬昭らのやり方が気に入らなかった阮籍は、司馬昭の前でひたすら酒を呑んで酔い続け、縁談の話を切り出す隙を与えなかった。そうして酔い続けること60日間、司馬昭もついに諦めたという。
幸か不幸か、阮籍は司馬一族による王朝簒奪(さんだつ)が完了する前夜にこの世を去った。あと数年長生きしていたら、粛清されていたか、粛清を免れても、朝廷からの追放は免れなかったはずだが、常人とは異なる価値観で生きていた阮籍には、痛くもかゆくもなかったかもしれない。
白目と酒で乱世を生き抜いた阮籍。いつかあなたが「白い目で見られる」身となったときには、 ぜひこの孤独な酒飲みのエピソードを思い出してみてほしい。