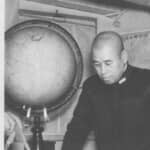日露戦争は何を理由に、どのように戦端が切られたのか?
今月の歴史人 Part.4
世界を驚かした日本軍の日露戦争での勝利。当時、劣勢とみられ、世界最強ともいわれたバルチック艦隊を有するロシアとの戦いは苦戦すると見られたものの、下馬評を覆して、日本軍は海戦史上類を見ない完全勝利となった。今回はこの日露戦争開戦のプロセスを追う!
■朝鮮半島の静謐を望む日本は満洲問題でロシアと国交断絶

秋山真之 日露戦争で連合艦隊作戦参謀として活躍。(国立国会図書館蔵)
明治33年(1900)8月、義和団(ぎわだん)の乱(日本では北清事変)は、日本を含む8カ国の連合軍により鎮圧された。各国が軍を引き揚げるなか、ロシア軍は満洲に居座ったうえ、朝鮮にも触手を伸ばしていた。
明治35年4月、ロシアは清国と協定を結び、満洲から3次にわたり撤兵する約束を交わした。第1次は実施されたが、翌36年4月予定の第2次は履行されなかった。
撤兵を要求する日本政府は粘り強 くロシア政府と交渉を重ねたが、折り合わず、暗礁に乗りあげた。
日露関係が緊迫の度を深めるなか、 12月28日、日本海軍は常備艦隊を解き、第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊に再編成。さらに第1、第2艦隊で連合艦隊を編成した(開戦後、第3艦隊が加わる)。
日本海軍は日清戦争後の軍備拡大により、戦艦6隻、巡洋艦6隻の「6・6艦隊」を実現。特に戦艦「三笠」 は、世界最強と謳われる新鋭艦だった。さらにアルゼンチンがイタリアに発注していた巡洋艦2隻(春日・ 日進)も購入した。

日露戦争で活躍した戦艦「三笠」 世界三大記念艦として今もその姿を残し、横須賀の三笠公園に東郷平八郎の銅像とともに展示されている。
明治37年1月6日午前9時、連合艦隊は佐世保(させぼ)港を進発した。この日、日本政府はロシア政府に国交断絶を通告。連合艦隊は時を置かずに、旅順のロシア太平洋艦隊を奇襲する作戦だった。
■瓜生少将の第2艦隊が仁川港外海戦で火蓋を切る
7日午後3時、瓜生外吉(うりゅうそときち)少将率いる第2艦隊第4戦隊は、旅順へ急行する本隊と分かれ仁川(じんせん)港へ向かった。巡洋艦5隻と水雷艇4隻を擁したのは、陸軍の先遣部隊約2000人が分乗した輸送船3隻を護衛する大任を帯びていたからである。
仁川港にはロシアの巡洋艦ワリャーグ(ワリヤーグ)、砲艦コレーツ(コレーエツ)、巡洋艦「千代田」など各国の軍艦が停泊していた。「千代田」は7日夜、ロシア軍艦の目を盗んで港外へと脱出し、8日朝、瓜生艦隊と合流した。
8日午後4時、港外に出てきたコレーツと瓜生艦隊が遭遇。午後4時40分、コレーツが先に砲撃(日本側の主張)したとも、水雷艇が先に魚雷攻撃した(ロシア側の主張)とも言われるが、この交戦で日露戦争の火蓋が切られた。
コレーツは港内に逃げ帰り、先遣部隊は夜を徹して上陸した。
9日午前11時30分、ワリャーグ、コレーツが港外に出てきた。砲撃戦が始まったが、圧倒的に有利な瓜生艦隊が2艦に損傷を与えた。ワリャーグは艦底弁を開いて自沈、コレーツは自爆、自沈した。
監修・文/松田十刻