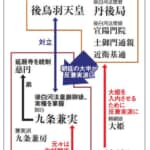大型巡洋艦の主砲を移管した戦艦「大和」の優秀な副砲
「戦艦大和」物語 第9回 ~世界最大戦艦の誕生から終焉まで~
戦艦「大和」には主砲以外に副砲と呼ばれるサブ的な攻撃力を備えていた。そのスペックを解き明かす。

戦艦「大和」の艦尾側の15.5cm3連装副砲砲塔。軽巡洋艦の主砲を利用したものがこの程度のサイズにしか見えないことから、大和がいかに巨大かということが理解できる。
戦艦「大和」は、世界最大の46cm主砲の他に、副砲として60口径15.5cm3連装砲塔を、2番主砲塔の後ろの艦橋前と、3番主砲塔の前の煙突寄りに各1基ずつ、さらに艦中央部の上部構造物側面の左右両舷に1基ずつ、計4基12門を装備していた。そのため、片舷(へんげん)に向けられるのは前後の2砲塔と、左右どちらかの1砲塔の合計9門となる。
この15.5cm砲の砲身は、最上型軽巡洋艦(比較的、小型の巡洋艦)が重巡洋艦(大型の巡洋艦)へと改装された際に、50口径20.3cm連装砲塔5基に換装されたため撤去されたものを流用。
ただし砲塔は、新造されたものだった。最大射程は27400mで、駆逐艦サイズの高速軍艦との近接戦闘を行う目的で搭載された。
しかし、航空機が海戦の主力的立場になってくると、左右両舷の1基ずつを撤去。大和では12.7cm連装高角砲6基に換装され、武蔵は高角砲の設置が間に合わなかったので、代わりに25mm3連装機銃6基が装備されたという。
とはいえ、この15.5cm砲は対空射撃も可能で、その際は零式通常弾と三式通常弾が使われた。ちなみにレイテ沖海戦では、大和が380発前後、武蔵が203発の対空射撃を副砲で行っている。
なお、対空射撃時の発射速度は、最上型時代の毎分5発から毎分7発に向上しているが、これは、大和型では揚弾機構が改善された結果であった。
このように、大和型の副砲は優秀な砲であったが、一方で、砲塔式の副砲を備える戦艦共通の懸念として、砲塔の装甲防御力の問題があげられる。
たとえば、敵戦艦の大口径砲弾が大落角で副砲砲塔の天井部に命中した場合、砲弾が貫徹して砲塔内部とその下の揚弾機構などを通過し、弾火薬庫に達して爆発するような事態に至れば、誘爆と火災により大きな損傷が生ずる恐れがあった。
もっとも、既述のごとくこれは大和型のみならず、副砲を砲塔式に装備したすべての戦艦が抱える弱点であり、解決策としては副砲砲塔天井部の装甲厚を増大させるしかない。
しかしその結果、砲塔そのものの重量が重くなると、砲塔旋回速度の低下などの悪影響が生じるため、対応が難しいところでもあった。