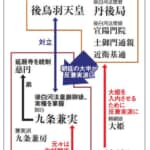アメリカに負けず戦艦「大和」も各種の最先端レーダーを積んでいた!
「戦艦大和」物語 第8回 ~世界最大戦艦の誕生から終焉まで~
戦艦「大和」には当時の最新技術であったレーダーが多数装備されていた。その役割とメカニズムをわかりやすく解説。

空母「瑞鶴(ずいかく)」の艦橋最上部に装備された2号1型電波探信儀。ベッドのスプリング状にも見える巨大な金網がアンテナである。実は大和は敵機の探知にレーダーを重用していたが、故障が少なくなかったのが泣き所であった。
一般論として、太平洋戦争中の日本は、電子技術でアメリカ、イギリスに遅れをとっていたとされる。
たしかに使用される真空管などの部品の品質や精度、また、技術面でも遅れていたのは事実だ。だが、実務をともなわない理論面では十分に世界水準にあった。
そのため、日本海軍でも「電波探信儀(でんぱたんしんぎ)」と呼ばれたレーダーが開発されており、すでに開戦直前の時点で実用の域に達していた。そして当然ながら、日本海軍が世界に誇る最新鋭巨大戦艦「大和」に、それが積まれていないわけはなかった。
最初に積まれたのは2号1型電波探信儀で、大和が装備したのは1942年夏であった。当初は実用試験を兼ねた仮の装備とされ、使用目的は捜索兼対水上射撃照準だったが、海面が起こす反射を強く拾ってしまうため、主に対空捜索監視に用いられた。
航空機は、編隊なら100km前後、単機なら70km前後の距離で探知できたため、十分に実用できるものだった。
ところが主砲の砲撃の衝撃で故障してしまうなどの初期トラブルが頻発。その解決に加えて、他にもいろいろと改良が施された。
その結果、対水上射撃照準もできるようになり、35000m前後で戦艦サイズの船を探知でき、15000m前後なら主砲弾による水柱も映るため、実戦での使用が可能となった。
2号2型電波探信儀は1843年夏に積まれたもので、主に対水上捜索用だった。戦艦サイズの船なら35000m前後、駆逐艦サイズの船なら15000m前後で探知でき、15000m前後で水柱も映る性能だったため、これも実戦で使用することができた。
その後、2号2型改3が積まれると、より精度が上がって光学測距儀を上回る精度を示したので、両者を併用した主砲射撃が行えた。
1号3型電波探信儀は1944年初期に積まれたもので、対空監視用だった。2基が装備され、編隊なら100 km前後、単機なら50 km前後で、3km前後の測距誤差で探知できた。
このように、大和は何種類ものレーダーを積んでおり、実戦でも、襲来する敵航空機の発見などに効果を発揮している。
つまり「日本海軍にはレーダーはなかった」という「風聞」は、技術面での遅れを極端に表現したものといえよう。とはいえ、やはりアメリカやイギリスには、性能面でも運用面でも追い付いていないという現実はあったのだが。