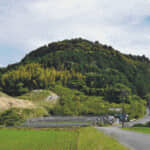村上義清 ー 信玄を2度破った男の生涯 ー
武田三代栄衰記⑯
謙信が「弓矢の父」と賞賛したほどの強さ

長野県埴科郡坂城町にある「村上義清公墓所(供養塔)」坂木の名家遺跡の亡失を憂い、江戸時代の初めに、越後高田藩の所領・坂木五千石の奉行となった長谷川安左衛門利次が建てた。
北信濃最大の強豪・村上義清(よしきよ)。その勢力は佐久郡・埴科(はにしな)郡・小県(ちいさがた)郡・水内(みのち)郡・高井郡ほか、信濃東部と北部に広がっていた。その要因はひとえに、越後の守護代・長尾為景(ながおためかげ)と1日に6回戦って勝ったと伝えられる彼の豪勇ぶりにあった(『村上家伝』)。
天文5年(1536)、東信濃の佐久郡・平賀(ひらが)城が甲斐の武田信虎(のぶとら)に攻め落とされる。このとき、信虎の子・信玄が義清に書状で外交交渉を行ったというが、史実ならこれが義清と信玄の初めての接触だろう。
これに対し、甲斐侵攻を図った義清が天文7年に甲斐の若神子(わかみこ)に砦を築かせたという記述が『信陽雑志(しんようざっし)』にある。若神子は佐久との通路を押さえる戦略的要地だから、武田氏を牽制するには良い場所だが、実行は難しい話だろう。だが、この当時、義清ら信濃の有力武将と武田氏との間が緊張状態にあったことは間違いない。
この緊張状態は2年後、信虎が娘の禰々姫(ねねひめ)を諏訪頼重(すわよりしげ)に嫁がせ、同盟を結んだことによって一旦解消された。信虎は、頼重、それに義清とも語らって翌天文10年に海野平(うんのたいら)に大軍をなだれこませる。海野平一帯は義清の統治下に入った。
義清の圧倒的な強さが海野平の戦いでも発揮されたこともあるだろうし、何よりも地政学的に海野平に一番近い位置にある義清が支配するのは当然でもあっただろうが、一方でこれは、義清にとって没落への道の選択でもあったかもしれない。
というのは、海野平への遠征にも関わらず寸土(すんど)も得ることができなかった武田家では、それを不満とする板垣信方(いたがきのぶかた)ら強硬派が信玄を担いでクーデターを起こし、信虎を駿河国へ追放してしまい、信濃侵略路線に舵を切ることになったからだ。
天文17年、南小県に侵攻して来た信玄を迎え撃った義清は、「上田原(うえだはら)の戦い」に臨む。
8000の敵に対し5000と、数では劣る義清だったが、信濃侵略の尖兵たる諏訪郡代・板垣信方ら圧倒的戦果を焦って猛進する敵を巧妙に誘い込んで包囲。不意を衝かれて混乱する武田軍に猛攻を加え、板垣信方・甘利虎泰(あまりとらやす)ら武田軍の有力部将を討ち取った。義清自身、武田軍本陣へ突入して信玄に負傷させたという。この経緯を聞いた上杉謙信は、義清の桁外れの強さに舌を巻いて「弓矢の父」と呼んだと伝わっている。
信玄が大敗北を喫した「戸石崩れ」とその後
2年後の天文19年、雪辱に燃える信玄は義清の支城・戸石(といし)城に攻め寄せた。この城は、義清にとって本拠地・葛尾(かつらお)城と上野国とを結ぶ流通ルートの中間に位置し、佐久郡を北上してくる武田軍を阻止する最後の砦といえる。7000の武田勢に対し城方は500に過ぎなかったが、天険(てんけん)を利用して急崖(きゅうがい)の上から石を投げ落とすなど巧みな戦術で甚大な損害を与え、横田高松(よこたたかとし)以下1000の武田軍を討ち取る大戦果をあげた。葛尾城からも義清が2000の兵を率いて後詰に駆けつけ、挟撃される形となった武田勢は動揺。追撃を受けて総崩れとなった。「戸石崩れ」と呼ばれる、信玄2度目の大敗だった。
こうして義清の武名は一層高まったが、翌年、信玄は真田幸隆(さなだゆきたか)に戸石城の内応工作を行わせ、あっさりと城を手に入れてしまう。抜群の勇猛さを誇る義清であっても、その配下は中世的な独立性の強い豪族連合の性格を持つ。家内の統制という面で義清の意識と力量に多くを期待するのは無理というものだろう。
信玄の政略によって抵抗の術を失い、天文22年、葛尾城を捨て越後へと落ちのびて行った義清は、その後、謙信の配下となり、生涯にわたって信玄と戦い続け死を迎える。
監修・文/橋場日月
(『歴史人』12月号「武田三代」より)