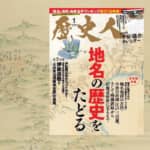江戸時代に由来する新宿・半蔵門・紀尾井町の地名
今月の歴史人 Part3
日本の首都・東京。その地名には全国的に有名なものも多い。そして、それらの地名の大半が江戸時代に名付けられたものだ。今では当たり前となった有名な地名は、どのような経緯で、どのように名付けられたのか? 今回は半蔵門・紀尾井町・新宿の地名の由来を解説する。
外堀沿いに流通拠点と武家地が並び甲州街道の起点へ至る
牛込・赤坂・四谷・新宿エリアも山の手に属し、武蔵野台地の一角を占めた。現在の行政単位では主に千代田区と新宿区となる。江戸城の西を守るように主に幕臣たちが集住したが、土地の起伏が激しいことを利用した配置でもあったのだ。守りやすく攻めにくい地勢が活用されている。
まずは現在の千代田区に相当するエリアから見ていこう。
.png)
九段江戸城田安門の近くの急坂に、人が往来するため9つの階を造ったのが「九段」の由来。勾配がきついため、武家屋敷を建てることはできなかった。現在は九段下駅が日本武道館の最寄駅となっている。(国立国会図書館蔵)

『江戸名所図会』に描かれた九段(国立国会図書館蔵)
千代田区の九段の地名は、その地に築かれた石の階段の数に由来する。幕府は江戸城四谷御門から神田方面に下る傾斜地に沿って石段を築いたが、土地の勾配がきつかったため、九段にも達し、傾斜地つまり坂道も九段坂と呼ばれるようになった。
.png)
半蔵門家康の「天正伊賀越え」にも同行したことで知られる服部半蔵の子孫が守りを担った半蔵門は、甲州街道の起点・新宿へと続く門。つまり、甲州方面から攻め来る敵への防衛の意味合いがあった。(国立国会図書館蔵)
半蔵門は江戸城の城門の名に由来するが、そもそも半蔵門の名は家康の家臣で槍の名手として知られた服部半蔵に求められる。この門外に半蔵の配下が組屋敷を与えられたことで、門の名前も半蔵門になり、ひいては地名となった。ただし、半蔵門は町名とはならず、半蔵門(駅)界隈の呼称にとどまっている。
紀尾井町は明治に入ってから生まれた町名だが、起源をさかのぼると江戸時代に行き着く。紀州徳川家の上屋敷、尾張徳川家の中屋敷、井伊家の中屋敷が接するエリアであったため、そこにあった坂は三家から一字を取り紀尾井坂と名付けられた。江戸時代には武家屋敷街には町名が付けられなかったが、明治に三家の屋敷も政府に取り上げられると、坂名にちなんで紀尾井町と命名された。
.png)
赤坂赤坂見附駅、市谷見附交差点などにその名を留める 「見附」は、城門の見張り番所のこと。江戸城には36の門があり、うち赤坂・市谷のほか四谷・小石川などに見附の名が付く。(国立国会図書館蔵)

『名所江戸百景』に描かれた赤坂(国立国会図書館蔵)
四谷見附や赤坂見附など、地名にとどまらず駅名にもなっている見附は見張りの番兵を置いた軍事施設のことで、江戸城外堀に置かれた城門に併設させる形で配置された。こうして、半蔵門と同じく、その界隈を示す呼称にもなっている。
.png)
牛込そもそもは牛を飼育する牧場があったことに由来するが、明暦の大火以降、運河による物流を促進するため、牛込御門近くの外堀に揚場河岸(船荷を陸揚げする場所)が築かれる。その結果、流通の拠点としても発展する。(国立国会図書館蔵)

『江戸名所図会』に描かれた牛込(国立国会図書館蔵)
牛込は武蔵野台地の東端に位置し、神楽坂に象徴されるように坂が多いエリアである。かつて多くの牛が飼育された牧場があったことに由来する。中世では牛込を苗字とする牛込氏の所領だったが、江戸時代に入ると起伏のある地勢を活用する形で幕臣たちの屋敷が立ち並んだ。さらに、戸城外堀の造成工事に伴い麹町などから多くの寺院が移転してくるが、寺も江戸防備に活用しようという意図が秘められていた。
-300x210.png)
新宿甲州街道の最初の宿場町。高遠藩内藤家の屋敷があったことから内藤新宿と呼ばれ、現在もこの地に「内藤町」の地名が残る。玉川上水の水番所があった四谷大木戸もここにあった。(国立国会図書館蔵)
新宿は名前の通り新しい宿場町のこと。誕生したのは江戸中期の元禄年間だ。江戸と甲斐国を結ぶ甲州街道の最初の宿場は高井戸宿だが、日本橋から16㎞以上もあり旅人には難儀な道中となっていた。そこで、中地点に新たな宿場・内藤新宿が創設された。高遠藩内藤家の屋敷に面していたことで、内藤新宿と命名されたが、いつしか簡略化されて新宿と呼ばれるようになる。
監修・文/安藤優一郎