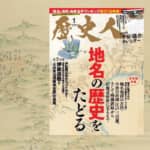江戸時代に由来する音羽・駿河台・水道橋の地名
今月の歴史人 Part2
現在の首都・東京の地名は全国的にも有名なものが多くある。それらの地名の大半が江戸時代に名付けられている。ここでは現在、当たり前のようにある有名な地名はどのような経緯で、どのように名付けられたのか?に迫る。約1400万人が暮らす東京。知らずに呼んでいた地名にも、深い歴史があったのだ。今回は音羽・駿河台・水道橋の地名の由来を解説する。
高台に幕臣が集住した由緒ある武家地
神田・駿河台・小日向・音羽エリアは下町に対して、「山の手」と呼ばれた地域だ。現在の行政単位では千代田・文京区となる。高台とでも呼べるような台地だが、江戸城の北を守るため主に幕臣が集住した。千代田区に該当する地域からみていこう。

駿河台。眺望が良く富士山を一望できた。徳川家康の出身地・駿府(駿河)にちなんだ地名という説が有力。(国立国会図書館蔵)
駿河台の北には神田川が流れていたため、当初は神田山と呼ばれた丘陵だったが、江戸開府後に全国から集められた人夫により切り崩され、その土をもって江戸城の南に広がっていた日比谷入江が埋め立てられる。切り崩されて生まれた駿河台の地名の由来には諸説あり、家康が駿府で死去した後、駿府から移ってきた家康付の旗本(駿河衆)が住んだ台地、あるいは駿河国の富士山を遠望できた台地などがある。

神田猿楽町。猿楽は、古くから公家・武家の保護を受けており、江戸幕府も式楽(儀式用の公式芸能)として採用した。その演者である猿楽師(左)が集住した地が猿楽町。現在も住民から伝統的な地名として支持されている。(国立国会図書館蔵)
神田猿楽町は旗本などの武家屋敷が集中する地帯で、江戸時代には町名は付けられていなかったが、猿楽のうち観阿弥・世阿弥の流れを受け継ぐ観世座の家元・観世太夫とその一座の人々が拝領した屋敷があった。つまり、猿楽師の拝領屋敷があったことで猿楽町と俗称されるようになったが、正式に町名となったのは明治に入ってからである。

水道橋。東京ドームの最寄駅・水道橋駅にその名を留めている。この橋は神田上水の懸かけ樋ひ(水路)で、中を水が通っていた。上の絵では見えないが、水質管理を担う見守番屋があった。(国立国会図書館蔵)
駅名にもなっている水道橋は、神田上水の水を運ぶ樋といが神田川に架けられたことが名前の由来だ。要するに、水を運ぶための橋つまり水路橋になっているとして水道橋と呼ばれた。現在の水道橋から100mほど下流に架かっていたとされるが、いつしか、この橋の辺りも橋名にちなんで水道橋と呼ばれるようになった。
現在の文京区小石川は武蔵野台地の一角を占める台地(小石川台)だが、その地名は小石が多い小川が幾筋も流れていたことに由来する。漢語風に礫川の呼称もあった。水戸徳川家や譜代大名、幕臣団の屋敷も集中するエリアだった。

小日向。地名の由来は武蔵江戸氏の庶流・小日向氏と関連付ける説がある。明暦期から市街地化が始まった。神田上水が通り、上水端にあった道祖神の祠ほこらが右の絵。神田上水の廃止とともにこの祠も姿を消した。(国立国会図書館蔵)
小日向は小石川の東に位置する台地(小日向台)で、南は神田川に面している。かつては鶴高日向という人物の領地だったが、鶴高家の断絶後、日向にちなんで小日向と呼ばれるようになったという。戦国時代には小日向を苗字とする武将もいた。家康が江戸城に入った時は沼や池も多かったが、その後の埋め立てで土地が整備され、小石川と同じく武家屋敷が立ち並ぶようになる。

音羽。護国寺は、5代将軍綱吉の生母・桂昌院が創建した寺院。桂昌院から信任が厚かった音羽という奥女中に、この門前町が与えられている。現在は閑静な住宅街であり、文京区音羽の町名としても知られる。
音羽は関口台と小日向台に挟まれた台地だ。地名は5代将軍・綱吉の母・桂昌院が音羽の地に創建した護国寺に由来する。護国寺門前が京都の音羽山清水寺門前のように賑わうことを願い、桂昌院が音羽と名付けた説。門前に江戸城大奥に勤める奥女中の音羽が拝領した土地があったことから名づけられた説がある。
監修・文/安藤優一郎