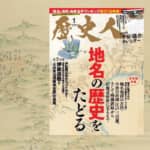「北海道」「青森」の地名にまつわる由来と歴史
今月の歴史人 Part3
日本各地の地名は、長い歴史を経て付けられたものが大半を占める。地形や災害、合戦など地名の数だけ歴史があると言っても過言ではない。今回は北海道と青森の地名について、その由来を解説していく。

雪化粧に包まれた北海道の十勝岳。十勝岳は美瑛町・上富良野町、十勝管内の新得町にまたがる。
【北海道】
北海道(ほっかいどう)⇒「海=加伊」はアイヌの国を指す
蝦夷地(えぞち)・アイヌ研究の先駆者として活躍した探検家の松浦武四郎(まつうらたけしろう)が、 明治2年(1869)、道名に関する意見書を政府に提出(日高見道・北加伊道・海北道・海島道・東北道・千島道の6つが候補)。松浦はアイヌ民族が自らの国を「カイ」と呼んでいたことから「北加伊道」を勧め、政府は「加伊」を「海」とし、「北海道」と命名した。
長万部(おしゃまんべ)⇒シャマンベ=鰈(かれい)のこと
アイヌ語で「オ(河口)シャマンベ(鰈)」→「鰈がたくさん漁れる河口」。また、春に写万部山(しゃまんべやま)の山腹に見られる残雪「ウパシ・シャマンベ(雪の鰈)」が訛ったという説もある。
札幌(さっぽろ)⇒乾いた大きな川
アイヌ語で「サッ・ポロ」で、「サッ」は「乾いた」、「ポロ」は「大きい」の意味。かつては「サッ・ポロ・ナ イ」(乾いた大きな川)と呼んでおり、その川は豊平川のことである。
知床(しれとこ)⇒大地の果て「最後の秘境」
オホーツク海に長く突き出した半島で、ユネスコ世界自然遺産に登録されている。アイヌ語の「シリエトク」に由来するとされ、「大地の頭の突端」「大地の行きづまり」という意味。
銭函(ぜにばこ)⇒銭函を積むほどの豊漁
由来はアイヌ語ではなく、アイヌの人々が住む時代から鮭漁の場として栄え、各戸で銭函を積むほどニシンの豊漁にも恵まれたことから、そのものズバリの地名となった。
富良野(ふらの)⇒十勝岳が地名に影響を与える
由来はアイヌ語の「フラ・ヌ・イ」で、「臭気を持つもの(川)」という意味。十勝岳から流れる富良野川に、硫黄が溶けているところからついた地名とされている。
【青森県】
青森(あおもり)⇒青々とした松の丘が由来
古くから「青森」と呼ばれる、松に覆われた小高い丘が沿岸部にあったことが由来とされる。県名成立の背景には、現在の青森県に領地を持っていた弘前(ひろさき)藩(津軽藩)と盛岡藩(南部藩)の長年の対立があり、両者の関係を少しでも修復するため、弘前ではなく、盛岡に近い「青森」に県庁所在地を置いたこととされる。
浅虫(あさむし)⇒「麻を蒸した」から「浅虫」に
由来は、かつてこの地の温泉で「麻を蒸した」のが定説。里中に煮え返る温泉があり、ここで麻を蒸すことを麻蒸といったが、蒸が火災を連想させるとして改称された。
五所川原(ごしょがわら)⇒岩木川の屈曲により誕生
『平山日記』によると、寛文年間に岩木川が屈曲したことで5つの村ができたことに由来。古くは御所川原と表記されたことから天皇にちなむという伝承も残っている。
龍飛(たっぴ)⇒アイヌ語で「刀の上端」
アイヌ語の「タム・パ」(刀の上端)に由来するというのが通説で、津軽半島自体が刀のような形をしており、その先端にあることでその名称がついた。納得できる説である。
野辺地(のへじ)⇒アイヌ語の「野中を流れる川」が由来
一見珍しい地名だが、その由来はアイヌ語の「ヌップペッ」からきていると言われる。「ヌップ」は「野」を意味し、「ペッ」は「川」を意味する。
八甲田(はっこうだ)⇒山々の姿にちなんだ地名
8つの山々の間にたくさんの湿地が点在しているというのが定説。また、8本の指を立てているように見えるので「八(甲)田」としたという説もある。
弘前(ひろさき)⇒2代藩主・津軽信枚(のぶひら)が改名
『和漢三才図会』によれば、古くは「広崎」と表記され、その後、高岡と呼ばれたが、2代藩主・津軽信枚が「弘前」と改名。命名は信枚が帰依(きえ)していた天海僧正によるものとされる。
監修/谷川彰英