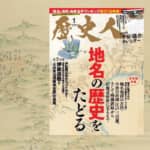「群馬」「栃木」「埼玉」の地名にまつわる由来と歴史
今月の歴史人 Part7
今回は、群馬・栃木・埼玉の3県に存在する地名について、その由来を解説。地形にちなんだ地名はもちろん、古代の伝承が入り混じったユニークな地名も散見される。

群馬県前橋市、桐生市などにまたがる赤城山の山頂にある小沼。5月下旬から6月下旬には、さまざまなツツジが満開となり美しい景観を楽しめる。
【群馬県】
群馬(ぐんま)⇒車から群馬に改められた
かつては「くるは」と読まれた「車」が「群馬」に転訛(てんか)。上毛野君豊城入彦命(かみつけのきみとよきいりひこのみこと)の後裔にあたる射狭君(いさのきみ)が、雄略(ゆうりゃく)天皇の御世に乗輿(じょうよ)を供進して姓を賜(たまわ)った「車持公」(くるまもちのきみ)氏に由来するとされる。
吾妻(あがつま)⇒亡き妻を偲(しの)び、嘆いた
古代より「吾妻郡」として知られる。『日本書紀』によると東征の後、都に戻ろうとした日本武尊(やまとたけるのみこと)が、この地で亡き妻の弟橘媛(おとたちばなひめ)を偲び「吾嬬はや」と3度嘆いたとされる。
草津(くさつ)⇒「くさい水」の意
「草津温泉」で全国的に有名。由来は、硫化水素が強い臭いを発することから、「くさい水」の意味で「くさみず」「くそうず」と呼んだことによるとされる。
高崎(たかさき)⇒「成功高大」の意
井伊直政が当地を「松ヶ崎」に改めようとした際、住職白庵から「成功高大」の意味をとって「高崎」を勧められ命名。また城地を定める際に、鷹を飛ばしたからという説も存在する。
前橋(まえばし)⇒「厩橋」(うまやばし)と呼ばれていた
「前にある橋」という意味ではなく、古くは戦国期から「厩橋」であった。厩は馬小屋のことだが宿駅の意味もある。「前橋」に変わったのは慶応年間とされる。
【栃木県】
栃木(とちぎ)⇒語源に諸説あり
地名の語源には、トチノキが茂っていたことが転訛した説、神明宮という神社の社殿の屋根の千木が10本に見えたことから「十千木」と呼ぶようになった説、また千切れた(侵食された)地形の「チギる」に接頭語の「ト」がついた説など、様々存在する。
宇都宮(うつのみや)⇒「一宮」転訛説が有力
宇都宮市の中心地に鎮座する二荒山(ふたあらやま)神社に由来。日光から「移し祀った」から、「討つの宮」「内宮」などの説もあるが、「一宮」が転訛したという説が一番信憑性が高い。
鬼怒川(きぬがわ)⇒「鬼怒川」表記は明治以降
河川の名はこの一帯がもともと「毛野国」(けぬのくに)であり、そこを流れる大河であっ たことから「毛野河」と 呼ばれていたことに由来。江戸時代には「衣川」「絹川」とも表記された。
益子(ましこ)⇒益子城を築いた豪族
かつて、この地に勢力を張った豪族「益子氏」が由来。源頼朝が奥州藤原氏討伐の軍を挙げた際に戦功を挙げ、源氏の旗である白旗一流を下賜されたという逸話がある。
真岡(もおか)⇒鶴は今日も「舞ふか」
古代中世に「真岡」という地名は存在せず、天正年間に改称したとされる。この地に集まっ た鶴が今日も「舞ふか」と人々が言っていたなど、由来には諸説あり。
【埼玉県】
埼玉(さいたま)⇒神社名が県名のルーツ
現在の行田(ぎょうだ)市に、「埼玉」という地名があり、埼玉の地名発祥の地とされる。ここには9基の大型古墳が群集する埼玉古墳群、またその一角には「前玉神社」があり、これが県名のルーツと言われている。
朝霞(あさか)⇒皇族の名にちなみ命名
かつては「膝折村」(ひざおりむら)と呼ばれたが、昭和7年(1932)、この地に移転した東京ゴルフ倶楽部の名誉総裁であり皇族でもあった朝香宮鳩彦王(あさかのみややすひこおう)にちなんで「朝霞」と命名した。
浦和(うらわ)⇒太古の昔は海だった
縄文時代には現在よりも海岸線が深く内陸に入り込んでいたことから、海の入り江を指す「浦」が使われた。日光御成街道の裏道・中山道に面した「裏の集落」が由来の説も。
川越(かわごえ)⇒入間川を「越える」
由来は、入間川を越えていくところから「川越」となったとされるが、「越」は「渡し」の意味もあったとも言われる。古くは「河越」「河肥」とも書かれた。
蕨(わらび)⇒「蕨」=「藁火」が有力
沖積低湿地帯で樹木不足のため、藁で煮炊きや暖をとったことによるとされる。源義経が「藁火村」と名づけた説や在原業平(ありわらのなりひら)が藁をたいてもてなしを受けた「藁火」が由来とも。
監修/谷川彰英