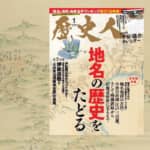「山形」「福島」の地名にまつわる由来と歴史
今月の歴史人 Part6
日本には、個性あふれる多種多様な地名が存在する。その背景にある、長い歴史を紐解くことによって各都道府県の特色も学ぶことができる。今回は、山形・福島の2県にある地名について、その由来を解説していく。

山形・蔵王エコーラインの紅葉。蔵王連峰を東西に横断する山岳観光道路、蔵王エコーラインにはカエデ類、ブナ、ナラなど赤、黄色を基調に色づいた木々が並び、主に9月下旬から10月中旬にかけて楽しめる。
【山形県】
山形(やまがた)⇒山の方にある土地が起源か
古代の出羽国最上郡、現在の山形市の南にあたる上山市付近を「山方郷」といったことに由来するとされている。南北朝時代に、斯波兼頼(しばかねより)がこの地に政治拠点を置いた際に「山形」という地名が史料に登場する。これは野方や里方に対して、蔵王周辺の山のあたりの土地を「山方」としたためと考えられる。
余目(あまるめ)⇒「余部」が転訛したもの
大化の改新で戸籍法が敷かれ、「戸(こ・へ)」という組織が誕生。戸が5つで「保」、保が 10個で「里(り・さと)」とし、10を超える端数を「余部(転訛して余目)」と呼んだ。
月山(がっさん)⇒山容から命名される
出羽三山(羽黒山、湯殿山、月山)の中で最も標高が高い(1984m)。半月上の山容(山の姿)から名づけられたとされるが、「犂牛山」(くろうしやま)とも呼ばれ、牛が寝ているような山容によるとも言われている。
白鷹(しらたか)⇒上杉鷹山(ようざん)の由来にも関係
地名の由来は、町の北東にそびえるように見えることにあるといわれる。また、江戸時代中期の名君として知られる上杉鷹山の号は「白鷹山」に由来する。
鶴岡(つるおか)⇒「鶴ケ岡城」が地名の由来
かつて鎌倉幕府の御家人・武藤氏が大宝寺城を築き、権勢を振るった。その後、関ヶ原の戦いで功績のあった最上義光(よしあき)の領地となり、「鶴ケ岡城」に改称されたことが「鶴岡」のルーツである。
天童(てんどう)⇒北畠天童丸にちなんだ地名
南北朝期にこの地を治めた国司・北畠顕家(きたばたけあきいえ)の孫・北畠天童丸が当地の山城に拠(よ)ったことにちなむ。舞鶴山の山頂で念仏を唱えると、2人の童子が舞い降りてきた伝説が由来とも言われている。
【福島県】
福島(ふくしま)⇒湿地帯「フケ」を縁起の良い「福」に
会津藩の発展に貢献した蒲生氏郷(がもううじさと)の客将である木村吉清は文禄元年(1592)、信夫郡(現在の福島市)の5万石を与えられる。この際の居城「杉妻城」を「福島城」に改めたことが由来とされる。湿地帯を意味する「フケ」が由来という説もあるが、「フケ島」を縁起のよい「福島」に変えたのであろう。
会津(あいづ)⇒将軍たちがこの地で遭遇
崇神天皇の時代に、北陸地方平定のために下向した大毘古命(おおびこのみこと)と東海道を経て派遣された建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと)の親子が、この地で出会ったことが由来とされる。「相津」から「会津」へ転訛している。
喜多方(きたかた)⇒会津地方の「北の方」
古くから、会津地方の北の方を「北方」と呼んでいたことが由来とされる。現在の「喜多方」に変わったのは明治8年(1875)で「喜びが多い」という意味で名づけられたという。
郡山(こおりやま)⇒郡衙(ぐんが)が置かれた場所の意
律令時代の国郡里制に基づき、役所「郡衙」が置かれた場所につけられる地名が「郡」で、全国に多数存在する。郡山の場合は、陸奥国安積郡に郡衙が置かれたことから命名された。
勿来(なこそ)⇒「来てはいけない」が語源
奥羽三関のひとつ「勿来(なこそ)の関」に由来する。語源は「な来そ(来てはいけない)」で、「さえぎる」を意味する「関」と同意語となることから、「関」の枕詞としても広く用いられた。
二本松(にほんまつ)⇒二本の松があったから
二本松城は奥州探題畠山氏の7代畠山満泰(はたけやまみつやす)が築いた城である。当時、この城の本丸に二本の霊松があったことから二本松城と呼ばれ、畠山氏も二本松畠山氏と呼ばれたという。
坂下(ばんげ)⇒明確な「崖」の地名
現在の「会津坂下町」。アイヌ語説や坂下にあたるからという説もあるが、ここは明確に「ハケ」「ハゲ」「ボッケ」などの「崖」地名であるといってよいだろう。江戸時代には越後街道の宿場として栄えた。
監修/谷川彰英