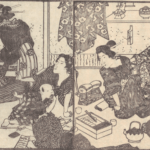吉原の遊郭よりも手軽に”遊女遊び”ができた【湯女・飯盛女】とは?
いま「学び直し」たい歴史
江戸時代の男たちの遊び場として有名なのは江戸の「吉原」や京の「島原」だろう。だがいわゆる遊郭の遊女たちと遊ぶには高額なお金がかかり、庶民たちには簡単に手が届くものではなかった。遊郭の女ではなく、巷でも遊べる遊女が存在した。こうした遊女たちは宿場や風呂場などにおり、お手ごろな価格で遊ぶことができたという。([『歴史人』電子版] 大人の歴史学び直しシリーズvol.4 「江戸の遊郭」より)
ソープランド化した風呂屋や体も売った宿場の女中がいた
手軽な女遊びを求めて男たちは江戸四宿を目指した

上野で花見をする遊女たち江戸時代の遊女たちはマイナスなイメージはなく、華やかで江戸っ子たちの憧れの存在であった。歌川広重『東都上野花見之図』(国立国会図書館蔵)
天正18年(1590)に徳川家康(とくがわいえやす)が入府し、江戸の建設が始まると、建設景気に沸く江戸に仕事を求めて若い労働力がどっと流入してきた。
このため、江戸時代の初期には江戸の人口は女にくらべて圧倒的に男が多かった。
その結果、結婚できない男が多数存在した。こうした男たちを目当てに江戸の各地に女郎屋(じょろうや)(遊女屋、妓楼、娼家)が乱立したが、そんななかでひときわ人気が高かったのが湯女である。
天正19年(1591)、伊勢与市(いせのよいち)という男が銭瓶(ぜにがめ)橋のあたりで湯屋を始めた。当時の湯屋は蒸し風呂である。その後、湯屋が林立し、湯女と呼ばれる女を置くようになった。15文か20文を払えば、湯女が客の垢すりや洗髪をしてくれたし、『慶長見聞集』によると、
「湯よ茶よと云ひて持来りたはむれ、うき世がたりをなす」
で、男の相手もするようになった。形態としては現在のソープランドに似ている。江戸で最初の人気風俗店はソープランドだったことになろうか。
ところが、吉原(元吉原)ができるにともない、湯女をはじめ各地の女郎屋は禁止された。なお、銭瓶橋は現在の千代田区丸の内1丁目あたりに架かっていた橋である。

『江戸高名会亭尽 深川八幡前』
江戸時代の料亭や旅籠屋に遊女はつきもので、夜な夜な男たちは遊行したという。(国立国会図書館蔵)
いっぽう、宿場の旅籠屋(はたごや)は飯盛女(宿場女郎)と呼ぶ遊女を置くことを幕府の道中奉行から許されていた。江戸時代も中期以降になると、庶民の生活水準が向上して伊勢参りなどの旅行が盛んになったが、泊まった旅籠屋で遊女と遊興するのが旅の男たちの大きな楽しみだった。
品川(東海道)、内藤新宿(甲州街道)、千住(日光・奥州街道)、板橋(中山道)の江戸四宿は宿場であり、厳密には江戸ではない。しかし、江戸市中から近かったので、江戸四宿は江戸の男にとって手
軽な遊里だった。
つまり、宿場の旅籠屋には純然たる旅人も泊まるが、遊女が目的で遊びにくる男もいたことになる。
遊女の揚代(あげだい)(料金)は昼間は600文(約9000円)、夜は400文(約6000円)が主流だった。もちろんこれは時間制で、泊まる場合はもっと高くなった。
品川は500人、内藤新宿、千住、板橋はそれぞれ150人まで遊女を置くことを許可されていたが、実際には倍以上の女がいるのは常識だった。
とくに品川は繁栄し、なにかにつけて吉原と比較対照されるほどだった。江戸後期の天保15年(弘化元年、1844)1月、関東取締出役(八州廻)が調査したところ、遊女を置いた旅籠屋は94軒におよび、定員500のはずの遊女の数は合わせて1348人にのぼった。定員の2・5倍以上である。
品川の遊びのガイドブック『品川細見』(嘉永5年)によると、揚代銀10匁(約1万7000円)の高級遊女が53人、金2朱(約1万2500円)が41人いた。そのほか600文、500文、400文の遊女もいた。こうした揚代の多種多様さが品川人気の理由のひとつであろう。
品川の 客にんべんの あるとなし
という川柳がある。にんべん(人偏)があるのは「侍」、にんべんがないのは「寺」で、つまり武士と僧侶が常連客だった。もちろん、町人の客も多い。
遊里品川にはあらゆる身分・職業の男、金のある者も、ない者もこぞって遊びにやってきた。
監修・文/永井義男
[『歴史人』電子版]
歴史人 大人の歴史学び直しシリーズvol.4
永井義男著 「江戸の遊郭」
現代でも地名として残る吉原を中心に、江戸時代の性風俗を紹介。町のラブホテルとして機能した「出合茶屋」や、非合法の風俗として人気を集めた「岡場所」などを現代に換算した料金相場とともに解説する。