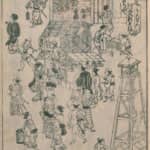江戸時代の風俗は街中でも“品定め”ができた!?
全国津々浦々 遊郭巡り─東西南北で男たちを魅了した女たち─第6回(静岡・安倍川町/あべかわまち 後編)
遊女という仕事の歴史は長く、江戸時代より昔、戦国時代にも存在していた。また江戸などの主要都市だけでなく、各地の宿場を中心に、遊女たちは全国に存在したという。ここでは武田信玄や徳川家康のゆかりのある地、駿河の安倍川という町に存在した遊郭について紹介する。
宿をとっても遊郭で遊んで朝帰り⁉

図3『白浪日記』(東里山人著、文政5年) 国会図書館蔵
吉原の妓楼は、通りに面して、張見世(はりみせ)と呼ばれる、格子張りの座敷をもうけていた。
遊女は張見世に居並んで座る。客の男は格子越しに遊女を見立て、相手を決めた。
図3は、吉原の妓楼(ぎろう)の張見世の様子である。
図4は安倍川町の妓楼だが、張見世は吉原とほぼ同様だった。

図4『栗毛弥次馬』(十返舎一九著、文久元年) 国会図書館蔵
さて、『東海道中膝栗毛』では、弥次郎兵衛と喜多八は張見世で相手を決め――
連れ立ちて、暖簾のうちへ入ると、若い者、
「これは、よく、おいでなさいました。まず、上へ」
と、二階へ案内する。ふたりは見立てた女郎を注文すると、すぐにその部屋へ連れて行く。
――という具合だった。
そのまま妓楼に泊まった弥次郎兵衛と喜多八は、翌朝早く、旅籠屋(はたごや)に戻り、そこで朝食となる。その後、ふたりは府中を出立した。
旅籠屋に宿泊しながら、弥次郎兵衛と喜多八が実際に寝たのは妓楼だったことになろう。
こういう男は珍しくなかったのか、ふたりが旅籠屋に朝帰りをしても、とくに苦情を言われた様子はない。
『色道大鏡』(畠山箕山著)の、「駿河国府中」の項に――
府中の遊女は、昔より有りけり。中頃、宮城野といひし者、其頃世に隠れなかりき、
――とあり、かつて府中の遊廓に、宮城野という全盛の遊女がいた。
同書によると、宮城野は富裕な男に身請けされ、幸せに暮らしていた。ところが、永禄十一年(1568)、武田信玄が府中に侵攻した戦乱で、宮城野は非業の死を遂げたという。
なんと、全盛の遊女宮城野は、武田信玄と同時代だった。このことからも、府中の遊廓の歴史の古さがわかろう。
絵師の司馬江漢(しばこうかん)が長崎に旅した時の紀行『西遊日記』に、天明八年(1788)六月三日、知人に案内されて府中の二丁町に行ったと記し――
見世コーシ、吉原の趣きなり。……(中略)……爰に泊りてよく朝帰る。
――とあり、張見世の格子は吉原を思わせた。江漢と知人は妓楼に泊り、朝帰りをした。
戯作者・文人の滝沢馬琴は享和二年(1802)、上方に旅をしたが、その時の紀行『羇旅漫録』に、「駿府二丁街」として――
駿河府中の妓院は二丁町とよびなす。本名は安倍川町なり。神祖御在城の日、免許の遊女町なり。
――と記している。
神祖、つまり徳川家康が駿府城にいたころに公認された遊廓だ、と。
妓院は遊廓のこと。
ただし、馬琴は続けて、妓楼は狭くてむさくるしいし、遊女が駿河訛りで吉原言葉を使うのはちゃんちゃらおかしいと酷評している。
馬琴の目には、しょせん田舎遊廓に見えたのだろうか。
『全国遊廓案内』(日本遊覧社、昭和5年)は、「静岡市安倍川遊廓」について――
静岡市は元駿府と云って、徳川家康の隠居地であった。……(中略)……この方面も殷盛を極めたもので、最も盛大の時は妓楼四十五軒を数えたこともあった。明治初年の火災以後はようやく衰えたりといえども、今なお十三軒の妓楼があり、娼妓百九十人を数えている。
――と記している。
江戸時代には及ばないものの、昭和初期にも繫栄していた。
なお、娼妓は娼婦(遊女)のこと。同書は、娼妓は尾張、美濃、伊勢地方の出身が多いと述べている。
また、料金は、「お定り」という標準的な遊び方で、泊りが、
甲 6円50銭
乙 4円50銭
丙 3円90銭
だった。
標準コースにもランクがあったのがわかる。
ちなみに、昭和四年(1929)の、実用的な自転車の平均小売価格は四十五~七十円だった。
[『歴史人』電子版]
歴史人 大人の歴史学び直しシリーズvol.4
永井義男著 「江戸の遊郭」
現代でも地名として残る吉原を中心に、江戸時代の性風俗を紹介。町のラブホテルとして機能した「出合茶屋」や、非合法の風俗として人気を集めた「岡場所」などを現代に換算した料金相場とともに解説する。