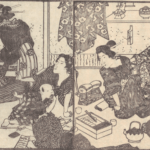片道3kmもかけて男たちが通った遊郭【静岡・安倍川町】
全国津々浦々 遊郭巡り─東西南北で男たちを魅了した女たち─第5回(静岡・安倍川町/あべかわまち 前編)
江戸時代の遊郭は、江戸の「吉原」だけではなく全国各地に存在していた。その中でも駿河に位置した安倍川遊郭は評判が高く、多くの快楽を江戸時代の男たちに与えていたという。江戸の吉原以上に満足でき、宿から約3kmも離れていたにもかかわらず、男たちが通ってしまった「安倍川」遊郭をここでは紹介する。
安倍川町の遊女は江戸の吉原の遊女と遜色ない

図1『東海道五拾三次 府中』(一立斎広重、喜鶴堂版、天保年間) 国会図書館蔵
安倍川町(阿部川町とも書いた)は、駿河(するが/静岡県中央部)の府中(静岡市葵区)にあった遊廓である。
府中は江戸時代、東海道の大きな宿場だった。同時に、安倍川町遊廓があることでも有名だった。
安倍川町遊廓は、俗に二丁町(にちょうまち)と呼ばれた。大門を入ってから奥行が二丁(約218メートル)あったから、広さが二丁四方だったから、などの説がある。
図1に、安倍川町遊廓が描かれているが、画中に「二丁町廓之図」とある。
つまり、府中にあった遊廓は、安倍川町とも二丁町とも呼ばれた。
東海道を行く旅人は、宿場である府中の旅籠屋(はたごや)に泊まった。そして旅装を解いて身軽になるや、やおら安倍川町に出かける。
ただし、安倍川町は府中の旅籠屋街からは二十四~五丁(約2.7キロ)も離れていたため、駕籠や馬で通う男も多かった。
図2に、馬の背に揺られてやってきた男が描かれている。

図2『五十三次』(広重、嘉永年間) 国会図書館蔵
戯作『東海道中膝栗毛』(十返舎一九著、文化6年)では、弥次郎兵衛と喜多八は府中の旅籠屋にあがったあと――
なんでもこれより、かねて聞き及びし安倍川町へしけこまんと、喜多八もろとも、その支度をして、宿の亭主を招き、
弥次「もし、ご亭主、わっちらあ、これから、二丁町とやらへ見物に行きてえものだが、どっちのほうだね」
亭主「安倍川のほうでございます」
弥次「遠いかね」
亭主「ここから二十四、五丁ばかしもあります。なんなら、馬でも雇ってあげましょうか」
喜多「こいつはいい」
弥次「から尻に乗って女郎買いも面白い、面白い」
――というわけで、馬方に引かれた馬に乗って、ふたりは安倍川町に出かける。
なお、から尻(軽尻)は、街道で、荷なしの馬に旅人が乗ること。
馬で安倍川町にやってきた弥次郎兵衛と喜多八は、大門の外で馬をおり、遊廓に足を踏み入れた。そのにぎわいは――
両側に軒を並べて、弾きたつる清掻(すががき)の音にぎわしく、店つきのおもむきは、東都の吉原町におおよそ似たり。
――で、にぎわいも、妓楼の店構えも、江戸の吉原に匹敵するほどだった。
「清掻」は、三味線で弾くお囃子(おはやし)のこと。
春本『旅枕五十三次』(恋川笑山、嘉永年間)は、阿部川町について――
揚代、金壱分と弐朱あり。すべてのこと、吉原の模様にほぼ変わらず、宿々の飯盛とはまた格別にて、見識もありて、廓の作法も正しく、遊女もみなおとなしき風にて、客を大切に手当てよく、宵に一番、夜中に一番、明け方に一番と、三番くらいはお定まりのようにさせる所なり。
――と評し、絶賛している。
宿場の飯盛女と呼ばれる遊女とは大違いで、安倍川町の遊女は、江戸の吉原の遊女と遜色ない、と。
しかも、ひと晩に三回くらいは普通にさせるという。ただし、これは春本特有の誇張かもしれない。
また、揚代は一分と二朱の区別があった。
嘉永年間の両替の相場で、金一分は千六百文、金二朱は八百文くらいである。当時、東海道の宿場の飯盛女の揚代は五百文前後だったから、やはり遊廓の遊女は値段が高かった。
記録によると、遊女の数は、
元禄五年(1692) 六十人
嘉永三年(1850) 百四十三人
である。
(続く)
[『歴史人』電子版]
歴史人 大人の歴史学び直しシリーズvol.4
永井義男著 「江戸の遊郭」
現代でも地名として残る吉原を中心に、江戸時代の性風俗を紹介。町のラブホテルとして機能した「出合茶屋」や、非合法の風俗として人気を集めた「岡場所」などを現代に換算した料金相場とともに解説する。