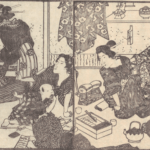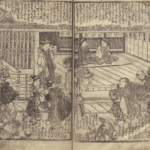維新の志士や貿易商が稼いだお金を使い果たすほど男を虜にした【長崎・丸山遊郭】
全国津々浦々 遊郭巡り─東西南北で男たちを魅了した女たち─第1回(長崎・丸山 前編)
西でも東でも男たちを魅了した花街の歴史を探訪─
古今東西、花街は男たちの心をつかんで離さなかった。女性たちの魅力に溺れ、夜を楽しむ遊郭は、どれだけ歴史を変えても、そのにぎわいがやむことはない。もちろん、全国各地に遊ぶ場所は存在し、名称やしきたりは違えど、遊女たちが集まる場所には、男たちも集まり、一つの歴史と文化を作り上げた。そんな全国各地にあった遊郭の歴史を本連載では紹介。第一回となる今回は、海外との交易でにぎわい、商人たちが全国から集まった長崎・丸山に存在した遊郭の様子を解説する。
坂本龍馬をはじめ、維新志士たちも通った長崎の遊郭

図1『肥前崎陽玉浦風景之図』(貞秀、元治2年) 国会図書館蔵
丸山は、長崎市にあった遊廓で、図1に、その全容が描かれている。
ただし、描かれた元治二年(1865)はすでに幕末である。図1は、坂本龍馬が遊んだころの丸山と思ってよかろう。
江戸時代初期の寛永十九年(1642)、それまで市中に散在していた妓楼(ぎろう)を丸山の地に集めて、丸山町と改称した。さらに、妓楼が多かった寄合町が隣接地に移転してきた。
こうして、丸山町と寄合町を合わせた地域が、丸山遊廓と呼ばれるようになった。
『諸国色里案内』(空色軒一夢著、貞享5年)に、「長崎丸山之事」として――
ここのおこりは、筑前の博多より、わずかに移り来たりしよりこのかた、百年ばかりにもならんか。いにしえの女郎町は古町といえる所なり。その後、古町を今の丸山に移し給いぬ。そのほか、長崎の町々に忍びの抱え女を、ここへ一緒に集め給いて、今の寄合町、これなり。
――とあり、博多から来た遊女や、長崎各地にいた遊女を集めて、丸山遊廓が形成されたのがわかる。
『長崎土産』(延宝9年)によると、
妓楼 三十軒
遊女三百三十五人(太夫/たゆう 六十九人)
である。
高級遊女である太夫が六十九人もいることから、遊廓としての繁栄がわかろう。

図2『長崎土産』(延宝9年) 国会図書館蔵
図2は、延宝九年(1681)頃の丸山の遊女の姿である。右に立っているのは、清(中国)人。長崎ならではの光景といえようか。この点は、後述する。
戯作『好色一代男』(井原西鶴著、天和2年)では、主人公の世之介が丸山で遊んだのはもう晩年の、五十九歳の時だった――
入口の桜町を見渡せば、はや面白うなってきて、宿に足も止めず、すぐに丸山に行きて見るに、女郎屋の有様、聞き及びしよりはまさりて、一軒に八、九十人も見せかけ姿、
――とあり、桜町は長崎の目抜き通りである。
つまり世之介は長崎に到着するや、気もそぞろになり、すぐに丸山に足を運んだ。そして、妓楼や遊女の繁盛の様子は、想像以上だったようだ。
一軒の妓楼に、八~九十人も遊女がいた。

図3『好色一代男』(井原西鶴著、貞享元年) 国会図書館蔵
図3は、世之介がながめた遊女の姿。
戯作『日本永代蔵』(井原西鶴著、貞享5年)は、長崎には上方の豪商が有能な手代などを派遣し、海外との取引で巨利を得ていると記したあと――
長崎に丸山という所なくば、上方の金銀帰宅すべし。
――と慨嘆(がいたん)している。
せっかく長崎で儲けた金を、上方の本店に送らず、丸山遊廓で使い果たしている手代がいたのだ。丸山がなければ、上方の本店にもっと送金されただろうに、と。
戯作『けいせい色三味線』(江島其磧著、元禄14年)は、丸山遊廓を丸山町と寄合町に分け、妓楼や遊女の名を紹介している。
最高位の太夫と、その下の天神がいて、揚代も異なっていた。揚代は銀である。
太夫 六十三人 三十匁
天神 十六人 二十匁
合わせて七十九人だが、これ以外に下級の遊女がたくさんいた。おそらく五百人を超えていたろう。

図4『金草鞋』(十返舎一九著、文化10年)、国会図書館蔵
図4は、丸山の遊興の様子である。
当時、料理は銘々に膳で出すのが普通だった。食卓に料理が並んでいるのが、いかにも長崎らしい。
料理は卓袱(しっぽく)料理だろうか。
(続く)
[『歴史人』電子版]
歴史人 大人の歴史学び直しシリーズvol.4
永井義男著 「江戸の遊郭」
現代でも地名として残る吉原を中心に、江戸時代の性風俗を紹介。町のラブホテルとして機能した「出合茶屋」や、非合法の風俗として人気を集めた「岡場所」などを現代に換算した料金相場とともに解説する。