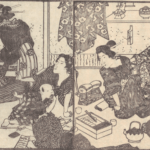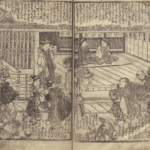お金をもらって触る、揉む…「三助」はなぜ、裸の女性を相手に仕事ができたのか?
転職してみたい江戸のお仕事 第1回 「三助」
客の体を叩く“仕上げの音”で腕の良し悪しがわかる

背中や肩、腕など自分では洗いにくい部分を丹念に磨き上げてくれた後、簡単なマッサージが付いて4文だった。湯屋に勤める者の多くは越後や越中などの出身で、お金をためて湯屋の経営者になることを夢見て真面目に働いていたという。イラスト/志水則友
裸の女性を触りまくった上にお金がもらえて感謝されることもあるという、大抵の男性が「うらやましい」と思える仕事がかつてあった。
この仕事がなぜ生まれたかということを説明するには、湯屋(ゆや)と呼ばれていた銭湯の歴史を紐とかなければならない。天正19年(1591)江戸で初めてできた銭湯は、今のように広い湯舟はなく、密閉した室内に湯気を充満させたところに客が入る。湯気で皮膚が柔らかくなり垢が浮いてきたところを搔き落とした後、ぬるま湯や水で洗い流すという今のサウナのようなものであった。
垢を搔き落とすといっても背中は自分では難しい。そこで、これを専門に行う人が現われた。湯女(ゆな)と呼ばれる女性である。背中を流し、髪を洗い、茶を入れてくれるなどして客とたわむれたという。どうたわむれたかは具体的なことが資料に書いていないのだが、公認されている遊郭・吉原の客を奪ってしまうほどの人気だったということからご想像いただきたい。こうした湯女を置いた湯屋は湯女湯屋と呼ばれ、江戸城外堀を取り巻く形で200軒以上あったが、明暦3年(1657)に禁止されてしまった。
湯屋では湯女は禁止されたが、客からは以前と同様の垢すりサービスを求められる。だが、女性を使うわけにはいかないので、湯を汲んだり釜を炊いたりする下働きの男性にさせるようになった。
3人の湯女から3人の男性に代わったので、「三助」と呼ばれるようになったという説があるが、本当のところは背中を流す人のなかに三助という人がいて、他の人も「三助」と呼ばれるようになったのではないだろうか。
そう、冒頭に書いたうらやましい人の正体は湯屋で客の求めに応じて背中を流した「三助」。1回4文で自分では洗うことが難しい背中をプロの技術で磨きあげてくれる。男性が女湯に入って問題がないのかというと、寛政3年(1791)に風紀が乱れるのでよろしくないと禁止されるまで、江戸の湯屋はほとんどが混浴だった。禁止はされてもなかなか徹底されなかったそうで、幕末に江戸を訪れた外国人が混浴に驚いたそうだが、江戸の人たちは気にしていなかったという。
三助の仕事ぶりだが、残念ながら当時のことは詳しくわかっていない。そこで、昭和の三助の仕事ぶりを紹介しよう。
前述したとおり、客の背中を流すだけが銭湯の仕事ではない。銭湯に就職するとまずリヤカーで薪を材木屋や家屋の解体現場などから集めて回る薪集めの下働きを数年した後、お湯を沸かす釜番に昇格。釜番はお湯の温度を管理するという重要な役目で、客の数によってくべる薪の量を調整する。この釜番になると客の背中を流すことができるようになった。
客は番台で料金を払い木札を貰う。同時に番台では控え室にいる三助に拍子木(ひょうしぎ)などで合図をする。合図を聞いた三助は木札を持った客のところに行き、背中を洗いマッサージを施す。この間約10分。他の客がいない時には長めにしてくれたそうだ。仕上げに客の体をパンパンと銭湯中に響きわたるような大きさで叩く音で、三助の腕のよしあしが分かったという。
江戸時代から続いた三助という仕事であったが、内風呂の普及などにより銭湯自体が町からなくなってしまい、三助も平成の終わりごろに姿を消した。