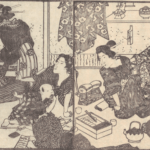横浜にあった遊廓・港崎は庶民だけでなく武士までもが憧れた【横浜・港崎遊郭】
全国津々浦々 遊郭巡り─東西南北で男たちを魅了した女たち─第4回(横浜・港崎/みよざき 後編)
江戸時代の遊郭といえば、華やかで男たちが集まった魅惑の場所であり、「吉原」をイメージする人も多い。しかし、花街と呼ばれる街は全国各地に存在。今や未来的な建物が立ち並ぶ横浜にも「港崎」という遊郭があったという。本記事では、この町に残された花街の逸話を紹介する。
異人との情交を拒んだ大和撫子の逸話

図5『横浜港崎廊岩亀楼異人遊興之図』(一川芳員、文久元年) 国会図書館蔵
横浜の開港と遊廓について、哀話がある。
岩亀楼(がんきろう)の遊女喜遊(きゆう)は楼主からアメリカ人の客を取るよう迫られても、異人に肌を許すのを拒み続け、ついには、
露をだにいとう大和の女郎花ふるあめりかに袖は濡らさじ
という辞世の歌を残し、懐剣(かいけん)で喉を衝いて自害したという。
遊女でさえ大和なでしこの操を守ったというこの哀話は、小説や芝居にもなって有名だが、まったくのフィクションであり、史実ではない。
港崎のガイドブックともいうべき『港崎細見』を見ても、岩亀楼に喜遊という遊女はいない。
さて、遊女が異人を敬遠したと先述したが、これは初めのうちだけだった。やがて、遊女は異人を歓迎するようになった。
その理由は、なんといっても異人の客は気前がよかったからである。
当時の通貨の関係から異人、とくに欧米人には日本の物価も人件費も格安に感じられた。そのため、妓楼でも散財したのである。
図5は、岩亀楼で異人客がどんちゃん騒ぎを演じているところである。まさに、豪遊していた。

図6『横浜文庫』(橋本玉蘭斎編、慶応元年) 国会図書館蔵
図6は、画中に「本町南横通り異人港崎皈り」とあり、馬車に乗った異人は港崎から帰るところである。
港崎に馬車で乗りつけたことになろうか。
紀州藩の下級藩士である酒井伴四郎は万延元年(1860)、江戸勤番を命じられた。伴四郎は江戸に着くと、赤坂にある紀州藩の中屋敷内の長屋に住んだ。
同年の十月二十七日、伴四郎は藩士ら合わせて五人で、横浜見物に出かけた。前年、横浜が開港し、話題の観光地になっていたのだ。
半四郎の日記(『酒井伴四郎日記』として知られる)によると、次の通りである。
八ツ半(午前三時頃)に起床し、支度をして屋敷を出発。一行は東海道を進む。
鈴ヶ森で夜が明け、六郷の渡しで渡し舟に乗り、六郷川(多摩川)を越えた。
川崎宿(神奈川県川崎市)で小休止したあと、ふたたび歩いて、四ツ半(午前十一時頃)に神奈川宿に着き、昼食。
埋め立てが進んだ現在では想像もできないが、当時、神奈川宿は海に面していた。
神奈川宿の渡船場から渡し舟に乗り、横浜の渡船場で下船。
伴四郎ら五人は、呉服・両替商の三井(越後屋)の横浜支店に行き、紹介状を見せた。紀州藩は三井にとって得意先だったのだ。
三井の番頭の案内で、伴四郎らは異人館を見物して回った。
その後、最も楽しみにしていた港崎に向かう。
港崎で、三井の番頭が言った。
「これが有名な岩亀楼でございますが、妓楼の中を見学し、料理と酒を味わうこともできます。ご案内しましょうか」
もちろん、三井の接待である。
喜んで岩亀楼にあがった伴四郎らは、建物の造りや調度の豪華さに、まさに度肝を抜かれた。見学後は、座敷で酒と料理を楽しんだ。
港崎を出たあと、三井で馳走を受け、渡し舟で神奈川宿に戻る。その夜は、旅籠屋に泊まった。
この伴四郎の体験からも、庶民だけでなく、武士までもが横浜と港崎遊廓にあこがれていたことがわかろう。
『幕末明治女百話』は、港崎の終わりについて――
慶応二年十月二十日の朝、辰の中刻(午前八時)土堤道の豚切売業鉄五郎方から、火事を出したのが、風が強く、夜の八時まで焼けて、関内をおおよそ焼払い、さしもの岩亀楼、神風楼、金石楼、岩里楼その他ことごとく焼けてしまったのは、惜しいものでした。この火事を、「豚屋火事」といって、横浜では名代の火事なんです。
――と述べている。
港崎の終焉はあっけなかった。
港崎は慶応二年(1866)の豚屋火事で全焼し、その後は再建されることはなかった。遊廓はほかに移り、跡地は公園となったのである。
港崎遊廓の繁栄はおよそ七年間に過ぎなかった。幕末に咲いたあだ花と言おうか。
[『歴史人』電子版]
歴史人 大人の歴史学び直しシリーズvol.4
永井義男著 「江戸の遊郭」
現代でも地名として残る吉原を中心に、江戸時代の性風俗を紹介。町のラブホテルとして機能した「出合茶屋」や、非合法の風俗として人気を集めた「岡場所」などを現代に換算した料金相場とともに解説する。