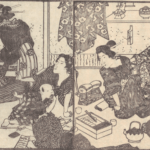横浜の東京オリンピック会場は江戸時代、花街だった⁉ 異人たちを魅了した「港崎」遊郭【横浜・港崎遊郭】
全国津々浦々 遊郭巡り─東西南北で男たちを魅了した女たち─第3回(横浜・港崎/みよざき 前編)
西でも東でも男たちを魅了した花街の歴史を探訪─
古来から男たちは花街の女たち女性たちの魅力に溺れ、名称やしきたりは違えど、遊女たちが集まる場所には、男たちも集まり、一つの歴史と文化を作り上げた。現在、日本有数の港町として栄える横浜にも、かつては花街が存在し、華やいだ。その遊郭は、幕末にやってきた異人たちのためのものであったという。「港崎(みよざき)」と呼ばれた遊郭の歴史をここでは紹介する。
みなとみらいのど真ん中に存在した「異国人向け」の遊郭

図1『東海道名所之内横浜風景』(五雲亭貞秀、万延元年) 国会図書館蔵
港崎は、神奈川県横浜市にあった遊廓である。
場所は、プロ野球の球場がある横浜公園。本年の東京オリンピックの会場ともなる場所である。かつて、ここに港崎遊廓があった。
安政五年(1858)に調印された日米修好通商条約にともない、翌安政六年に横浜が開港することが決まった。
横浜が開港すれば、異人(外国人)がどっと来航するのが予想された。また、横浜には居留地もでき、異人の定住も始まる。
こうした事態に直面して、幕府はあわてて遊廓の設置を決めた。
遊廓建設を請け負ったのは、品川宿の飯盛旅籠(めしもりはたご)屋(女郎屋)の主人・佐吉である。
大岡川支流東岸の湿地を埋め立てて、一万四千坪の敷地を造成した。そして、安政六年(1859)の末から、遊廓としての本格的な営業を開始した。
なお、この功績により、佐吉は港崎の名主に任じられた。
幕府の意向を受け、遊廓の仕組みは吉原遊廓、異人客の扱いは丸山遊廓のオランダ人対応にならうとした。
図1から、港崎の敷地が堀で完全に囲まれているのがわかろう。吉原がお歯黒どぶという堀に囲まれているのと同じだった。

図2『横浜名所一覧』(五雲亭貞秀、万延元年) 国会図書館蔵
図2からも、港崎が堀に囲まれているのがわかる。
当初、異人と肌を合わせるのを恐れ、あるいは嫌い、肝心の遊女が集まらなかった。
そこで、東海道の宿場である神奈川宿(横浜市神奈川区)の飯盛女(遊女)をなかば強制的に移転させて、ようやく開業に踏み切った。
ところで、幕府は当初、異人が日本人と交流するのを極力阻止するため、港崎についても、丸山がオランダ人に対しておこなっていたデリバリー(出前)方式を適用しようとした。
ところが、開国にともない横浜では、すでに異人は市内を歩く自由を認められていた。長崎のオランダ人のように出島に押し込められているわけではない。
異人は横浜の町を闊歩し、港崎にも足を踏み入れた。もう、なし崩しであり、もはや丸山方式は通用しなかった。
港崎で最大の規模を誇ったのが、岩亀楼(がんきろう)である。楼主は佐吉。

図3『横浜岩亀楼之図』(二代目広近) 国会図書館蔵

図4『横浜岩亀楼之図』(二代目広近) 国会図書館蔵
図3に岩亀楼の外観、図4に内部が描かれている。
当時としては珍しい和洋折衷の建物は人々を驚かせ、見物に来る人は引きも切らなかった。
『幕末明治女百話』(篠崎紘造著、昭和7年)に、岩亀楼についての聞き書きがあり――
横浜の岩亀楼というものは、どなたも御存じの遊女屋で、家の中に、日光の朱塗の橋が拵えてあって、有名なもので、異人さんが珍しがって、よく遊びに参ったものです。見物料を取って、見物させたといいますが、ソノ見物料が、一人分二朱と五分ですから、十七銭五厘でした。一両出せば、同楼一番の大広間の「扇の間」というへ通して、立派な茶菓が出たんですが、横浜見物で、岩亀楼を観なくっては、見物甲斐がないといいました。
……(中略)……
この岩亀楼の娼妓は、たいてい西洋人の相手が多く、その向きの内意も含んでいましたが、岩亀楼に出向かれない、身分のある異人のためには、同楼から娼妓を、異人館へ駕籠で送り込んだもので、ソレは毎晩のように御用があったんですから、吉原では「男の朝帰り」が目に立ちますが、横浜ではアベコベに、異人館から「娼妓の朝帰り」があったんです。
――と、遊女のデリバリーもあったが、丸山とは意味合いが違っていた。
また、岩亀楼では見物だけの客もあげていたのがわかる。
それにしても、楼内を見学し、扇の間で茶と菓子のもてなしを受けるだけで一両とは、かなり高額である。
(続く)
[『歴史人』電子版]
歴史人 大人の歴史学び直しシリーズvol.4
永井義男著 「江戸の遊郭」
現代でも地名として残る吉原を中心に、江戸時代の性風俗を紹介。町のラブホテルとして機能した「出合茶屋」や、非合法の風俗として人気を集めた「岡場所」などを現代に換算した料金相場とともに解説する。