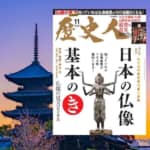日本の仏像の起源をたどる ─ガンダーラから中国・朝鮮半島をめぐる歴史─
今月の歴史人 Part2
仏像は1世紀ごろに釈迦の姿を表して、パキスタンやインドで造られるようになったのがはじまりである。その後、中央アジアからシルクロード経由で伝わった仏教美術、日本の仏像の原点となった「中国・朝鮮半島」の仏像は今や日本各地で確認できる。その歴史と広がりを明らかにする。
皇帝が仏教を保護し 仙人と釈迦が同一視される

如来三尊仏龕石造 703年 像高/中尊36.5㎝
左脇侍50.6㎝ 右脇侍51.0㎝
中国・陝西省西安宝慶寺
唐の女帝則天武后が造営した、光宅寺の七宝台(高層の楼閣)の内壁を飾っていた浮彫りの石仏。インド・グプタ朝 美術の影響を受けており、衣のヒダや ポージングが写実的に表現されている。

古代中国・朝鮮半島の仏像の歴史
ガンダーラで生まれ、シルクロードを渡った仏像はやがて中国にたどり着き、中国から朝鮮、そして日本へと伝播することになる。中国から日本へ、どのような経緯で仏教、仏像が伝わってきたのか。まずは中国での広がり方を見ていきたい。
古代中国の人々が仏教に触れたのは、仏像が誕生するよりも前、紀元前のことだった。西域から訪れた仏僧や商人によって仏教が広まったのである。この時代、仏は「浮図」と呼ばれ、寺院や仏像も造られ始めるが、造られる仏像はまだ南?中央アジアの影響を大きく受けたものが多かったようだ。何より当時の中国人は仏像を異国の神の像と見ていたらしく、副葬品の銅鏡に墓を守る神として釈迦の姿を彫りこむこともあった。釈迦・仏は神仙の一人として人々に受け入れられていく。
やがて北方遊牧民族が中国を支配する五胡十六国時代になると、皇帝が仏教を保護。これにより、民衆の間に仏教が浸透し、同時に信仰の拠り所である伽藍や仏像も多く造られるようになった。初期の像はガンダーラ仏の雰囲気を残していたが、時が経つごとに杏仁形と呼ばれる切れ長の瞳に微笑を浮かべる口元など、独特の表情へと変化していく。
そして五胡十六国時代の次の時代、南北朝時代でも南・北ともに仏教は 大いに栄えた。しかしその反動か、 北朝では二度にわたる廃仏運動が勃 発。北朝の仏教は壊滅的な被害を受けてしまう。これを受けて北朝の皇帝は仏教復興に乗り出した。追善供養のため、洞窟に仏像を彫る石窟寺院造りを命じたのである。
大規模な石窟寺院の建造で 多くの仏像が造られる
世界遺産としても名高い中国三大石窟寺院の敦煌、雲岡、龍門のうち、洛陽の「龍門石窟」は南北朝時代から唐まで400年近くかけて完成したという途方も無い石窟寺院で、10万を超える石仏群が安置されている。中でも、賓陽洞の釈迦如来坐像は6世紀中国の北魏様式の特徴を色濃く残す作品として著名で、洞窟のやや奥まった場所にあるため彩色が綺麗 に残っている。本像は、日本仏像史最初期の作例である法隆寺金堂釈迦三尊像とよく比較され、面長な輪郭やアルカイックスマイルなど共通点が多々見受けられる。
「雲岡石窟」は断崖に彫られた石窟寺院だ。東西1kmの洞窟の中に5万体を超える石仏が刻まれるなど、南北朝時代から始まったこれら石窟寺 院は当時の仏像を今に残す貴重な存在である。
やがて時が経ち隋・唐の時代へと突入する。安定した政権が続いたことで世情は落ち着き、平和な日常の中で様々な文化が花開いた時代でもある。皇帝も仏教を推奨したことで、金銅仏が多く生み出された。皇帝の庇護のもとで造像の技術も伸び、唐 代にはまさに仏像の成熟期を迎えた。
中国で仏教が隆盛し始めた4世紀以降、その情報は朝鮮半島にまで伝わった。この時代、朝鮮は高句麗、百済、新羅が覇権を争う三国時代だ ったが、各国とも中国の影響を受け仏像造りが始まる。朝鮮半島の仏像 は優しく丸みを帯びた顔立ちで、口元に微笑みを浮かべるなど中国仏像の流れを汲むものが多い。また、中国で5世紀に多く造像された半跏思惟像も三国で流行を見せた。下ろした片足の上にもう片方の足を載せ、 前傾姿勢で思惟する仏像であり、特 に韓国の「国宝 号・半跏思惟像」がよく知られている。またこの像は、「国宝 号・菩薩半跏像」と並んで未だに謎を多く残す京都広隆寺の半跏思惟像「宝冠弥勒」との共通点が多く見られることでも有名だ。そして6世紀頃、百済より日本に仏教が伝来。仏教だけではなく、仏像造りとその技術も日本に伝わることになる。仏像はインドからシルクロード、中国と長い旅をしてようやく日本へ到達するのである。
監修/岩崎和子、文/野中直美