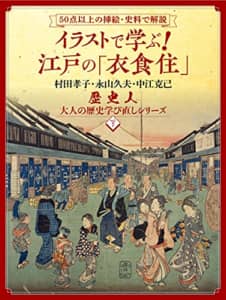江戸庶民が”ご近所付き合い”を大切にした理由
いま「学び直し」たい歴史
プライベートが重視される現代では、かなり薄れつつある“ご近所付き合い”。江戸時代の長屋暮らしにおいては、この”ご近所付き合い”は欠かせないものであり、とくに大家さんとの関係性は生活を左右する重要な要素だった。(歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」より)
火事を想定して作られた隣人関係や家賃、大家との間柄

花見でにぎわう江戸時代の上野・不忍の池 江戸時代から桜の名所として知られた上野公園周辺。上野の花見は江戸っ子たちの年に一度の楽しみとして、武家の人々から江戸庶民まで身分を問わず、楽しまれた。(『名所江戸百景 上野清水堂不忍ノ池』国立国会図書館蔵)
江戸庶民の多くはその日暮らしだったが、それでもちょっとしたひまを見つけて、梅や桜などの花どきを楽しんだ。桜の季節には弁当をつくり、隅田川や飛鳥山へ花見に出かけた。いまでも人気がある亀戸天神(江東区亀戸)へ藤の花を見にいく。上野の不忍池(上野公園)は蓮の花見 で早朝から賑わったし、名物の蓮の葉飯を食べるのが楽しみ、という人が少なくなかった。
しかし裏長屋で楽しく過ごすには、大家とのつきあいをうまくやることだった。大家というのは通称で、ほかに家守(やもり)とも称したが、正式には家主(いえぬし)という。
「大家といえば親も同然、店子[たなこ](借家人)といえば子も同然」
俗にそのようにいわれた大家だが、なにかと頼りになる存在だった。いま大家といえば、賃家の持主を指すが、江戸では管理人のこと。持主は地主といい、表店の経営者とか職人の棟梁(とうりょう)が多かった。

江戸の長屋暮らしの様子左手に井戸、ゴミ溜めなどの共有スペース、右手奥に 長持ち、長屋内で戯れる仲間がいる。お隣との境界が この長屋では障子になっている。(『道中膝栗毛』/国立国会図書館蔵)
投資として賃家経営をしていたが、 住人たちとはじかにかかわらない。しかし、消防や水道、祭礼など、高額な分担金を引き受けていた。大家はその地主に雇われて長屋を管理した。
まず店子と長屋の賃借手続をするほか店賃を集めて地主に納める、というのが大きな仕事だった。
ほかには店子たちの婚姻や出産、死亡などの届け出。隠居、勘当、離婚というのもある。関所手形(身元 証明書)の申請など、さまざまな公用を担当していた。

蚊帳蚊帳は麻などで作り、虫は通さず風は通す1ミリほどの網目 になっていた。夏の夜、蚊帳に入るときは蚊帳の裾をつま み上げ、蚊を追いやりながら、子供を抱え速やかに入る。(『浮世風俗やまと錦絵』錦絵初期時代 上巻蚊帳橋口五葉 編/国立国会図書館蔵)
監修・文/中江克己
歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7
「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」
世界に冠たる100 万人都市「江戸」。町の住む半数以上は町人であり、質素な長屋暮らしのなかでも衣食住に工夫をこらし、生き生きと生活していた。ファッション、美容、食、住居などには江戸ならではの文化が花開き天下泰平の大都市であった。意外と知られていない「江戸っ子」たちの生活の実態には、改めて教訓とすべきライフスタイルが詰まっている。
Amazon / Apple Books / 楽天Kobo