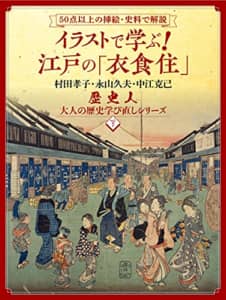江戸であまりに人気で高値となり、幕府に販売を制限された食べ物とは⁉
いま「学び直し」たい歴史
江戸時代、庶民たちの間で「初物を食べると長生きする」という風習が流行した(江戸の食に学ぶ「長寿法」参照)。世界一といわれるまでに成長し、人口が増えた江戸の長生きにはこうした風潮が一因にあったのかもしれない。ただ「初物」のなかでも絶大な人気を誇った、あるものは人気が出すぎて、値段が高騰、販売が制限されるまでになったというから驚きだ。(歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」より)
江戸で大人気となった「旬なものを食べる」初物長寿法
値段が高騰するあまり、幕府は売り出しを制限

右下に初鰹売りが描かれた江戸の絵。鮮度を保つため、大急ぎで売り歩いたという。この姿も初夏の風物詩だったのかもしれない。(『東都歳事記』「初夏交加図」/国立国会図書館蔵)
江戸っ子が、初物の中でもっとも熱中したのが初がつお。女房の晴着や蚊帳まで質に入れてでも初がつおを買うという、負けずぎらいの江戸っ子だから、値段なんか見ないで入手しようとする。走りのかつおはべらぼうな高値がついた。

『守貞謾稿』江戸時代の三都(江戸・京都・大阪)の風俗や事情を解説した百科事典。初物に関する記述も見られ、初物を食することに対する当時の盛り上がりを読み取ることができる。(国立国会図書館蔵)
『守貞漫稿』によれば「初て来るかつお1尾2、3両に至る」とある。1本のかつおが2両も3両もしたというのである。現在の金にすると1両は8万円位に相当するから、3両というと、何と24万円也だ。異常というか、バカバカしい高値としか言いようがない。
したがって、初がつおを腹の中へ納めてから大変だった。初がつおと苦戦した、江戸っ子たちの川柳である。
○初鰹銭とからしで2度なみだ
○初鰹薬のように盛りさばき
○女郎よりまた鰹かと女房言ひ
○春の末銭へ芥子(からし)をつけて食い
「銭」は初カツオが高価なことを示す。芥子は薬味である。
かつおばかりでなくなす・きゅうりなども同じで、あまりの初物フィーバーに寛保2年(1742)に幕府は売出しに制限をつけた。「ますは正月より、あゆ、かつおは4月、さけは9月、あんこうは11 月、白魚は12月より」。しかし、あまり守られなかった。
監修・文/永山久夫
歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7
「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」
世界に冠たる100 万人都市「江戸」。町の住む半数以上は町人であり、質素な長屋暮らしのなかでも衣食住に工夫をこらし、生き生きと生活していた。ファッション、美容、食、住居などには江戸ならではの文化が花開き天下泰平の大都市であった。意外と知られていない「江戸っ子」たちの生活の実態には、改めて教訓とすべきライフスタイルが詰まっている。
Amazon / Apple Books / 楽天Kobo