江戸のファッションリーダーは遊女⁉ 独自の工夫で楽しんだ女性の衣服事情
いま「学び直し」たい歴史
階級や身分によって派手な着物を統制されていた江戸時代。江戸の女性たちは地味に控えながらも、自分なりの工夫であか抜けた色や柄を着こなし、お洒落を楽しんでいた。身分などで慣習がある中、流行や文化を育んだ江戸の女性たちの装い事情を紹介。(歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」より)
遊女や歌舞伎役者たちが江戸の粋なモードをリードした
江戸女たちのファッション事情

庶民奢侈(しゃし)禁止令により派手な着物が禁じられたが、茶屋娘から火がついた前垂れなどでお洒落を楽しんでいた。(歌川豊国「江戸名所百人美女 浅草寺」国立国会図書館蔵)

武家武家の女性は、もともと大奥でも身分の高い女性の着用する打うち掛かけを羽織り、格式の高さを示した。(『千代田の大奥』国立国会図書館蔵)

遊女江戸のファッションリーダーだった吉原の遊女は、輸入物など贅の限りを尽くした一級品をまとっていた。(歌川国貞「吉原高名三福対」/国立国会図書館蔵)
江戸時代の化粧、髪型、衣装などのファッションをリードしたのが、遊女や歌舞伎役者といわれている。なかでも有名なのが、承応から明暦頃(1652~1658)に登場した遊女勝山で、もとは賎(いや)しからぬ身分だったといわれている。
神田の堀丹後守の屋敷前にあった紀伊国屋風呂の湯女となり、のちに吉原に移り太夫(たゆう)となった。美人でその上、伊達な異風を好み、髪型も下げ髪を曲げて輪とした屋敷風に結い上げた姿は評判となり、道中姿を一目見ようと道の両側にたくさんの人たちが並んだという。多くの女性たちが、その髪型を真似たことは、その後に書かれた肉筆浮世絵の女性たちを見ても分かる。
勝山のことは、井原西鶴(さいかく)も『好色一代男』巻一で「抑(そもそも)丹前風と申(もうす)は、江戸にて丹後殿前に風呂ありし時、勝山といへるおんなすぐれて情もふかく、髪かたちとりなり袖口廣(ひろ)くつま高く…」と紹介している。
江戸時代末期の弘化4年(1847)に山東京伝の弟の岩瀬百樹(ももき)(山東京山)が書いた「歴世女装考』という本にも、勝山髷のこと、さらに巡礼姿の勝山が描かれている。勝山髷は、川柳の『柳多留(やなぎだる)』にも「いい女郎世上の髪に名をのこし」と詠まれている。時代がたつにつれ、少しずつ髷の形が横に大きくなっていったが、長く愛された髪型でもあった。
歌舞伎役者のなかで、江戸時代中期に登場して、江戸時代末期まで影響を与えたファッションリーダーといえるのが、王子路考(おうじろこう)とも呼ばれた二世瀬川菊之丞(きくのじょう)であろう。容顔美麗なことでも評判は高かったが、路考結び、路考茶、路考染め、路考櫛、路考髷など、常に工夫し色々な流行を編み出したことでも知られている。
路考結びは、これも八百屋お七の中でお七を演じていたとき、帯の結び目が解けてしまい、結びなおす暇がなかったので、とっさに解けた帯を挟みいれて芝居をしたという。その形は、8年以上たった文化10年(1813)の『都風俗化粧伝』に形は変化しつつも紹介されている。
監修・文/村田孝子
歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7
「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」
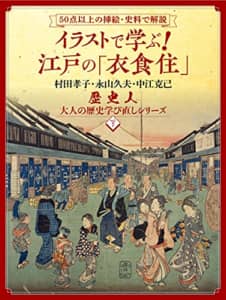
大人の歴史学び直しシリーズvol.7
世界に冠たる100 万人都市「江戸」。町の住む半数以上は町人であり、質素な長屋暮らしのなかでも衣食住に工夫をこらし、生き生きと生活していた。ファッション、美容、食、住居などには江戸ならではの文化が花開き天下泰平の大都市であった。意外と知られていない「江戸っ子」たちの生活の実態には、改めて教訓とすべきライフスタイルが詰まっている。
Amazon / Apple Books / 楽天Kobo






