江戸っ子は80歳まで生きた? 江戸の食に学ぶ「長寿法」
いま「学び直し」たい歴史
現在、日本人の寿命は世界的に見てもかなりの高水準に達している。しかし、今ほどの医療技術がなく、食料も豊かではなかった江戸時代においても、実は70歳や80歳を超え長生きしたという人物が少なくなかった。今回はこの江戸時代に行われていた「歴史」の産物から、日頃より実践できる食事の知恵を学びたい。(歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」より)
みずみずしい果物、野菜 初物で寿命がのびる

初鰹初物をさばいている女性。鰹は「勝魚」とも呼ばれた縁起物。天文6年(1537)北条氏綱が小田原沖に船を出していた時、船の上に鰹が飛び込んできた。その船で勝利を収めたことから出陣前に鰹を食べて縁起を担いだという。三代歌川豊国「十二月内 卯月 初時鳥」/国立国会図書館蔵
「初物七十五日」。江戸の町で盛んに用いられたことわざで、その季節の初物を食べると、75日長生き出来るというもの。
江戸の町は、江戸中期で人口が100万を突破し、世界一の大都会であったが、そのような超過密都市で暮らしていれば、常に気分転換が必要になる。そのひとつが「初物への熱中」だった。
ストレス解消の養生に、初物は役に立つ。みずみずしい果物、野菜等の初物を口にすれば爽快感を味わえるし、それらに含まれているビタミンCの効果も大きい。 ビタミンCはストレスに対する抵抗力を強くしたり風邪などの感染症を予防したりする上でも役に立つ。江戸の庶民たちにとって初物は長生きするための「初物長寿法」になっていた。
「魚であれ、果物、野菜であれ『初物』とつく物は人に先がけて食べる」という風潮があり、そこには、他人に負けたくないという江戸っ子気質があった。大店の主人から裏長屋の住人まで、全員参加で熱中したのである。現代でも初物をよろこぶ風潮は続いていて、たけのこ、木の芽、しょうが、初がつお、さんま、まつたけなどだ。

『新版御府内流行名物案内雙六』「売り出し」と「ふりだし」をかけた日本橋魚市場(下中央)から始まり、「山王御礼祭」の上がりまで物が双六形式で並んでいる。店舗型の名店の「どじょう」から屋台で食べられる「やぶそば」「むぎめし」まで紹介している。
一英斎芳艶/国立国会図書館蔵
監修・文/永山久夫
歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7
「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」
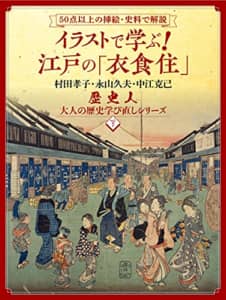
大人の歴史学び直しシリーズvol.7
世界に冠たる100 万人都市「江戸」。町の住む半数以上は町人であり、質素な長屋暮らしのなかでも衣食住に工夫をこらし、生き生きと生活していた。ファッション、美容、食、住居などには江戸ならではの文化が花開き天下泰平の大都市であった。意外と知られていない「江戸っ子」たちの生活の実態には、改めて教訓とすべきライフスタイルが詰まっている。






