水道も化粧水もなかった江戸で人々が清潔と美容を保った方法とは?
いま「学び直し」たい歴史
水道もエアコンも家風呂もなかった江戸時代。江戸っ子たちは清潔を保つために、どのようなことをしていたのか?現在でも真似してみたくなる、江戸っ子たちの清潔術を紹介する。(歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」より)
■各家庭にお風呂がなかった江戸時代の身体を洗う方法は『行水』

『名所江戸百景 王子不動之滝』国立国会図書館蔵
身体は銭湯でなく行水で洗ったようだ。手間はかかったが、美しくなるためには苦にならない、子供も庭や長屋の広場で洗う尊い時間であった。夏場になると“涼”を求めるために、タライにぬるま湯や水を入れ、大人も子供も汗を流したという。また上の絵に描かれている、現在の北区王子にあった滝。「滝浴み(たきあみ)」という夏の遊びの様子を描いており、江戸の人々は“涼”を求め、近郊の滝まで足を運び、滝に打たれるなどして涼んでいた。
■天然成分を活用した美容水で行っていた⁉ 「洗面」

歌川豊国「江戸名所百人美女 御殿山」/国立国会図書館蔵
洗面で使用する水は、糠(ぬか)や洗粉(あらいこ)を含ませ、石鹸がわりに用いられていた。糠には脂肪、ビタミン、タンパク質などが含まれており、天然のクリームの役割を果たした。糠以外にも糸瓜から取った「へちま水」を化粧水にするなど、江戸女性は天然の美容成分を活用していた。
■月に2~3回しか髪を洗わない⁉ 「洗髪」
水の手配が困難であった江戸時代の一般庶民は月2~3回程度のペースで行われた。髪を固め光沢をだすために、蝋、松脂、香油などを混ぜた「伽羅(きゃら)の油」を使った際には、油性の汚れを落としやすいアルカリ性の「火山灰」や「灰汁」を洗髪に用いた。
■歯ブラシがない江戸時代の「歯磨き」とは⁉

芳年『風俗三十二相 めがねそう 「弘化年間むすめの風俗」』/国立国会図書館蔵
房楊枝(ふさようじ)というものを使い、歯磨粉は千葉県から産出する磨き砂、房州砂に丁子、白檀などの香料で香りづけしたものを使用した。
■爪の清潔さにもこだわっていた江戸っ子たち 「爪切り」

豊原国周「当世三十二相 はさみがきれ相」/国立国会図書館蔵
爪が汚い人は「垢たまりて爪の先黒き」は笑われる。爪は短く清潔にが江戸銭湯には爪切り用の鋏があり、爪が柔らかいうちに手入れをした。
現在のように便利な道具がなかった江戸時代。自然にあるものを採用しながら、知恵と工夫で清潔を保っていた。
監修・文/村田孝子
歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7
「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」
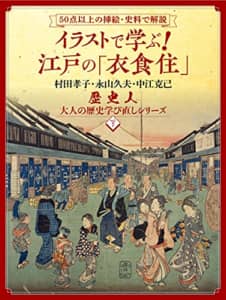
大人の歴史学び直しシリーズvol.7
世界に冠たる100 万人都市「江戸」。町の住む半数以上は町人であり、質素な長屋暮らしのなかでも衣食住に工夫をこらし、生き生きと生活していた。ファッション、美容、食、住居などには江戸ならではの文化が花開き天下泰平の大都市であった。意外と知られていない「江戸っ子」たちの生活の実態には、改めて教訓とすべきライフスタイルが詰まっている。






