江戸の食生活は豊かだった? 現代よりデリバリーが充実していた庶民の朝食
いま「学び直し」たい歴史
当時の世界の主要都市と比べても人口が多かった江戸は経済も高水準であり、政治も安定。庶民も生き生きとした暮らしが実現していたと伝わる。食の面でも独自の文化が発展し、「食を楽しむ」という風潮があった。現在、日本だけでなく世界でも重宝されている食事のデリバリーサービスは、江戸において、なくてはならないものであり、ウーバーイーツに負けないほどの充実度があったというのだから驚きだ。(歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」より)
世界最大の大都会だった江戸町人家庭の〝豊かな〟ご飯

『日ごとの心得』汁が省略された町家の食事。室町時代末期、僧の間で点心が普及し、元和、寛永の時代は2食だったが、明暦の大火の復興で朝夕の2食では体力が持たない庶民にも3食が広まる。(国立国会図書館蔵)
江戸時代の中期になると、江戸の人口は100万人以上にふくらみ、大都会に成長していた。
当時、ヨーロッパ最大の都市といわれたロンドンの人口が85万人位とみられており、何と江戸は世界最大の都市人口なのである。
100万人の約70パーセントが庶民で、この人たちの住まいが長屋であり、借家の集合住宅。明六(あけむつ)[午前6時頃]に路地口にある木戸が開けられ、この頃に住人たちは起き出して朝の支度にかかる。
長屋は6畳一間の狭い間取りで、台所はあるが、井戸とトイレは共同で使う。
朝起きると、井戸で水をくみ、家の水瓶まで運ぶ。井戸端で口をすすいだり、顔を洗ったりした後は、家に帰って炊事の支度をする。
江戸の食文化について記録した『守貞漫稿(もりさだまんこう)』によれば、「平日の飯は江戸では朝に炊き、味噌汁に合わせ、昼と夕は冷飯を食べる。ただし、昼は一菜を添え、野菜や魚肉などは、必ず昼食に食べるが、夕食は茶漬けに香の物を添えるだけ」とある。
これに対して、上方では飯を炊くのは昼食で煮物や魚類、または2、3種を合わせて食べ、朝食と夕食は冷飯と香の物が中心だった。
しじみや納豆売りに起こされ味噌汁で始まる朝食

醤油の仕込み『広益国産考』江戸中期以降、関東の下総・上総・相模・常陸で醤油づくりが盛んになり、おかずに醤油をかけて食べるのが普通となっていた。大蔵永常が醤油の製造工程を詳しく解説している。(国立国会図書館蔵)
江戸は便利な町で、早朝から行商の棒手振りが、朝食にすぐに役立つ食材を担って家の前までやってくる。
○納豆としじみに朝寝起こされる
当時の川柳で、長屋の朝は納豆としじみの売り声で始まった。
○納豆を帯ひろ解けの人が呼び
「納豆屋さーん」。あわてて飛び出して来たおかみさんの着物の前がはだけ、帯を引きずっている。
納豆には2種類あり、叩き納豆と糸引き納豆。叩き納豆は刻んだ納豆に豆腐と野菜が添えてあり、台所に用意しておいた味噌汁に入れて火にかけると立ち所に納豆汁。こちらは家族の多い家で用いられる場合が多い。独身の場合は、糸引き納豆を求め、醤油でかき混ぜご飯にぶっかけかっ込み食い。
惣菜が足りなければ棒手振りから煮豆や漬物、でんがくなどを買ってもよい。麦めしも売りに来たが、こちらは独身者用である。通りに出れば屋台店が並び、その中には煮豆などのお惣菜を4文均一で売る四文屋(しもんや)もあった。1文は20円位だから何を買っても80円位。
屋台には大福や焼き餅、饅頭類を提供する餅菓子屋もあり、長屋の独身者や大店の住み込み店員、下級武士たちに人気があった。
監修・文/永山久夫
歴史人電子版 大人の歴史学び直しシリーズvol.7
「イラストで学ぶ! 江戸の『衣食住』」
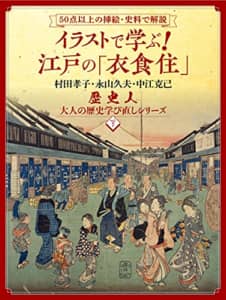
大人の歴史学び直しシリーズvol.7
世界に冠たる100 万人都市「江戸」。町の住む半数以上は町人であり、質素な長屋暮らしのなかでも衣食住に工夫をこらし、生き生きと生活していた。ファッション、美容、食、住居などには江戸ならではの文化が花開き天下泰平の大都市であった。意外と知られていない「江戸っ子」たちの生活の実態には、改めて教訓とすべきライフスタイルが詰まっている。






